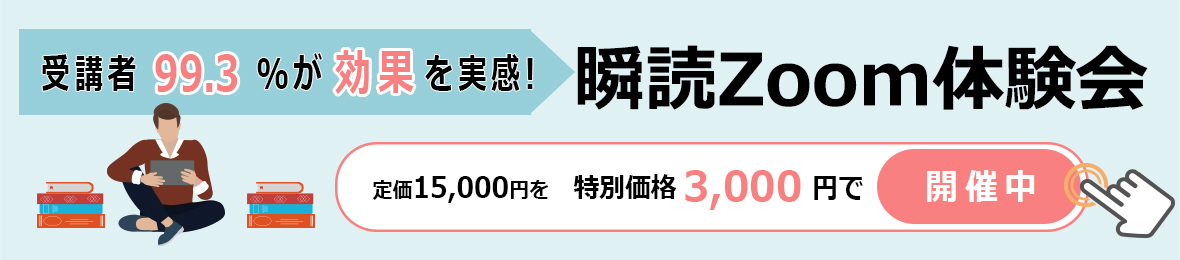記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
私たちは日常生活のなかで、「どうしても思い出せない」「あと少しで出てきそうなのに」という経験をよくします。これは単に記憶力が悪いからではなく、脳の仕組みや生活習慣、情報の扱い方に原因があることも多いのです。
この記事では、思い出せない理由を整理しながら、今すぐ実践できる思い出しのコツや、記憶を引き出しやすくする習慣づくりについてわかりやすく解説していきます。
目次
なぜ思い出せないのか?原因を知ることが第一歩
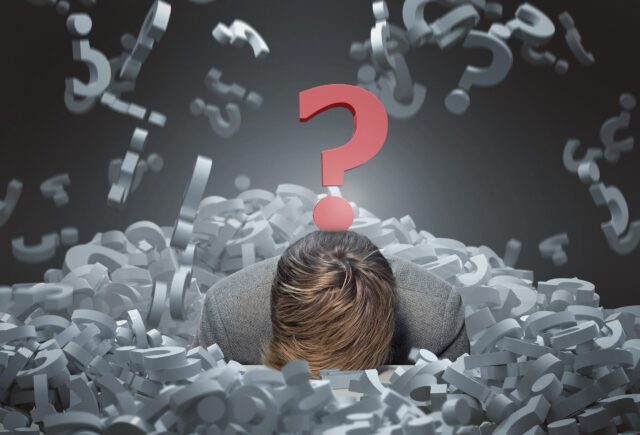
思い出せないことが増えてきたら、まずは原因を知ることが、思い出す力を取り戻す第一歩です。ここでは、脳の記憶プロセスやストレス・情報過多といった代表的な要因を整理して解説していきます。
◆記憶力低下の主な原因については、コチラの記事でもお読みいただけます
脳の仕組みと記憶のプロセスを理解する
記憶を思い出すためには、まず記憶の流れを理解しておくことが大切です。記憶は、「記銘(情報の記憶)→保持(記憶の保持)→想起(記憶の取り出し)」というプロセスを経て成り立っています。この流れのどこかに不具合があると、スムーズに思い出せなくなるのです。
たとえば、記銘や保持に問題があり、インプットした情報を覚えられない状況になると、通常「認知症」と診断されます。認知症ではない人が思い出せない場合は、記銘や保持ではなく、想起に問題のあるケースが多いです。
こういうケースでは、記憶のフックを事前に仕込んでおくと、記憶の呼び出しがスムーズになります。(具体的な方法については、「記憶を思い出しやすくする習慣づくり」で紹介)
いずれにせよ、記銘・保持・想起がバランスよく機能していないと、うまく思い出せないことが増えてきます。記憶力に不安を感じているなら、できるだけ早く対応策に取り組んでいきましょう。
◆記憶の基本プロセスについては、コチラの記事でもお読みいただけます
ストレスや疲労による記憶力の低下
記憶力が低下する大きな要因のひとつが、ストレスや疲労です。強いストレスを受けると、脳内でストレスホルモン(コルチゾール)が分泌され、記憶の保存や取り出しを担う海馬の働きが抑えられてしまいます。
また、睡眠不足や長時間の労働で疲労が蓄積すると、前頭葉の活動も鈍り、集中力や判断力が落ちて情報を思い出しにくくなります。徹夜明けで人の名前や会議の内容が思い出せなかった、という経験を持つ人も多いでしょう。それは、睡眠不足で脳が十分に休息を取れなかったことが原因です。
つまり「思い出せない」の背景には、記憶力そのものの衰えだけでなく、ストレスや疲労による一時的な脳機能の低下が隠れている可能性があるのです。そういう場合は、なによりも心と身体のケアを優先してください。
情報過多による脳の混乱
現代社会では、ネットやSNSなどから、毎日嫌でも膨大な情報が入ってきます。そのため、過剰な情報が、「思い出せない」現象を引き起こしているケースが非常に増えているのです。
脳が処理できる情報量には限界があり、一度に大量のデータを抱え込むと、必要な記憶が埋もれてしまいます。SNSやメール、ニュースなどを次々にチェックしていると、記憶の優先順位が乱れてしまい、本当に残したい情報が長期記憶として残ってくれなくなってしまうのです。
たとえば、重要な会議の直後に SNSを見てしまったとしましょう。会議の内容はSNSの情報に上書きされてしまい、会議の記憶が薄まってしまいます。こうなると、あとから会議の内容を思い出そうとしても、なかなかうまくいきません。
情報過多による弊害が出ているなら、情報を意図的にストップしない限り、ますます必要な情報を思い出せなくなってしまいます。
すぐにできる!思い出すためのテクニック

なかなか思い出せないときでも、ふとしたきっかけで記憶が蘇るケースは少なくありません。記憶の取り出しがうまく機能していない人は、思い出すためのフック(きっかけ)を決めておくと、記憶を思い出しやすくなります。
この章では、記憶のフックの呼び起こし方について、5つのアイデアをご紹介します。
キーワードや関連情報から連想する
思い出せないときは、関連するキーワードを手がかりに連想してみるのが効果的です。記憶は単独で保存されているのではなく、似た情報同士が複雑に絡み合って記憶に保存されています。
そのため、周辺の情報について考えているうちに、いつの間にか目的の情報を思い出すということがよくあります。たとえば、打ち合わせをした人の名前を思い出したいときに、相手の名前にフォーカスしてしまうと、なかなか思い出せません。
ところが、打ち合わせをした場所や同席した人、話した内容などを思い浮かべると、記憶の糸口が見つかるケースも多いものです。思い出せないときこそ、周辺情報にフォーカスして、どんどん記憶を引っ張りだしてあげましょう。
五感を使って記憶を呼び起こす
思い出せないときは、視覚や聴覚、嗅覚など五感を刺激すると、スーッと記憶が蘇ることがあります。脳は情報を単に文字や言葉として保存しているのではなく、音や匂い、映像といった感覚とセットで記憶しているからです。
たとえば、昔聴いた音楽を耳にした瞬間に、そのときの情景や気持ちが一気に浮かんできた経験はないでしょうか。また、特定の香りで美味しいものを食べた記憶や、友達と行った旅行先を思い出すなどということもよくあります。
このように記憶と五感は密接に結びついているため、関連する感覚を意識すると、それが記憶の引き金になってくれることがあるのです。
場所や感情を頼りに思い出す
思い出せないときは、情報を得た「場所」や「気分」を手がかりにすると効果的です。人間の脳には、覚えたときと同じ環境(感情なども含む)にいると記憶を思い出しやすいという性質があります。こういった性質を、心理学では「文脈依存記憶」といいます。
たとえば、思い出したいのが会議の内容だとしたら、会議室の雰囲気や座っていた位置、聞こえた音、室温、そのときの自分の感情まで順に再現してみましょう。
現場に行けない場合でも、頭のなかで当時の状況をできるだけ細かくイメージすればOKです。環境や感情を忠実に再現するほど、思い出す確率は大きく高まります。
目をつぶって記憶へ深くダイブする
なかなか思い出せないときは、いったん目を閉じて雑念を遮断しましょう。視覚から入る刺激がなくなると、脳は内部の情報処理に集中しやすくなり、埋もれていた記憶が浮かび上がってくることがあります。
前述の文脈依存記憶を利用して人の名前を思い出そうとする場合も、目をつぶって当時の雰囲気や会話の内容を頭のなかで再現してみるのです。余計な外部情報を遮断すると、脳の検索機能が促進され、文脈依存記憶の効果がより強く働いてくれます。
目を閉じるというのは、本当に単純で誰でもできる方法です。ですが、静かな場所で行うと、その効果は抜群です。思い出せなくて焦ってしまうときは、目を閉じて不要な外部情報を入れないようにしてみてください。そうすれば、きっと記憶が蘇ってくるはずです。
最初からやり直してみる
どうしても思い出せないときは、思い切って最初からやり直すのもひとつの方法です。記憶は、前後の情報とつながりを持ちながら保持されています。そのため、起点から順に流れを再構築すると、その流れのなかで抜け落ちた箇所に再び出会える可能性が高いです。
ただ多くの人は、同じことの繰り返しを嫌がります。単純に、同じことをするのが面倒だからです。しかし、思い出せない状態のまま、思い出せないことにフォーカスしても、なかなか思い出せません。
たとえば、アプリの設定方法を思い出せないなら、アプリのダウロードからやり直してみるのです。そのあとアプリを起動して、メニューを開いて、設定ボタンを押してという作業をしているうちに、「そうだ!◯◯にチェックを入れればよかったんだ」と思い出すかもしれません。
「出発点に戻る」という単純な行動ですが、その思い出すきっかけをつくる効果は、非常に大きいといえます。行き詰まったときは、ぜひいちど出発点に戻ってやり直してみてください。
記憶を思い出しやすくする習慣づくり

記憶は一度きりの工夫で劇的に改善するものではなく、日々の習慣の積み重ねで思い出しやすさが大きく変わります。最後に、思い出す力を高めるためにぜひ取り入れたい習慣を4つ紹介していきます。
メモを習慣化する
記憶を確実に思い出すためには、日常的にメモを取る習慣が役立ちます。人の脳は一度に多くの情報を保持できません。そのため、頭のなかだけで覚えておこうとすると、せっかく覚えた情報の多くを取りこぼしてしまいます。
その点、ちょっとした用事やアイデアもメモに残しておけば安心です。メモさえあれば、時間のあるときに見返して、じっくりと覚えられます。
メモが真価を発揮してくれるのは、会議や打ち合わせです。受け取る情報量が多いので、メモをしておかないととてもカバーできません。頭のなかで覚えておこうとすると、覚えることに意識が向き、肝心の理解が追いつかない危険性があります。
また、メモを取る行為そのものが、「書いた」という経験として記憶を強化してくれる効果もあります。記憶の抜け落ちのないように、そしてあとから確認できるように、ぜひメモを習慣化していきましょう。
◆効率のよいメモの取り方については、コチラの記事でお読みいただけます
定期的な復習で記憶を強化する
記憶を長く保つためには、定期的な復習が欠かせません。人の脳は、時間の経過とともに、覚えた情報を忘れてしまう性質があります。しかも、放置する時間が長くなるほど、思い出すのにも時間がかかってしまうのです。
そこでオススメしたいのが、適度な間隔を空けた復習(スペースド・リピティション)です。1978年の古い研究※でも、すでに「復習は忘れる前より、忘れかけた頃に行うのがもっとも効果的である」ということがわかっていました。
その日に復習して終わりではなく、数日後、1週間後、1か月後と、少しずつ間隔を広げて復習すると、記憶が長期保存されやすくなります。
学生時代の試験勉強でも、一夜漬けで覚えた内容は、試験が終わるとすぐに忘れてしまいましたよね。でも、何回も繰り返し覚えた知識は、何年経っても覚えているものです。しっかりと覚えておきたい内容については、間隔を空けた定期的な復習をオススメします。
※:Want to Remember Everything You’ll Ever Learn? Surrender to This Algorithm | WIRED
◆間隔復習(スペースド・リピティション)については、コチラの記事でもお読みいただけます
情報をストーリー化して覚える
記憶を思い出しやすくする方法として、ストーリー法(物語法)は非常にオススメです。脳はバラバラの数字や単語よりも、物語の流れのように関連づけられた情報を長く保持しやすい性質を持っています。
だから、覚えたい情報を組み合わせてひとつのストーリーをつくり、そのストーリーごと記憶していくわけです。たとえば、「牛乳、コーヒー、卵、パン」という買い物リストを覚えたい場合、「朝食に牛乳を入れたコーヒーを飲み、卵を挟んだパンを食べた」という短いストーリーを考えます。
ただ、バラバラにリストを覚えるより、ストーリーのほうが圧倒的に覚えやすいと思いませんか?
なお、ストーリー法以外にも、場所法やペグ法など、いわゆる記憶術は数多くあります。記憶術については、別記事で詳しく紹介しているので、ぜひそちらも読んでみてください。
◆ストーリー法については、コチラの記事でもお読みいただけます
興味や感情を伴う学び方を意識する
記憶には、「自分の興味や感情と結びついた情報ほどしっかり定着する」という性質があります。これは、感情の処理を担う扁桃体が海馬と連携し、印象的な体験を優先的に記憶へ残そうとするからです。
たとえば、強盗に襲われそうになった記憶は、おそらく一生忘れませんよね。これは、恐怖という感情を伴った記憶を留めておき、また同じような状況になったら、素早く対処できるようにという本能のようなものです。
もちろん、これは極端な例であり、もっとマイルドな喜びや楽しみ、面白さといった感情であっても同様の効果が得られます。
同じ勉強をするにしても、いつもひとりで黙々と勉強していたら、記憶の効率は上がりません。たまには、気分を変えて友達と問題の出し合いをしてみるのはどうでしょうか。当たって嬉しい、間違えて悔しいといった感情が記憶の後押しをしてくれます。
このように、興味や感情の動きをインプットに取り入れると、記憶の定着度は大きくアップします。忘れっぽい人は、ぜひこういった方法を取り入れてみてください。
まとめ
思い出す力は特別な才能ではなく、正しい知識と習慣で誰でも高められます。今回紹介した方法を基に、ぜひ思い出す力を磨いていっていただければと思います。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読