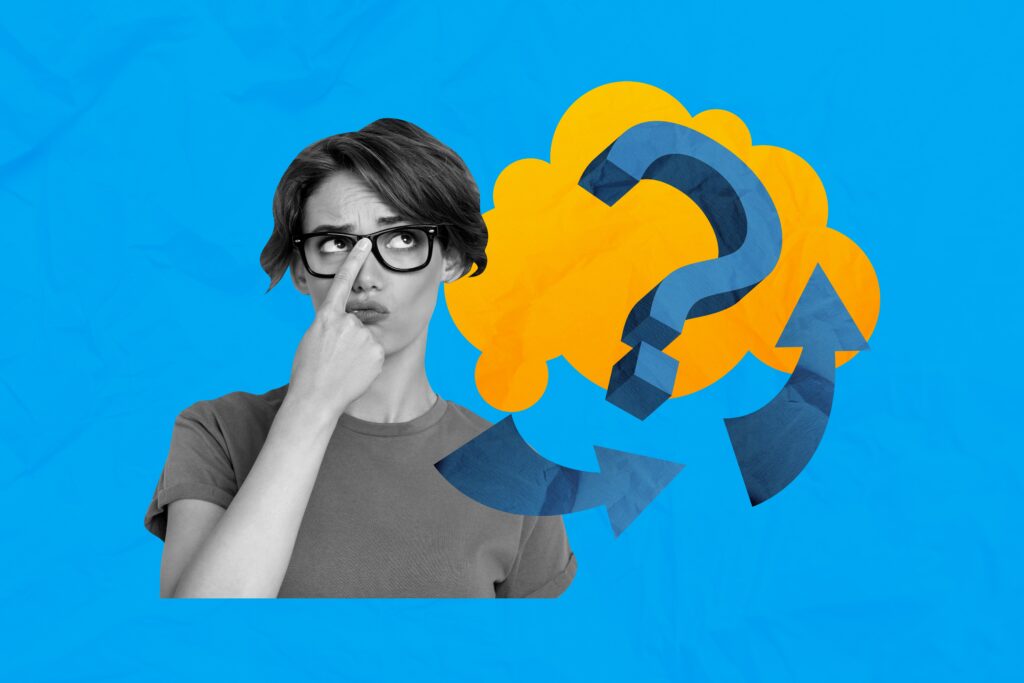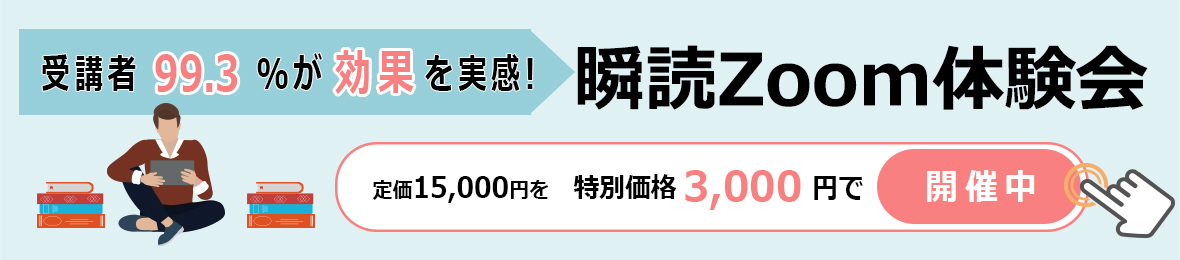記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
思考力は、生まれつきの才能ではなく、日々の習慣やトレーニングで鍛えられる能力です。この記事では、初心者でも今日から実践できる思考力の鍛え方をわかりやすく紹介します。もし思考力不足で悩んでいるなら、ぜひ今回紹介する思考力トレーニングに取り組んでみてください。
目次
思考力が高いとどんなメリットがある?

思考力は、日常生活からビジネスシーンまで、あらゆる場面であなたの判断や行動に影響を与える重要なスキルです。では、思考力が高い人は、実際にどのような場面で優れた思考力の恩恵を受けているのでしょうか?
この章では、優れた思考力によって得られる具体的なメリットを、3つの視点からわかりやすく紹介します。
複雑な問題に冷静に対応できる
複雑な問題に直面したとき、思考力が高い人は冷静に状況を整理し、的確な対応ができます。なぜなら、思考力のある人は「感情」と「論理」を切り分けて、冷静に考えられるからです。
たとえば、職場でトラブルが起きたときに、思考力の浅い人は、表面的な出来事だけに反応します。一方優れた思考力をもつ人は、「なぜそれが起きたのか」「解決の糸口はどこにあるのか」といった問題の背景までしっかり目を向けているのです。
実際、業務でトラブル対応が得意な人は、原因分析・情報の整理・優先順位づけといった思考プロセスを無意識のうちにおこなっています。でも、こういう人も最初からスムーズな思考ができていたわけではありません。
焦らず冷静に行動できるのは、日頃から「考える練習」をしているからこそです。このように、思考力を高めて感情に流されず問題へ対応できるようになれば、周囲からの信頼も自然と高まっていきます。
仕事のパフォーマンスが上がる
思考力がレベルアップすると、仕事の効率や成果が大きく向上します。なぜなら、物事の優先順位を見極めたり、課題を整理してスムーズに進めたりできるからです。
ただ与えられた作業をこなすのではなく、「なんのためにやるのか」「もっとよいやり方はないか」といった視点で考えるクセがつくと、自然とムダな動きが減っていきます。
たとえば資料作成ひとつを取っても、目的を明確にし、構成を練ってから取りかかる人ほど修正の手間が少なく、完成度の高い資料を作成できます。
一方で思考力が不足していると、目的や依頼者の意図を確認しないまま作業を始めてしまい、方向性のズレやムダな手戻りが発生しがちです。そうなると、あなたの評価はどうしても下がってしまいます。
仕事のパフォーマンスを上げて、相応の役職や給与を得るには、やはり「上司や取引先の意図を正確に読み取り、期待に応える力」が不可欠なのです。
対人関係や交渉力もスムーズに
思考力に優れた人は、人間関係や交渉の場面でもスムーズに対応できます。というのも、相手の立場や意図を冷静に読み取り、自分の考えを論理的に伝える力が備わっているからです。
ただ自分の意見を主張するのではなく、「相手はなにを求めているのか」「自分はなにを伝えるべきか」といった相手の立場に立った思考ができるので、会話のズレや衝突がほとんど発生しません。
たとえば、上司に提案を通したいときでも、相手の関心や不安に配慮しながら説明を組み立てます。だから、条件のむずかしい案件でも、相手に納得してもらえる確率が高いのです。
結果として、職場での信頼関係が深まり、ますます対人関係がうまく回りだします。
相手から「あの人なら大丈夫」と言ってもらえるようになれば、もうしめたものです。より重要な打ち合わせや商談に参加する機会が増え、成果もどんどん出せるようになっていきます。
今日からできる思考力トレーニング法

むずかしい勉強や専門知識がなくても、身近なことを少し意識するだけで、考える力は着実に伸びていきます。この章では、初心者でもすぐに始められる思考力トレーニングを5つご紹介します。どれも日常生活に取り入れやすい内容なので、ぜひ気軽に試してみてください。
まずは「なぜ?」を繰り返してみる
物事に対して「なぜ?」と問いかける習慣が、思考力を鍛える第一歩になります。「なぜ?」を繰り返すと、表面的な理解から一歩踏み込んだ本質的な考えにたどり着けるからです。
たとえば、「今日は仕事でミスが多かった」と感じたときに、「なぜミスが起きたのか?」「なぜ確認を怠ってしまったのか?」と自問してみてください。そうすると、単なる結果だけでなく、その背景や原因が見えてきます。
なぜ?の気持ちがないと、ミスの原因はそのまま。おそらくまた同じようなミスを繰り返すでしょう。そうすれば、周囲からの信頼も失ってしまいます。
思考力を磨くには、子どもが「なぜなぜ期」を通じて自己成長するように、大人も物事を深く追求する意識が必要です。
毎日1つ「アイデア出し」の習慣をつける
優れた思考力を身につけるために、毎日1つでもいいので、アイデア出しを実践してみてください。なぜかというと、新しい発想を得るためには、柔軟な発想力や直感力、論理的な思考が必要だからです。
「朝食をもっと効率よく作る方法は?」「この商品を別の使い方で活用するには?」といった簡単なテーマでも構いません。重要なのは、アイデアの内容や正解を出すことではなく、「考えるクセ」をつけること。
1日1テーマ、自分なりに考えてメモするだけでも、思考の引き出しは確実に増えていきます。このように日々のアイデア出しは、ひらめきや問題解決力を磨く強力なトレーニングです。まずは、1日1アイデアを目標に、今日から取り組んでいきましょう。
他人の意見に「反論」してみる
他人の意見に対してあえて反論を考えてみるのも、思考力を鍛えるうえで非常に効果的です。なぜなら、反論を考える行為が、自分とは異なる視点を深く考察するきっかけをくれるからです。こういった思考法を、「クリティカルシンキング(批判的思考)」といいます。
もちろん、実際に対立を生むような反論を仕掛ける必要はありません。心のなかで「この考えに別の見方はあるか?」と問うだけでも十分です。
たとえば、ニュース番組でコメンテーターの意見を聞いたときに、「本当にそれが唯一の解決策なのか?」「ほかの立場の人はどう感じるだろう?」といった問いを立ててみましょう。
あくまでも、自分の固定観念を捨て去り、新しい可能性について思考を巡らすのが目的です。だから、答えが見つからなくてもまったく問題ありません。こういった積み重ねが、あなたに深い思考力をもたらしてくれます。
相手より優位に立つためではなく、自分の思考力を磨くため、ぜひクリティカルシンキングを取り入れてみてください。
◆クリティカルシンキングについては、コチラの記事でもお読みいただけます
マインドマップで思考の整理を習慣に
思考力を鍛えるためには、「マインドマップ」を使った頭のなかの整理整頓を強力にオススメします。マインドマップはひとつのテーマから連想を広げる構造になっていて、自分の思考を可視化できます。そのため、思考の全体像や抜けている部分が、ひと目でわかるのです。
たとえば、「副業を始めたい」と思ったときには、まず中心に「副業」と書きます。そこから「やりたいこと」「使える時間」「スキル」「リスク」「資金」といった要素を枝葉のように広げていくのです。
思考を頭のなかだけでまとめるのは、想像以上にむずかしいものです。しかしマインドマップの場合は、既出の情報を確認しながら必要な要素をすべて書き出すので、あとから「あー、◯◯を忘れていた」ということがほとんどなくなります。
よく大事なことを忘れてしまう、思考がまとまらない、できるだけ失敗をしたくないという人は、ぜひマインドマップを活用していきましょう。
◆マインドマップについては、コチラの記事でもお読みいただけます
読書でさまざまな価値観に触れる
なにかひとつだけ思考力のトレーニングを選ばなければならないとしたら、迷わず読書をオススメします。なぜなら、読書によって多様な価値観に出会えるからです。
私たちは、どうしても自分の思考パターンを通して物事を判断しようとします。もちろん、自分の考えをもつのは大切なことです。しかし、自分以外の考えを受け入れられないと、失敗も増えるし、周囲との摩擦も避けられません。
書籍にはそれこそ著者の数だけ異なる価値観が込められており、読書によってさまざまな視点や価値観に出会えます。そうやって新しい価値観との出会いを重ねて、次第に多角的に捉える力が育ってくるのです。
自分の知らない知識や考え方が、わずか2,000円弱で手に入るのですから、本を読まないのはあまりにももったいなさすぎると思いませんか。
また読後には、ぜひ先ほど紹介したクリティカルシンキングで、本の内容を振り返ってみてください。そうすると、著者の意見を鵜呑みにすることなく、必要な情報を正確に入手できます。
◆読書のメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
年齢別・目的別のオススメ思考力トレーニング

思考力を鍛える方法は、年齢や目的によって最適なアプローチが異なります。子どもには楽しみながら取り組める工夫が必要ですし、ビジネスパーソンには実践的なトレーニングが効果的です。
この章では、子ども・学生・社会人・高齢者といった立場ごとに、無理なく続けられる思考力トレーニングを紹介します。自分に合った方法を見つけて、ぜひ日常に取り入れてみてください。
子どもには「なぞなぞ」「ボードゲーム」が効果的
子どもの思考力の育成は、「なぞなぞ」や「ボードゲーム」のように、遊びと学びがセットになっていないとなかなかむずかしい側面があります。というのも、子どもはどうしても集中できる時間が短く、興味のないものにはすぐに飽きてしまうからです。
あくまでも、遊んでいるうちに自然と思考力が身につくよう、大人が考えてあげないといけない。この点が、自主的に思考力を鍛えようとする大人との大きな違いです。
たとえば、子ども向けのウミガメのスープクイズ(「はい」「いいえ」「関係ありません」だけしか返答できない質問をして答えを導く水平思考クイズ)などは、子どもが喜んで食いついてくれます。
オセロや将棋のような戦略系ゲームもオススメです。相手の打ち筋を見極めないと勝てないので、他人の思考をくみ取る感性が自然と身につきます。
なにを選ぶにせよ、子どもだけでなく、親子で一緒に楽しみながら思考力を鍛えるのがポイントです。遊びの時間がそのまま「考える練習」になる。そんな環境づくりをぜひ意識してみてください。
◆将棋の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
学生には「ディベート」や「ジャーナリング」がオススメ
ある程度自立した高校生や大学生には、「ディベート」や「ジャーナリング」といったアウトプット型のトレーニングが効果的です。
ディベートは、物事を論理的に整理しながら相手に伝える力を養うのに適しており、一方のジャーナリングは、自分の内面を見つめ直しながら考えを言語化する力を育てます。
「話す」と「書く」、形式は異なりますが、どちらも思考の整理や深掘りに役立つトレーニングです。
とくに10代は、多感な時期であり、社会や環境への関心が芽生えてくる時期でもあります。たとえば、環境問題や経済格差といったテーマについて「賛成・反対」の両面から考えるディベートは、自分の視野を広げる格好の訓練になります。
また、日々感じたことや考えたことをノートに書き出すジャーナリングは、感情の整理と自己理解を深めるうえで大きな助けになってくれるでしょう。
こうした取り組みを続けることで、「ぼんやりとした考え」からステップアップして、筋道を立てて考えられる力が少しずつ身についていきます。
◆ジャーナリングのメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
ビジネスパーソンは「ロジカルシンキングの練習」を
ビジネスの現場で思考力を活かすには、「ロジカルシンキング(論理的思考)」の練習が欠かせません。
なぜなら、説得力のある提案をするには、筋道の通った考え方が不可欠だからです。とくに、会議や報告の場では、感情や思いつきではなく、明確な理由と対策の提示が求められます。
そういった思考に慣れていない人は、パターン化されたフレームワークがオススメです。たとえば、「結論→理由→具体例」の順で伝えるPREP法や、細分化した要素をツリー状に配置して整理するロジックツリーなどは、あらゆるビジネスシーンで活用できます。
また、フレームワークを使うと、判断材料の抜け落ちがほとんどなくなります。その分、精度の高い判断ができるので、ロジカルシンキングに慣れるまでは、どんどんフレームワークを活用していきましょう。
◆ロジカルシンキングについては、コチラの記事でもお読みいただけます
高齢者には「脳トレアプリ」や「書く習慣」が有効
高齢者が思考力を保つための取り組みとして、「脳トレアプリ」や「書く習慣」は非常にオススメです。年齢とともに脳の働きがゆるやかに低下していくなか、意識的に脳を使う時間をもてば、認知機能の維持や活性化が期待できます。
たとえば、ゲーム感覚で楽しめるアプリや、手を動かしながらじっくりと考える作業なら、高齢者でも無理なく続けられるでしょう。
さいわい、間違い探し、クロスワードパズルなど、記憶力や判断力といった認知機能を幅広く鍛えてくれる脳トレアプリが数多くリリースされています。目的に応じて適切なアプリを選べば、より効率的なトレーニングが可能です。(目的別のアプリ紹介は別記事に掲載しています)
一方、日記やジャーナリングなど「書く習慣」も、思考力を養ううえで大切な取り組みです。 高齢者になると、健康や人間関係などについて、どうしても不安を感じやすくなります。
しかし日頃から日記やジャーナリングに自分の感情を書き出していると、自分の感情と冷静に向き合えるようになり、前向きな思考が生まれやすいです。
むずかしく考える必要はありません。楽しみながら脳を使うこと。それが、年齢を重ねても思考力を保ち続ける一番の秘訣です。
◆オススメの脳トレアプリについては、コチラの記事でお読みいただけます
◆ジャーナリングについては、コチラの記事でお読みいただけます
まとめ
思考力は特別な才能ではなく、日々の習慣や工夫で誰でも鍛えられる能力です。今回ご紹介したトレーニング法は、どれも今日から始められるシンプルなものばかり。
年齢や目的に合った方法を見つけて継続できれば、考える力は確実に伸びていきます。ぜひ日常生活のなかに取り入れて、より深く、より柔軟に考えられる自分を育てていきましょう。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読