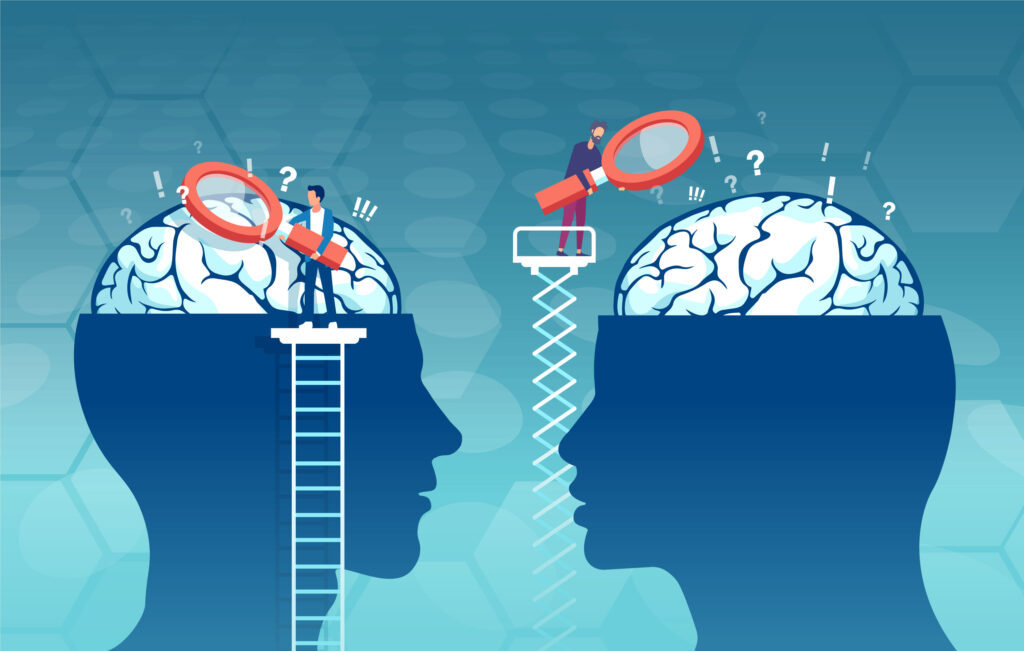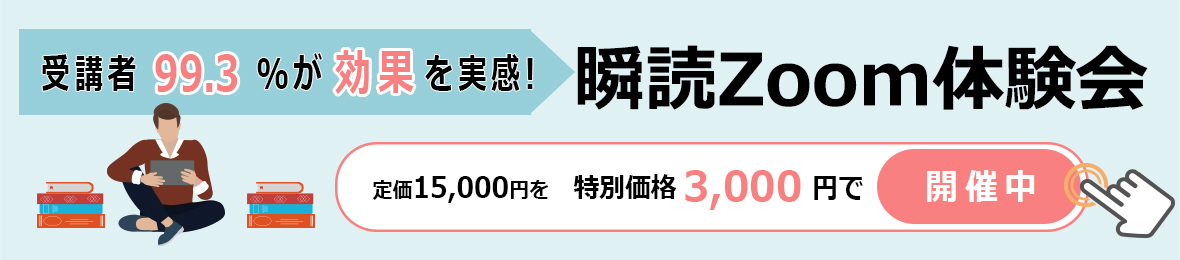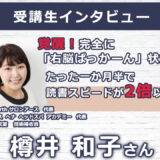記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
ある程度年齢を重ねてくると、集中力の低下や記憶力の衰えなど、さまざまな機能の衰えに大きなストレスと不安を感じてくるものです。
この記事では、そういった脳機能の衰えを最小限に抑えるべく、誰でも簡単に取り組める脳活習慣を紹介しています。脳活をうまく生活に取り入れられれば、心身両方の健康が向上し、生活のクオリティは大きく向上します。
ぜひ脳活を習慣化して、快適な毎日を手に入れましょう!
目次
脳活性化のメリットとその重要性について

脳活をする前に、まずは脳活性化のメリットを押さえておきましょう。
- 健康面の変化
- 記憶力など機能が向上
- ストレス軽減
今回は数あるメリットのなかから、上記3点をピックアップして解説していきます。
脳活性化がもたらす健康面の変化
脳活といえば、認知症の予防というイメージをもつ人がほとんどです。しかし、脳活は私たちの健康面に対しても、大きな変化をもたらしてくれます。
まず、脳活をおこなうと、脳が刺激を受けて活動的になります。新しい刺激に対応できるように、神経細胞がネットワークを強化しようと働き出すからです。
また脳活を習慣化すると、血流が改善され、脳の栄養源であるブドウ糖や酸素がスムーズに供給されるようになります。脳は思考や肉体の動きを司る重要な器官なので、脳の働きが活性化すれば、必然的に体全体の機能が改善されるわけです。
また数ある脳活のなかでも、ウォーキングやリズム体操のような有酸素運動は、心肺機能を向上させ、全身の血流を改善してくれます。クイズのような頭を使うものだけでなく、ぜひ体を動かすタイプの脳活も習慣化したいですね。
◆ウォーキングなど脳と運動の関係については、コチラの記事でお読みいただけます
脳活性化で記憶力と集中力がアップ
脳活が習慣になれば、記憶力や集中力のレベルアップが期待できます。前述のとおり、脳活によって脳内の神経ネットワークが強化されるので、情報を効率的に処理できるようになるからです。
また脳活によって、記憶の司令塔とよばれる「前頭前野」や「海馬」も、同時に鍛えられます。そうなれば、知識量が増えて、そのぶん仕事や勉強で成果を出しやすくなります。とくに受験を控えた学生にとって、脳活は大きな助けになってくれるでしょう。
もちろん、心情的に「脳活よりも勉強をしたい」と考える人がほとんどだと思います。しかし週に数回、1回15分くらいなら、とくに勉強の妨げにはならないはずです。
なお前頭前野は、感情(集中力も含む)をコントロールする重要な役割も担っています。脳活により感情が安定すれば、ビジネスでもプライベートでも、安定したパフォーマンスを発揮しやすくなるのは間違いありません。
結果を求められる忙しい人ほど、脳活によって得られる恩恵は、大きなものになると思いますよ。
◆記憶力を改善する方法については、コチラの記事でお読みいただけます
脳活性化によるストレス軽減とリラックス効果
脳活のメリットといえば、ストレス軽減とリラックス効果も見逃せません。たとえば、瞑想やヨガといったリラックス効果の高い脳活習慣は、心身の緊張を解放し、ストレスを軽減してくれます。
ウォーキングや軽めの筋トレも、ストレス解消にはもってこいです。前述のとおり、体を適度に動かすタイプの脳活トレーニングは、全身の血流をよくしてくれます。
しかも、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を抑える効果もあるので、ストレスに苦しんでいる人は試してみる価値が十分あるでしょう。
また、楽器の演奏や絵画などのクリエイティブな脳活習慣も、ストレス解消の有効な手段になり得ます。自分のなかにある思いや創造性を自由に表現するのは、本当に気持ちのいいものです。その表現方法は人それぞれですが、こういったアート系の脳活も、ぜひ取り入れてみていただきたいですね。
◆絵画の脳活効果については、コチラの記事でお読みいただけます
習慣化しやすいオススメの脳活方法

脳活を習慣化するメリットがわかったところで、今度は脳活を習慣化するための具体的な方法を10個紹介します。どの方法にも優劣はないので、自分のやれそうなことから、取り組んでみてください。
体にいい食生活で脳の働きを改善
脳活の目的は、脳の働きを活性化することです。そのためには、まず脳が正常に働く下地をしっかりとつくる必要があります。となると、まず考えるべきは、食事です。脳も体の一部である以上、食べるものの影響を強く受けています。
脳の主な栄養源は、ブドウ糖です。しかし、ブドウ糖だけを摂取していればよいわけではありません。セロトニンのような神経伝達物質を適量分泌するには、タンパク質やビタミン・ミネラルといった栄養素が必要になります。
ところが、忙しい現代人は、どうしても炭水化物中心の食事になりがちです。もちろん、炭水化物は重要な栄養素のひとつですが、過剰に摂りすぎると脳の働きを鈍らせます。
「たんぱく質13〜20%」「脂質20〜30%」「炭水化物50〜65%」(年齢と性別で異なる)を目安に、バランスのよい食事を心がけましょう。
なお、オメガ3脂肪酸が豊富な青魚やナッツ類、ビタミンB群や鉄分が含まれる緑黄色野菜や豆類は、脳のエネルギー代謝を促進して脳の働きを向上させてくれます。ぜひ積極的に、食べるようにしてください。
◆脳によい食材については、コチラの記事でお読みいただけます
ウォーキングやストレッチなど軽めの運動で脳を活性化
ここまで何回もお伝えしているように、ウォーキングやストレッチといった軽めの運動は、脳を活性化させる効果があります。
こういった運動を続ければ、体中の血行がよくなり、必要な栄養と酸素が脳へたっぷりと供給されます。脳の状態が改善されれば、そのぶんパフォーマンスを発揮しやすくなり、その結果として記憶力や集中力が向上するわけです。
脳の活性化という意味でいえば、アスリートのような高強度の運動は必要ありません。あまり負荷の高い運動を続けると、脳も体も疲労してしまい、脳活としてはまったくの逆効果です。
2019年にWHOが発表した「認知症と認知機能予防に関するガイドライン※」では、以下の運動量を推奨しています。(65歳以上の場合)
- 週に合計150分以上の中強度の有酸素運動
- 週に合計75分以上の強度の高い活発な運動
65歳以上の成人は、少なくとも上記のどちらか、もしくは組み合わせて運動を習慣化する必要があるそうです。同ガイドラインには、ほかにも「有酸素運動は10分以上続けておこなう」「筋トレは週に2回以上」といった提言が述べられています。
決してムリする必要はありませんが、ひとつの目安としていちど確認してみることをオススメします。
※参考:Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines
良質な睡眠で脳のリカバリー機能を促進
人間の脳は、睡眠中に記憶の整理をおこないます。重要だと判断した情報だけを記憶して、必要のない情報をリセットするのです。よく眠れた朝は、頭がスッキリとしていませんか。これはリカバリー機能がうまく働いて、脳がしっかりとリフレッシュした状態に戻った証拠です。
こういったリカバリー機能が正常に稼働するには、良質な睡眠が欠かせません。記憶の整理は、主にレム睡眠時におこなわれます。レム睡眠は90分間隔で一晩に4〜5回しか発生しないため、睡眠時間が短いと記憶の整理をする時間が不足する可能性も出てきます。
良質な睡眠を得るには、就寝時間と起床時間をできるだけ固定してください。いつも同じ時間睡眠を確保できれば、体内時計が狂うことなく、ぐっすりと眠れます。
また、深い眠りには、寝室の環境も重要です。いくら時間を確保しても、寒すぎたり暑すぎたりすれば、眠りは浅くなってしまいます。ほかにも、湿度や音、光も、睡眠の質を左右する重要な要素です。
とくに、朝方の日光量管理には、細心の注意が必要です。日光浴はよい習慣ですが、それはあくまでも起床後の話になります。目を覚ますまでは極力外部の光を入れないように、遮光カーテンを設置するのもオススメです。
◆睡眠の重要性については、コチラの記事でお読みいただけます
瞑想でメンタルを強化
個人的に瞑想は、脳に対して非常によい影響を与えてくれると感じています。静かに座り自分の心とじっくりと向き合う過程で、心が本当に落ち着くんです。
日本の座禅やアメリカで大流行したマインドフルネスなど、瞑想に分類される手法は、世界中で500種類以上もあるといわれています。脳活目的なら、正直どの瞑想法を選んでも構いません。こまかい違いはありますが、やるべき内容は基本的に共通していますので。
もし瞑想をする時間が取れないほど忙しい場合は、深呼吸がオススメです。やることは、単純に、ゆっくりと息を吸い込み、ゆっくりと吐き出すだけ。言葉にするとたったそれだけですが、ほんの数回深呼吸を繰り返すだけで、驚くほど気持ちがリラックスしている自分に気づくでしょう。
とはいえ、瞑想の時間を取れないほど気持ちに余裕がない状態は、脳にとって決してよい環境とはいえません。夜寝る前の10分でもいいので、静かに自分と向き合う時間を取るように心がけてください。
◆瞑想の種類については、コチラの記事でお読みいただけます
香り(アロマ)を生活に取り入れる
手軽に脳を活性化させたいなら、ぜひ香りを生活に取り入れてみてください。香りは私たちの心と体に深く作用し、なかでも記憶や感情といった人間の重要な機能によい影響を与えてくれます。
香りを感じた嗅細胞は情報をまず嗅覚野に送り、そこから嗅覚の電気信号が大脳辺縁系や視床下部に伝わります。大脳辺縁系の海馬や扁桃体は記憶や感情を、視床下部は自律神経を司っている非常に重要な器官です。
香りは、そういった重要な器官の働きを整えてくれます。なかでも、アロマが副交感神経を落ち着かせてくれる働きには特筆すべきものがあり、ストレスに悩む人はすぐにでもアロマを試してみてください。
なお、アロマのなかでなにかひとつだけオススメするとしたら、ラベンダーがオススメです。ラベンダーには抗うつ・抗不安作用※があり、軽い不眠や頭痛、胃腸系のトラブルに効果が期待できます。
※参考:アロマと嗅覚、そしてストレス | 生物学科 | 東邦大学
会話を楽しむ
誰かと会話をするという行為は、脳を活性化し、さまざまな社会的スキルをレベルアップしてくれます。
会話というのは、じつは言葉だけで成り立っているわけではありません。有名な心理学上の法則「メラビアンの法則」では、コミュニケーションにおける影響度の割合を、以下のように提唱しています。
- 言語情報7%
- 聴覚情報38%
- 視覚情報55%
会話の際には、話の内容が重要に思われていますが、じつは言葉による影響は7%しかないそうです。それよりも、口調や表情といった「非言語コミュニケーション」が93%も占めています。
普段意識はしていませんが、私たちが会話をするときには、相手の表情や話し方から言葉の裏にある意図を読み取ろうとして脳がフル回転しているのです。
もちろん、新しい情報を知る高揚感や孤独感の減少といった点も、脳の働きによい影響を与えてくれます。普段人と話す機会の少ない人は、会合やイベントなどに出席して、話す機会をどんどん増やしていきましょう。
料理を振る舞う
料理と聞けば、単純に「食べるものをつくる作業」というイメージがあるかもしれません。もちろん、食材を切る・炒める・煮る・洗うなど、作業もたっぷりおこないます。しかし、料理を完成させるまでには、考えなければならないことが山のようにあるのです。
- 献立の決定
- 材料選び
- 買い出しの準備
- 下ごしらえの段取り
- こまやかな火加減の調整
- 味つけの調整
- キレイに見える盛りつけ
- 明日のレシピの選定
よく料理をする人が、「うーん、今日の晩ごはんは、なににしよう……」って悩んでいますよね。頭のなかを、何十個ものレシピがぐるぐると駆け巡っている状態は、まさに脳活そのものです。
鍋でお湯を沸かす間に材料を切り、別な食材をレンジで下ごしらえする。いとも簡単にやっているように見えますが、上記の行程をスムーズに進めるために、料理中の脳はフル回転しています。
もし、今までほとんど料理をしたことがないなら、週に2〜3回でいいので、ぜひ料理にチャレンジしてみてください。
◆料理の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
楽器を習う
もし、少しでも楽器演奏に興味があるなら、脳活として楽器演奏に取り組んでみてはいかがでしょうか。ピアノ・ギター、楽器の種類を問わず、楽器演奏は脳のさまざまな部位を同時に鍛えてくれます。
- 楽譜を読む→後頭葉「視覚野」、側頭葉「ウェルニッケ野」
- 楽譜を覚える→前頭葉「前頭前野」
- 鍵盤やフレットの位置関係を確認→頭頂葉「頭頂連合野」
- 楽器を弾く→前頭葉「運動野」
上記はあくまでも一例ですが、鍵盤やフレットを押さえるだけでも、これだけの部位が連動して、はじめて成立するわけです。もちろん、いきなり独学で楽器を演奏するのは、少々ハードルが高いと思われます。なにもかもひとりで覚えようとすると、おそらくうまくいかなくて、すぐに挫折してしまう可能性が高いです。
幸い、今は楽器演奏を教えてくれるスクールが数多くあるので、まずはしっかりと基本を教えてもらいましょう。
◆楽器の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
語学を学ぶ
語学は、私たちの言語機能・記憶力・集中力・感情コントロールなど、さまざまな認知機能を鍛えてくれます。ただ、外国語は小さい頃に学ばないと、流暢に話せるようにならないと思っている人が非常に多いです。
たしかに、ネイティブレベルを目指すなら、幼少期から多言語に触れたほうが圧倒的に有利でしょう。しかし、脳活が目的なら年齢はまったく関係ないし、何歳からはじめてもコミュニケーションに不自由しないレベルには問題なく到達できます。
語学学習の効能については、近年さまざまな研究により、ポジティブな結果が明らかにされています。たとえば、ケンブリッジ大学出版のサイト※には、語学学習が脳や神経系統のつながり強化に役立つと書かれていました。
こうした働きは、幼少期に外国語を学んだいわゆる「バイリンガル」だけに現れるわけではありません。高齢になってから学習をはじめた人にも、同じように脳神経ネットワークの発達が見られるそうです。
英語、中国語、スペイン語、言語はどれでも構いません。脳活を兼ねて、興味のある言語の勉強に取り組んでみてはいかがでしょうか。
※参考:How learning a new language changes your brain | Cambridge English.
あえて計算機を使わない
「最近、計算力が衰えてきたな」と感じたら、計算機を使わずに暗算に挑戦してみるのもオススメです。計算機は決して間違わず計算も速いのですが、その代償として、自分の計算力をまったく使わなくなってしまいます。
たとえば、15×12といったふた桁同士の掛け算式を、筆算を使わずに計算してみてください。「えっ、9×9までの掛け算なら暗算できるけど、ふた桁になるとちょっと……」と思った人も多いのではないでしょうか。
この計算は、以下のように1の位を0に振り分けると、比較的簡単に計算できます。
15 × 12 =(10+5)× 12
= 10 × 12 + 5 × 12
= 120 + 60
= 180
こういった自分の脳を使った計算は、たしかに面倒です。しかし、定期的に暗算する機会をもてば、計算力の衰えは最小限に食い止められます。
認知症の診断テストには、計算力も診断項目に含まれています。これは逆をいえば、計算力が落ちなければ認知症になりにくいということ。小学生向けのドリルで構わないので、自分で計算する機会をぜひ定期的につくってください。
脳活習慣を継続させる4つのコツ

正直なところ、脳活にはなんの強制力もありません。忙しくなり、内容にも飽きてくれば、多くの人はおそらくすぐにやめてしまうでしょう。それくらい、脳活の継続はむずかしいのです。
そこで最後に、脳活習慣を継続させるコツを4点紹介しておきます。せっかくはじめた脳活を継続していくためにも、ぜひ参考にしてください。
1.継続しやすい環境を整える
焦って脳活トレーニングへ飛びつく前に、脳活を快適におこなうための環境を整えてください。快適に楽しく過ごせる環境があれば、途中で挫折するリスクを最小限に減らせます。
まずは、脳活をおこなう場所を決めてしまいましょう。静かで集中できる場所が理想的ですが、自分がリラックスできる空間であれば、どのような場所でも構いません。自室でもカフェでも、自分にとってその場所が快適なら、それでいいのです。
次に、脳活をおこなう時間も決めておきたいですね。人によっては、朝の散歩がやりやすいだろうし、夜静かな時間帯に自室でじっくりと取り組みたい人もいるでしょう。時間帯も場所と同様に、本人が快適ならいつでも構いません。
ただし、毎回できるだけ同じ時間帯に設定したほうが、「そろそろ時間だから脳活の準備をしよう……」と、脳活をルーティン化しやすいです。
なお将棋や麻雀、ゴルフのようにメンバーを集める必要のある脳活は、継続という面でやや難があります。パズルや料理のようにひとりでできる脳活にも取り組むか、アプリを活用してひとりでも楽しめるように、いろいろと工夫をしてみてください。
2.好きなことや興味を持てることから取り組む
脳活を習慣にするためには、自分が好きなことや興味をもてることから取り組むと、うまくいきやすいです。
そういう意味でいうと、前述のとおり、趣味やゲームを脳活の入り口にするのは非常にいいアイデアだと思います。誰だって、興味のあることのほうが楽しんで取り組めますからね。
もちろん、内容はなんでもOKです。クイズやパズルゲーム、音楽やアートなど、本当に興味をもてるものにどんどんチャレンジしてください。
とはいえ、いくつか押さえておくべきポイントもあります。
- 頭脳系と作業系をバランスよく選ぶ
- 複数の脳活を並行しておこなう
- ときどき新しいことに取り組む
上記はすべて、脳活に飽きないための工夫です。いくら楽しくても、同じことばかりやっていたら、脳活の効果が薄れてしまいます。効果が感じられなければ、やはりすぐに飽きてしまうでしょう。
頭と体をバランスよく使い、いろいろな脳活で飽きを防止。さらに定期的に新しい刺激を与えれば、脳活を継続できる確率は大きくアップするはずです。
3.成果を見える化してモチベーションを維持
脳活習慣を続けるうえで、成果を見える化し、モチベーションを維持するのは非常に重要です。脳の活性化が目的なので、なにかしらの成果が感じられなければ、途中で嫌になってしまうでしょう。その点、少しでも自分の進歩が見えてくれば、継続する意欲が高まります。
まずは、脳活の成果を記録するのがスタートです。とはいえ、エクセルなど、手入力で記録するのは案外面倒なもの。もしやりたい脳活トレーニングのアプリがあるなら、ぜひアプリを活用してください。
ほとんどの脳活アプリには、成績や進捗を自動で記録してくれる機能が搭載されています。得意な面・苦手な面をグラフでわかりやすく表示してくれるので、次にやるべき内容がすぐにわかるのも嬉しいポイントです。
もちろん、いくら成果を目で確認できても、事前に脳活の目的を決めておかないと、あまり意味はありません。ゴールが決まっているから、これからなにをすればいいかがわかるんです。脳活における目標設定については、以下の記事でも解説しています。ぜひ読んでみてください。
4.他人へのライバル心をうまく利用する
前述のモチベーションと大きく関係する話ですが、他人へのライバル心をうまく利用できると脳活習慣は維持しやすいです。ゲームでも友達とスコアや順位を競い合えば、「負けないぞ!」とやる気が出てきますよね。脳活も、これと同じです。
適度なライバル心は、脳活を継続する原動力となり、目標達成へのモチベーションを高めてくれます。
ただし、過剰なライバル心は、ネガティブな感情を呼び起こしやすいので注意が必要です。負けたくないあまり、「あいつ失敗すればいいのに……」などと考えるようになったら、脳活という本来の目的から大きく外れてしまいます。
おそらく、人間関係にも悪い影響を与えてしまうでしょう。あくまでも、よい意味でのライバル関係に留めておくよう、心がけてくださいね。
まとめ
脳活(脳トレ)を習慣にできれば、必ずなにかしらのよい成果が感じられるはずです。ところが、脳活を継続できずに、途中でやめてしまう人も決して少なくありません。
今回の記事では、脳活のメリット、脳活の具体的な方法、習慣化のコツをしっかりとお伝えました。もちろん、すべてをいっぺんにおこなう必要はありません。ムリのない範囲で、できることから取り組んでみてください。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読