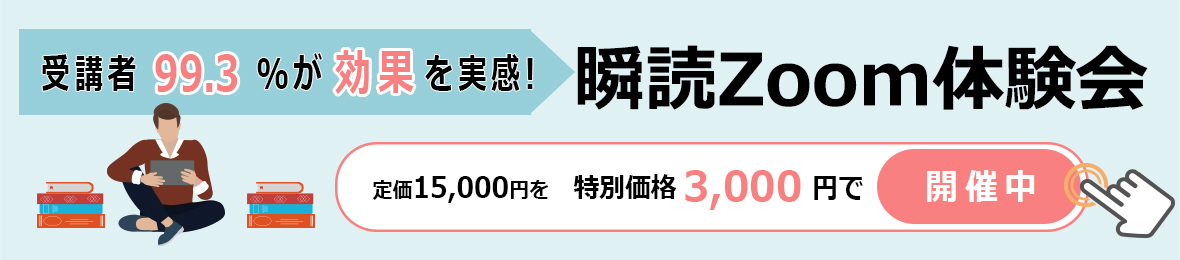記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
近頃、認知症の予防に効果があるということで、脳トレが注目されています。右脳速読を指導している私のところにも、「速読には脳トレ効果がありますか?」といった問い合わせがよくきます。
今まで脳トレをしたことがない人にすれば、脳トレに興味はあっても、本当に効果があるのか不安に感じるのは当然でしょう。
今回の記事では、脳トレで認知症や理解力は改善されるのか、その効果をしっかりと検証していきます。また、オススメの脳トレも12個紹介しますので、もし気になる脳トレがあれば、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。
目次
脳トレの効果を徹底検証

脳トレが認知症を改善してくれるという意見もあれば、まったく効果がないという、真逆の話もよく耳にします。実際のところ脳トレにはどういった効果が期待できるのか、オススメの脳トレを紹介する前に、しっかりと確認しておきましょう。
脳トレで本当に脳機能は改善するのか?
まず結論からお話しすると、現時点では脳トレと機能改善の関係性について、明確な答えは出ていません。脳トレは認知症予防に有効だというデータがある反面、とくに効果はないというデータも発表されており、簡単には判断を下せない状態です。
ただし、あくまでも個人的な観点にはなりますが、私は「脳トレに脳機能を向上させる働きがある」という説が有力だと考えています。なぜならば、効果ありデータのサンプル人数が、効果なしデータのサンプル人数よりも圧倒的に多いからです。
エクセター大学とキングスカレッジ・ロンドンが2019年に発表した調査結果※によると、定期的にクロスワードパズルやナンプレに取り組んでいる人は、「注意力」「推理力」「記憶力」に関する評価テストの成績が大幅によかったそうです。
文法的に推測する力は10歳、短期記憶については8歳ほど、実年齢よりも若い人と同等の水準をキープしていました。
注目すべきは、19,000人というサンプル人数の多さです。後述する効果なしデータのサンプル人数は、およそ1,000人でした。サンプル数が絶対とはいいませんが、研究対象が19倍も多い調査のほうが、より精度は高いと考えるのが自然でしょう。
脳トレは意味がないという意見の正体とは?
「脳トレは効果がない」とする意見の背景には、特定の研究結果があることも事実です。たとえば、カナダ・ウェスタン大学の研究では、熱心に脳トレをおこなっている人たちでも「注意力・推論・記憶・計画立案」といった認知機能が大きく向上する兆しは見られなかったと報告されています。
こうした結果をもとに、「脳トレは意味がない」と結論づける声が出るのは当然かもしれません。ただし、これはあくまで「ある条件下での一例」にすぎません。すべての脳トレを否定するには根拠として不十分です。
前述の通り、効果があったというデータも数多く存在します。大切なのは、正しいやり方と継続です。ひとつの研究結果だけをうのみにせず、柔軟に考える姿勢が求められるのではないでしょうか。
※参考:APA PsycNET
効果のカギは「内容」と「継続」にあり
脳トレの効果を引き出すには、「どのような内容に取り組むか」と「どれだけ継続できるか」が重要なポイントになってきます。脳は筋肉と同じで、一度の刺激では変化が起きません。反復によって少しずつ神経回路が強化されていきます。
たとえば、クロスワードパズルや計算トレーニングといった定番トレーニングも、数回でやめてしまっては効果は限定的です。1回あたりの時間が短くても、とにかく継続していくことを目指してください。
最初は週2〜3回、1回10分からでもOKです。継続しやすい頻度で、少しずつじっくりとレベルや時間を伸ばしていくのがポイントになります。また、同じ内容を繰り返すだけでは脳が慣れてしまうため、バリエーションを持たせることも大切です。
いずれにせよ、脳トレの成果は、内容の質と継続性によって大きく左右されます。無理なく続けられるスタイルを見つけて、脳トレを習慣にしていきましょう。
認知症対策に脳トレは有効なのか?
脳トレは認知症予防の手段として、一定の効果が期待できると考えられます。その理由は、脳トレによる刺激が脳の神経回路の活性化を促してくれるからです。
たとえば、アメリカのコロンビア大学が実施した研究では、軽度認知障害のある高齢者にクロスワードパズルを継続しておこなってもらったところ、記憶力や言語能力の低下を防ぐ明らかな改善が見られたと報告されています。
また、ブロンクスの追跡調査でも、クロスワードを習慣的におこなっていた人は、記憶力の衰えが平均2.5年遅かったという結果が出ています。もちろん、脳トレには認知症を治療してくれる役割はありません。あくまでも、認知症予防と軽度認知症の機能維持を目的におこなうべきものです。
脳トレは万能ではありませんが、少なくともなにもしないよりは脳によい影響を与えるのは確かです。脳トレへの取り組みは、認知症対策の選択肢のひとつとして十分価値があるといえるのではないでしょうか。
※1:Have you done your crossword puzzle today? – Harvard Health
脳トレで得られるそのほかのメリット
脳トレには、認知症予防以外にもさまざまなメリットがあります。
- ストレスの軽減
- 自己肯定感の向上
- 学習意欲の向上
- 人間関係の活性化
とくに注目したいのは、ストレス軽減や自己肯定感の向上といった心のケア効果です。パズルやゲームに集中している時間は、余計な不安や悩みから意識を切り離せるリフレッシュタイムになってくれます。
また、学習意欲の向上も、脳トレの魅力のひとつです。できなかった問題が解けるようになると、自分に対する評価が自然と高まり、学習意欲や前向きな気持ちにつながります。
さらに、将棋やRPGなど人と一緒に楽しむタイプの脳トレでは、会話や交流のきっかけが生まれ、人間関係の活性化も期待できます。このように脳トレは、脳を鍛えるだけでなく、心にもよい影響を与えてくれる有益な習慣なのです。
◆脳トレの効果(メリット)については、コチラの記事でもお読みいただけます
認知症予防が期待できるオススメの脳トレ

ひとことで脳トレといっても、本当にたくさんの種類があり、どれを選べばいいのか迷ってしまうかもしれません。認知症予防のために脳トレをおこなう人も多いので、今回は主な認知機能別にオススメの脳トレを紹介していきます。
もちろん、脳トレによって、特定の認知機能だけに効果が現れるわけではありません。どういった脳トレでも脳全体になんらかのよい影響をもたらしてくれますので、あまりむずかしく考えず、とりあえず気になるものから取り組んでみてください。
記憶力アップ「クロスワードパズル」
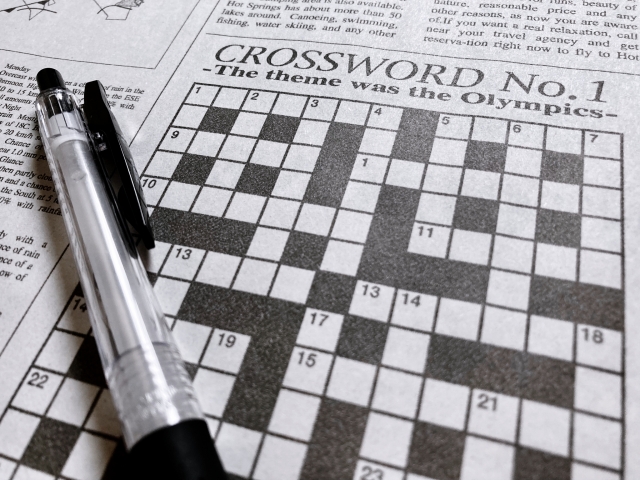
脳トレと聞けば、多くの人がクロスワードパズルを思い浮かべるのではないでしょうか。クロスワードパズルは、番号が書かれた空白のマスへ、ヒントをもとに文字を埋めていきます。
縦横が交差する箇所には同じ文字が入るので、ひとつのヒントだけでなく、ほかのヒントも考慮しながら答えを探していかなければなりません。だから、クロスワードパズルはむずかしいんですね。
また、ヒントから言葉を導くので、当然その言葉を知っていることが大前提となります。しかし、過去に聞いたことのある言葉であっても、すぐに頭に思い浮かぶとは限りません。
でも、大丈夫です。「あれ、なんだったっけなあ……」と記憶の引き出しから言葉を引き出そうとする過程が、私たちの記憶力を大きく刺激してくれます。
もちろん、なかにはまったく知らない言葉も出てくるでしょう。そういう言葉をチェックしていくことで、記憶力だけでなく、新しい語彙が増えていくのもクロスワードパズルの魅力のひとつです。
幸いクロスワードパズルを入手するのは簡単です。書店にいけば、数多くの専門誌が販売されています。どれか1冊手に取って、まずは1問解いてみてください。
◆クロスワードパズルについては、コチラの記事でもお読みいただけます
記憶力アップ「間違い探し・各種クイズ」
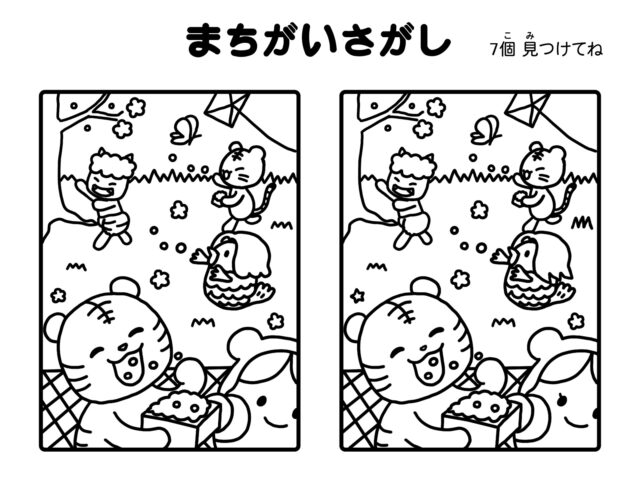 間違い探しも、非常にポピュラーな脳トレです。ほぼ同じように描かれた2枚の絵を見比べながら、間違いを探していきます。間違いの数は通常3〜5個ですが、多ければ10個以上間違いを探す場合もあります。
間違い探しも、非常にポピュラーな脳トレです。ほぼ同じように描かれた2枚の絵を見比べながら、間違いを探していきます。間違いの数は通常3〜5個ですが、多ければ10個以上間違いを探す場合もあります。
最初の1〜2個は比較的簡単に探せても、残りの数個がなかなか見つからずに、思わず熱中してしまうかも。目の錯覚を利用して巧妙に描かれているものも多く、脳への刺激という意味では、非常に効果が期待できる脳トレだと思います。
また間違い探し以外にも、漢字を当てるクイズや四択クイズなど、脳に効果のありそうなクイズはたくさんあります。ネットや雑誌などをリサーチして、ぜひ自分に合ったクイズを探してみてください。
言語能力アップ「ジャーナリング」

ジャーナリングとは、頭のなかにある考えや感情をストレートに書き出す行為のことです。書き出すためには、ぼんやりしている思考をしっかりと言語化しなければなりません。この「思考の言語化」が、あなたの言語能力を大幅に高めてくれます。
よく日記と混同されがちですが、日記はその日に起きたできごとを記録する意味合いが強いです。あとから読み返すことを意識してか、キレイな文章でまとめようとする人が多いので、本当の気持ちから外れてしまうことも少なくありません。
ジャーナリングをする際には、そういった意識は邪魔になります。今考えていること、今感じていることをそのまま素直に書き出してください。
とはいえ、いきなり思考を言語化といわれても、最初はなかなか手が動かないでしょう。慣れるまでは、「新規プロジェクトで準備しておくこと」「今日嬉しかったこと」など、なにかテーマを決めて書き出してみるのがオススメです。
◆ジャーナリングについては、コチラの記事でもお読みいただけます
言語能力アップ「速読トレーニング」
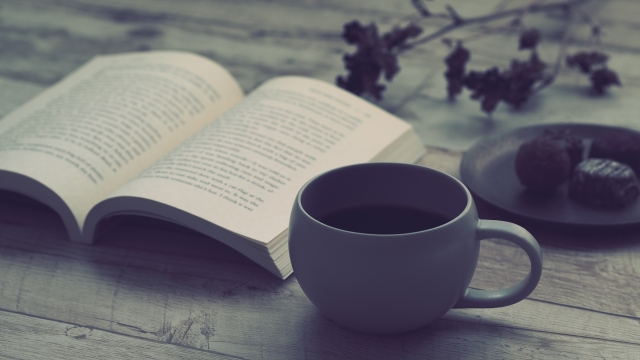
脳への刺激を考えると、私が指導する右脳速読は本当にオススメです。通常の速読は、目を速く動かして速読するので、どちらかといえば運動に近いといえます。
ところが右脳速読の場合、目を過度に動かしたりはしません。その代わりに、イメージ化やひらめきが得意な右脳を使って、文章を映像として記憶していきます。なので右脳速読をすると、普段あまり使われない右脳が、これでもかというくらい刺激を受けるんですね。
右脳速読の受講生のなかには、1分間に2万文字のペースで本を読める人がたくさんいます。2万文字といえば、300ページのビジネス書なら5分程度で読めてしまうスピードです。
大量の知識を吸収しながら脳トレにもなる、右脳速読は本当にオススメですよ。
◆右脳速読の詳細についてはコチラの記事でお読みいただけます
計算能力アップ「珠算式暗算」

珠算式暗算は、そろばんを頭のなかでイメージしながら計算する暗算法です。そろばんの珠を頭のなかで動かして計算することで、ただ暗算をするよりも、計算スピードが格段に速くなります。
高齢になると、どうしても計算力が衰えてくるものです。しかも近年では、電子マネーやセルフレジが普及して、自分の頭で計算する機会が激減しています。もし計算力の衰えを少しでも感じているなら、こういった暗記法のトレーニングは非常にオススメです。
もちろん、珠算式暗記法をおこなうには、そろばんを使った計算ができないと話になりません。珠算式暗算では実際にそろばんを使いませんが、空中で指を弾く「エアそろばん」で計算していきます。
そろばんができない人は、まず教室で珠算の基礎を習うことから始めましょう。そろばんの基本的なしくみを理解し、珠算式暗記トレーニングを続ければ、計算力の衰えは最小限で抑えられるはずです。
計算能力アップ「ナンプレ」
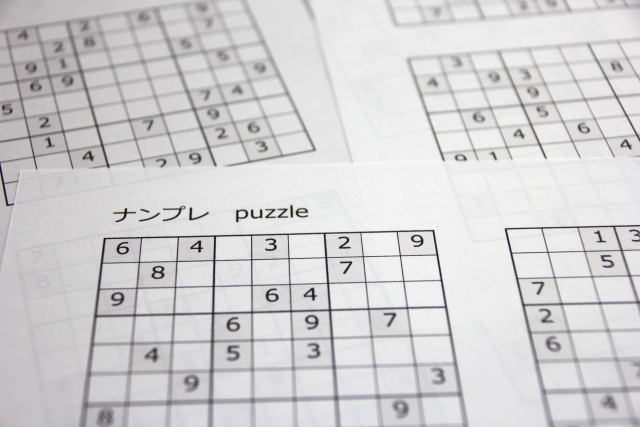
ナンプレ(数独)は、1から9までの数字を使ってマスを埋めていくパズルです。ナンプレ自体に複雑な計算は含まれませんが、ルール通りに空いているマスを埋めていく必要があるので、非常に頭を使います。
9つのマスに、1から9の数字を入れていくだけなら、それほどむずかしくありません。しかしナンプレの場合、以下のようなルールがあり、すべてのルールを満たすように数字を配置するのは、なかなか大変です。
- どのタテ列にも1〜9の数字が1個ずつ入る。
- どのヨコ列にも1〜9の数字が1個ずつ入る。
- どの3×3ブロックにも1〜9の数字が1個ずつ入る。
数字のパターンやほかのマスとの位置関係を論理的に考えながら埋めていくため、計算力だけでなく集中力や直感力も磨かれます。
ナンプレは世界中で人気のゲームであり、日本でも数多くの雑誌が発行されています。さまざまなアプリもリリースされていますので、気軽にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
判断力アップ「将棋・囲碁」

将棋や囲碁といったゲームは、厳密にいえば脳トレではないかもしれません。しかし、脳へ与える刺激を考えると、ほかの脳トレよりも高い効果が期待できます。
さきほど紹介したパズルやクイズと違い、将棋や囲碁には対戦相手がいます。そうなると、相手に勝つには、自分の思考だけでは足りません。
「相手が次にどのような手を打ってくるか」を読み、ゲームの進行状況に応じて臨機応変に作戦を立てられなければ、おそらくすぐに負けてしまうでしょう。
とくに将棋は、コマによって動かせる方向と役割が異なります。「限られた盤上でどのように手駒を動かすか」そういうこまかい判断の積み重ねが、脳(とくに前頭葉)の働きを活発にしてくれるのです。そういう意味では、似たルールのチェスも非常にオススメできます。
判断力アップ「ロールプレイングゲーム(RPG)」

ゲーム好きなら、判断力を磨いてくれるロールプレイングゲーム(RPG)はどうでしょうか。RPGは、架空の世界(主に未来や異世界)で主人公を操作して、物語を進めていくゲームの総称です。
どのゲームでも、はじめのうちは主人公のステータスが低く、そのままでは物語が進行しません。そのため、怪物を倒す・道具を購入する・イベントをこなすなど、さまざまな経験を重ねて、少しずつレベルを上げていくわけです。
しかし、RPGには「次は◯◯をする」という明確なルールがないので、自分でなにをすればいいのか手探りで探っていく必要があります。(攻略本はありますけどね)
たとえば、どこにいくか・誰を仲間にするか・どんなアイテムを使うかなど、RPGは状況に応じて最適な判断をしなければならない場面の連続です。レベルが上がれば、クリアする課題の難易度も高くなり、より高度かつ素早い判断が求められます。
また、選択した行動によってストーリーの展開が大きく変わってくるため、先を見通して判断する「予測力」も育まれます。楽しみながらできるRPGは、判断力を鍛えるだけでなく、柔軟で創造的な発想力も養える理想的なトレーニングといえるでしょう。
遂行力アップ「絵画・ぬり絵」

「パズルもいいけど、私は手を動かすほうがいいなあ」という人は、絵を描いてみるのはどうでしょうか。なんといっても、絵を描く作業は、普段使わない右脳をたくさん使います。
モチーフを正確に捉える「空間把握能力」、見たままではなく自分の感性を加えて構成を考える「ひらめき」など、絵画は右脳をフル稼働する作業です。
また最近では、大人の塗り絵もかなり一般化してきました。もしかすると、塗り絵は子どもの遊びというイメージがあるかもしれません。しかし、大人向けに絵柄はこまかく描写されていて、色選びにもセンスが問われます。
なお、人間の手先には敏感な神経が何百本も集まっており、「第二の脳」などといわれることもあるそうです。絵画や塗り絵には、そういった鋭敏な手先を使い、脳を刺激する働きがあります。
今なら100円ショップで画材を安く購入できますので、出費に関してもそれほど気にする必要はないでしょう。ぜひ、気軽に挑戦してみてください。
遂行力アップ「料理」

手を動かす脳トレなら、料理もいいですね。できあがりを想定しながらレシピを考えていくので、右脳がばっちり鍛えられます。買い物をしたり調理をしたりと、体も動かすので、バランスよく左右の脳が刺激されるのも嬉しいところです。
また自炊をすれば、味つけや調理法を自由に選択できます。塩分を控え、青魚などの認知症によいとされる食材を積極的に摂れば、健康状態も大きく改善するでしょう。
友達を招いての食事会なども、じつに楽しそうです。美味しいものを食べて、家族や友人と楽しくおしゃべりをする。そう考えると、料理は最強の脳トレかもしれませんね。
身体能力と脳機能の連動「指回し運動」

ウォーキングやスポーツは、血流を改善し、脳の働きを高めてくれます。しかし、高齢になり足腰に不安のある方の場合、こういった運動を定期的におこなうのは、大きな負担となる可能性が高いです。
その点、指回し運動なら誰でも気軽に取り組めます。具体的には、指先をくっつけたままぐるぐる回す・指を一本ずつ曲げ伸ばしする・グーとパーを交互に繰り返すといった方法が考えられます。余裕のある人は、2本指に輪ゴムをかけて指の開閉をおこなう方法もオススメです。
手や指には、第二の心臓とよばれるくらい、さまざまな神経が通っています。手指を動かして運動系や感覚系の神経を刺激してあげると、全身の血流が改善され、脳の認知機能も向上します。
無理をして筋肉を傷めない程度に、どんどん指先を動かして、体と脳の両方を鍛えていきましょう。
◆指回し運動については、コチラの記事でもお読みいただけます
身体能力と脳機能の連動「左右バラバラトレーニング」

指回し運動に慣れてきたら、今度は全身を使った「左右バラバラトレーニング」に挑戦してみましょう。
左右バラバラトレーニングは、左右異なる動きを同時におこない、脳と体の連動性を高めていきます。試しに、右手で円を描きながら左手で三角形を描くといった動きをしてみてください。おそらく、想像以上にギクシャクした動きになってしまったはずです。
私たちは、通常左右同じような動きしかしません。だから、いきなり左右で違う動きをしようとしても、うまく体に指令を出せないのです。しかし、しばらく左右バラバラトレーニングを続けていると、徐々に動きがスムーズになってくるでしょう。
このように、普段やらない動きをあえてすることで、運動機能や認知機能は大きくレベルアップしていきます。運動する時間がなかなか取れない人は、先ほどの指回し運動を左右違う動きでやってみるのもオススメです。
また応用編として、ドラムやギターといった楽器演奏に挑戦してみるのもいいかもしれません。楽器演奏をする際には、自然と左右異なる動きをすることになりますからね。
左右の動きが異なっていればどういった運動でも構わないので、いろいろな動きを試してみてください。
◆左右非対称運動については、コチラの記事でもお読みいただけます
脳トレの効果を引き出す4つの工夫

せっかく脳トレに取り組むなら、できるだけ効果的におこないたいものです。そこで、最後に脳トレの効果を引き出す工夫を4つご紹介していきます。
年齢やレベルに合わせてトレーニングを選ぶ
脳トレの効果を高めるには、自分の年齢や認知機能のレベルに合った内容を選ぶことが大切です。というのも、脳への刺激は「ちょっとむずかしい」と感じるくらいがちょうどよく、負荷が合わないと飽きたり続かなかったりするからです。
たとえば子どもには「間違い探し」や「伝言ゲーム」など、遊び感覚で集中力や記憶力を養うタイプの脳トレが向いています。自主的に脳トレに取り組む大人と違い、飽きるとすぐにやめてしまいますので。
働き盛りの世代には、「速読トレーニング」や「ジャーナリング」のように、実生活に役立つ実用的な脳トレがオススメです。
一方、高齢者には、「クロスワードパズル」や「ナンプレ」など、記憶力や判断力を刺激する脳トレが効果的です。手先の感覚を鈍らせないために、「ぬり絵」や「料理」といった指先を使う脳トレもいいですね。
もちろん、年齢にこだわりすぎる必要はありません。自分にとってちょうどいい負荷だと感じるなら、どういった種類の脳トレを選んでもOKです。
習慣化のコツは「楽しさ」と「簡単さ」にあり
習慣化のカギは、「楽しさ」と「簡単さ」が握っています。どれだけ頑張って取り組んでもつまらなかったり、むずかしすぎたりすれば、途中で嫌になってしまいます。
最初のうちはモチベーションも高いので問題ありませんが、時間の経過とともに義務感で脳トレをやっている状態になったら危険です。なかでも、定番脳トレである漢字クイズや計算問題は、どうしても勉強感がつきまといます。
飽きてしまうのも早いので、間違い探しやオンライン対戦ゲームなど、遊びの延長でできる脳トレをうまく組み込むといった飽き防止の工夫が必要になってくるでしょう。
また、難易度も重要なポイントです。簡単すぎればすぐに飽きてしまうし、むずかしすぎれば嫌になってしまいます。前述の通り、「今の自分には少しだけむずかしいというレベル」が、脳トレの効果を最大限に発揮してくれる難易度です。
背伸びをして難易度の高い問題をやるよりも、少し頑張ったらクリアできる問題を数多くこなしてください。
アプリで脳トレに対するハードルを下げる
ひと昔前までは、紙とペンを使う脳トレが主流でした。ところが、今やAIやアプリを活用するのがごく一般的です。アプリを使えば、いろいろなところから脳トレの題材を集めてくる必要がありません。場所や時間を選ばず、スマホひとつで手軽に脳を刺激できます。
たとえば「NeuroNation」や「Peak」のような総合脳トレアプリには、記憶力や判断力など、鍛えたい分野に合わせた多彩なゲームが用意されています。しかも近年はAIが搭載されており、自分の得意・不得意に応じてメニューを調整してくれるのも魅力のひとつです。
どの脳トレを選ぶか迷う時間も減り、効率よく続けられます。また、1回数分でできるゲームが多いので、スキマ時間の活用にもぴったりです。
同じ脳トレでも、アプリならダウンロードするだけですぐに取りかかれます。脳トレの準備に面倒くささを感じている人ほど、ぜひアプリを試してみてください。
◆オススメの脳トレアプリについては、コチラの記事でもお読みいただけます
脳トレだけに頼らず生活習慣も整える
脳トレの効果を最大限に引き出すには、生活習慣そのものを見直すことも欠かせません。脳の働きは、睡眠・食事・運動といった日々の習慣に大きく左右されるからです。
たとえば、スタンフォード大学の研究※1によると、6時間未満の睡眠が続くと集中力や判断力が著しく低下することが明らかになっています。脳は睡眠中に記憶の整理と定着をおこなうため、睡眠時間が短くなると脳を十分にリフレッシュできないのです。
また、食品摂取の多様性が高い人ほど、豊富な栄養素を摂取しており、それが認知機能の低下を抑制する要因になっているという研究データ※2があります。私たちはどうしても炭水化物中心の食事になりがちです。野菜や果物、魚類を中心に、バランスのよい食事を心がけましょう。
運動については、ウォーキングやストレッチなど軽目の運動を習慣化できれば、血流がよくなり、脳への栄養と酸素供給がスムーズになります。WHOのガイドライン※3でも、認知機能低下予防に対して、身体的活動の介入を推奨しています。
こうした土台が整ってはじめて、脳トレ本来の効果を発揮できるのです。まずは日々の過ごし方を見直しながら、脳を育てる環境づくりを意識してみましょう。
※1:Research Update on Sleep – Stanford Center on Longevity
◆生活習慣の改善については、コチラの記事でもお読みいただけます
まとめ
本文中でお話ししたとおり、脳トレが認知症に与える影響については、まだ最終的な結論が出ていません。でも、実際に認知機能が改善されたというデータがある以上、私たちはもっと気軽に脳トレに取り組んでもいいのではないでしょうか。
なによりも、脳トレは楽しいです。最悪自分に合わないと思っても、別な脳トレはいくらでもあります。「楽しそうだからやってみようかな」このくらいの感覚で、今回紹介した脳トレにぜひ挑戦してみてください。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読