
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
仕事や家事に忙しく、最近どうも頭がうまく働いていないと感じている人も多いのではないでしょうか。
そういうときは、ぜひ生活習慣を見直してみましょう。食生活や睡眠、運動など、生活習慣を少し変えるだけで、驚くほど頭が冴える自分に気づくはずです。
当記事では、まず食生活にスポット当てて、改善のポイントを解説します。そのあとで、生活習慣全般における改善ポイントをわかりやすく紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
目次
頭が冴える食生活とは

オススメの食材や水分補給といった、頭が冴える食生活に関するポイントを5つご紹介します。
脳によいオススメの食材
脳によいといわれるブレインフードは、数多くあります。今回は、ナショナル大学が紹介している勉強に最適なブレインフード※のなかから、3点ピックアップしてご紹介します。
- ベリー類
- ダークチョコレート(カカオ70%以上)
- 卵
まず、ベリー類についてです。ブルーベリーやストロベリーなどのベリー類には、抗酸化物質が豊富に含まれています。これらの抗酸化物質は、脳細胞を酸化ストレスから守り、記憶力や学習能力を向上させてくれます。
次に、ダークチョコレートです。ダークチョコレートにはフラボノイドという抗酸化物質が含まれており、脳の血流や炎症を抑えてくれます。また、カフェインも少量含まれているので、適量を食べれば集中力を高めてくれるでしょう。
卵も脳によい食材のひとつです。卵にはビタミンB類やコリンという栄養素がたっぷりと含まれています。なかでもコリンは、脳内の情報伝達と関係の深いアセチルコリンの原料としての役割があり、感情や記憶の調整をおこなってくれます。
上記はあくまでも参考例なので、そのほか気になるブレインフードがあれば、いろいろと試してみてください。
※参考: Best Brain Foods for Studying | National University
◆ブレインフードについては、コチラの記事でもお読みいただけます
水分補給の重要性
私たちの体の約60%は、水分でできています。体内に取り込んだ水分は、血液に代表される体液となって、身体中に運ばれます。体液には、必要な栄養と酸素を供給し、逆に不必要な老廃物を体外に排出する重要な働きがあるのです。
だから、水分量が極端に減ってしまうと、体の機能が正常に働かなくなってしまいます。水分を20%失えば命を失うほど、水分は体にとって必須成分なのです。厚生労働省によると、1日に必要な水分量※は、約2.5Lとなっています。
もちろん、2.5Lの水をゴクゴクと飲むのは、かなり大変でしょう。でも、大丈夫です。2.5Lのなかには、食事からの水分も含まれているので、飲水としては1.2L程度で賄えます。もちろん、30℃を超える真夏には、もっと多く水分を補給する必要があります。
労働環境や運動量などによっても、必要な水分量は変わってくるので、その点は臨機応変に対応してください。いずれにせよ、喉が渇いたと感じてからでは、水分補給が遅すぎます。喉が渇いていなくても、定期的な水分補給を心がけましょう。
※参考: 「健康のため水を飲もう」推進委員会 後援 : 厚生労働省
◆水分補給の重要性については、コチラの記事でもお読みいただけます
朝食の効果
しっかりと頭が冴えた状態で1日を迎えるためにも、朝食はしっかりと食べることをオススメします。胃腸を休ませるという意味で朝食を食べない人もいますが、朝になにも食べないのは、やはりエネルギー不足によるパフォーマンスの低下を招きやすいです。
もちろん個人差はあるし、お腹が空いていないのに無理に食べる必要はありません。ただ、シリアルや卵、バナナ1本でもいいから、なにかしらお腹に入れておく方が、午前中のパフォーマンスは間違いなくアップします。
令和元年国民健康・栄養調査報告※によると、20〜49歳の世代が28%前後と、突出して朝食の欠食率が高いです。仕事や家事にバリバリ活動している世代の朝食欠食率が高いのは、大きな懸念材料といえます。
また、15〜19歳になると、7〜14歳世代の5.2%からいきなり19.2%に上昇します。これは、義務教育が終わり、ある程度子どもの自主性が尊重されるようになったことと、大きく関係しているでしょう。
しかし、15〜19歳といえば、まだまだ体も心も成長を続けている年代です。学業や運動でしっかりと結果を出していくためにも、朝食をしっかり食べるようにしたいですね。
※参考: 令和元年国民健康・栄養調査報告 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果
◆朝食の重要性については、コチラの記事でもお読みいただけます
サプリメントで効率的に栄養補給
サプリメントは、食事だけでは補えない栄養素を、効率的に摂取するのに役立ちます。忙しくて丼ものやお惣菜が続けば、どうしても栄養が偏ってしまうもの。
本来はきちんとバランスのよい食事を心がけるべきですが、サプリメントで気軽に栄養補給できれば、食生活の乱れは最低限に抑えられるでしょう。
ドラックストアにいけば、ビタミンやミネラル、オメガ3脂肪酸といった栄養素を含んだサプリメントが大量に販売されています。魅力的な宣伝文を見ると、サプリメントを飲めばメキメキと健康になるのではないかと錯覚してしまいそうです。
しかし、いくら便利だからといって、闇雲にサプリメントを摂取するのはオススメできません。とくにさまざまなビタミンが配合されているマルチビタミンは、特定のビタミンの過剰摂取を引き起こす危険性があります。
あくまでもサプリメントは、不規則な食事の補助的役割であることを、忘れないようにしてください。
カフェインと集中力の関係
カフェインは、コーヒーやお茶、エナジードリンクなどに含まれる成分で、脳を活性化させる効果が有名です。しかし過剰摂取により、心拍数の増加・イライラ・不安・下痢・吐き気といった健康被害をもたらす危険性があります。
普段眠りの浅い人なら、少しカフェインを摂っただけで、夜眠れなくなってしまうことも少なくありません。とはいえ、カフェインに脳の覚醒効果があるのは事実です。朝の勉強や仕事の前にコーヒーを飲んで頭をスッキリさせるのは、理にかなった戦略といえます。
個人差はありますが、適度なカフェインの摂取量は、1日にコーヒー2〜3杯程度が目安です。カフェインで体調を崩さないように、カフェインが含まれる飲料を飲む際は、カフェインを摂る時間帯と適量をきちんと把握しておくようにしましょう。
頭が冴えるオススメの習慣とは
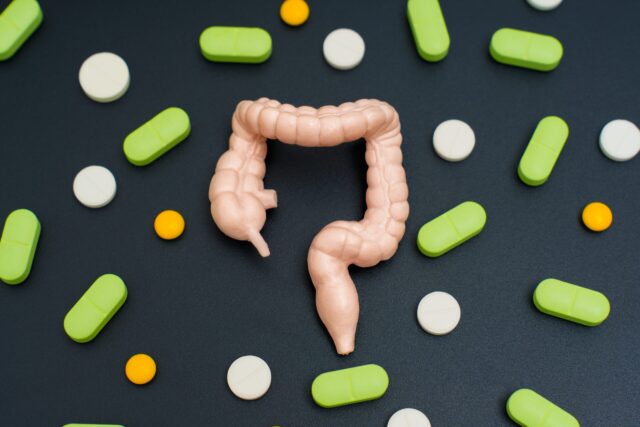
頭が冴える食生活の次は、頭が冴えるオススメの習慣を10個紹介します。一気にすべて改善するのは大変なので、優先順位をつけて、ひとつずつじっくりと取り組んでいきましょう。
質の良い睡眠で脳をリセット
睡眠不足になると、集中力や判断力が著しく低下します。夜ふかしした翌日は、日中眠くなったり、タスクに集中できなくなったりしませんか。こういった弊害が起こるのも、簡単にいえば、脳が十分に休めていないからです。
また、人間の脳は、寝ている間に記憶の整理と定着をおこないます。しかし、整理と定着は、ひと晩に4〜5回だけ発生するレム睡眠中にしかおこなわれません。
そのため、睡眠時間が短くなると、レム睡眠の回数も減り、整理と定着が十分におこなわれないまま朝を迎えることになります。
個人差はありますが、最低7時間、できれば8時間前後の睡眠は取りたいところです。まれに、3〜4時間の睡眠で足りるショートスリーパーの人もいますが、間違っても真似はしないでください。
国立精神・神経医療研究センターの研究※では、1日に4時間半の睡眠不足が5日続くと、不安・抑うつ傾向が高まる可能性があるという結果が明らかになっています。健康的な生活を送るために、しっかりとした睡眠を心がけましょう。
◆睡眠と脳の関係については、コチラの記事でもお読みいただけます
睡眠前のスマホ使用を控える
睡眠の質を上げて脳を冴えさせたいなら、寝る前のスマホ使用はなるべく控えたいところです。就寝前のスマホ最大の問題点は、スマホの画面から発せられるブルーライトにあります。
夜になると、睡眠の質を高めるホルモン「メラトニン」が分泌されます。しかし、強いブルーライトを目に受けると、メラトニンの分泌が弱まってしまうのです。その結果、体内時計が乱れてしまい、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。
しっかりと眠れなければ、脳は十分な休息が取れず、翌日のパフォーマンスが大きく下がってしまうのは当然です。最低でも就寝の1時間前(できれば2時間)にはスマホから離れて、読書やストレッチなどをしながらゆっくり過ごすことをオススメします。
そうすれば、ブルーライトの影響を受けずに翌朝スッキリ目覚めて、頭の働きがグンと冴えてくるでしょう。
週2回の運動で血流を改善
適度な運動は、体と心の健康にとてもよい影響を与えます。頭が冴える状態をできるだけ維持したい人は、少なくとも週に2回の運動を継続できるように頑張ってみてください。
運動は、筋肉を肥大させ、心肺機能も強化してくれます。1,000ccの車と3,000ccの車を比較したら、圧倒的に3,000ccの方が走りに余裕がありますよね。1,000ccの車が3,000ccと同じスピードで走ろうと思ったら、エンジンを高速回転させなければなりません。
そうなれば、当然エンジンや車体に負担がかかり、車の寿命が著しく低下してしまいます。人間の体も、同様です。同じ活動をするにしても、大きくて丈夫な体なら、それだけ体に負担がかからずに済みます。
疲れにくい体になれば、なにをしても楽なので、じっくりと頭を働かせるゆとりが生まれるというわけです。
また、運動は睡眠の質を高める効果もあります。体を適度に動かせば、夜にぐっすりと眠れるようになり、スッキリとした状態で1日をスタートできるでしょう。適切な運動の強度と回数については、別記事で詳しく解説しています。そちらの記事も参考にしてください。
◆運動の強度と回数については、コチラの記事でお読みいただけます
朝散歩でセロトニンを活性化
朝に散歩をすると、脳内のセロトニンが活性化し、集中力や意欲が向上します。なぜ朝におこなう散歩がよいのかというと、太陽の光がセロトニンの分泌を促進してくれるからです。
セロトニンには体内時計を正常にリセットする働きがあり、5分程度の日光浴で効果が出始めます。ただ、散歩によってビタミン類生成が始まるまでに、約15分必要です。せっかく朝散歩をするなら、最低15分、できれば30分程度続けましょう。
セロトニンが低下すると、イライラしたり、気分が落ち込んだり、うつ病に似た症状を引き起こします。「なんとなく調子が出ないな…」という日は、朝散歩をするのが億劫になることもあるでしょう。
そういうときは、5分でもいいからとにかく歩き出してください。いったん歩き出してしまえば、案外簡単に15分くらいは歩けてしまうものです。無理をせず、短い時間でもできるだけ毎日続けるのが、朝散歩のコツです。
◆朝散歩のメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
自然のなかでリフレッシュする
自然のなかで過ごす時間は、頭をリセットして澄んだ思考を取り戻す最良の習慣です。森林浴のメリットに関する報告は多数存在しており、たとえば政府広報オンラインのインタビュー記事には、ストレス時に高まる交感神経活動の低下や血圧の低下といった森林浴のメリットが掲載されています。
また環境省の国立公園の紹介サイトにも、以下のようなデータが掲載されています。
- 都市部に比べてNK細胞が2%活性化
- NK細胞が1日で27%上昇
- 副交感神経活動が5倍増加
- コルチゾール(ストレスホルモンの一種)が13%減少
- 森林の香りにより副交感神経活動が8%アップ
また、ミシガン大学の研究では、自然を感じられる環境で20〜30分過ごすのが、もっともストレスホルモンを下げてくれるという結果が報告されています。忙しいなら、仕事帰りに近くの緑道や公園を20分程度歩くだけでも十分です。
無理をして遠くに出かけようとすると、どうしても回数が減り、自然に触れる時間が不足します。まずは、近場の自然と触れ合う時間を増やして、頭をリフレッシュしていきましょう。
※:人はなぜ、森へ行くとリラックスするのか。 | MAY 2024 | HIGHLIGHTING Japan
※:データで見る国立公園の健康効果とは? | 国立公園に、行ってみよう! | 環境省
◆自然のなかで過ごすメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
感情日記で脳のモヤモヤを吐き出す
頭がスッキリしないと感じるときは、感情を紙に書き出す「感情日記」が効果的です。脳にたまったモヤモヤを外に出せば、必要な情報だけが残るので、思考がスッキリとします。
余計な感情を溜め込むと、ほかの大切なことが頭の隅に追いやられてしまいます。余計なことを覚えておくのは、脳にとって大きな負担です。不安や悩み、イライラした感情などは、言語化して頭の外へ追い出してしまいましょう。
もちろん書き出すのは、感情だけでなく、情報や知識などなんでも構いません。情報を可視化すると、判断のクオリティが大きくアップします。忘れや漏れがなくなるからです。
これまで別記事でも、思考を書き出す「ジャーナリング」や「モーニングページ」を紹介してきました。今回は、感情の排出にフォーカスして感情日記と表現しましたが、基本的にどれも同じものです。
重要なのは、とにかく余計な感情や情報を頭から排出して、思考のスペースを作る点にあります。1ページ書きなぐるだけでもよいので、ぜひ感情日記を習慣化してみてください。きっと、頭が冴える感覚を味わえるはずです。
◆モーニングページについては、コチラの記事でお読みいただけます
タイムマネジメントで脳の疲労を防ぐ
脳の疲れを防ぐには、上手なタイムマネジメントが欠かせません。なぜなら、タスクが詰まっていると、脳が常にフル回転となり、余計なエネルギーを消耗してしまうからです。
たとえば、「午前中は思考系の作業」「眠くなる午後の前半は単純作業」といったふうに、時間帯に応じて仕事の内容を振り分けるだけでも、脳への負担はぐっと軽減されます。また、やるべきことを決めておくことで、ほかのことに気を取られずに集中できるというメリットもあります。
さらに、「やらないことリスト」を作成してみるのも有効です。つい手を出してしまう雑務や、断りづらい依頼をあらかじめ棚卸ししておけば、意思決定に使うエネルギーを節約できます。
時間をうまく区切り、脳の負担をコントロールすることは、冴えた思考を保つための土台ともいうべき重要なポイントです。どうもものごとがうまく回らないと感じているなら、タイムマネジメントを意識してみてください。
新しいことを学び脳に刺激を与える
いつも同じようなことばかり繰り返していると、深く考えなくてもこなせてしまいます。そのため、脳が省エネモードに入ってしまい、いざというときに本来のパフォーマンスを発揮できません。
もし、今の生活がマンネリ気味だと思うなら、ぜひなにか新しいことに挑戦してみてください。新しい挑戦をすると、覚えること・やらなければいけないことがたくさん出てくるので、半分眠っていた脳が再び活性化してくるでしょう。
また、新しいことを学ぶときは、わかる・できるようになるまで、何回も繰り返し練習(復習)するはずです。そうすると新しい情報に対応しようとして、神経細胞を増やそうとか、信号の伝達をスムーズにしようと脳が働きだします。
さらに、新しいことに挑戦する際には、自然と新しい人々との出会いや経験が増えます。そうやって新しい価値観や考え方に触れるようになると、脳が刺激を受けて、ますます頭が冴えた状態になるわけです。
資格の勉強でもスポーツでも、なんでもよいので、まずはなにかひとつ新しいことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
音楽でストレスを解放する
音楽の力をうまく活用できると、ストレスが和らいで頭がスッキリします。というのも、心地よい音楽には副交感神経を優位にして、脳の緊張を緩める作用があるからです。
たとえば、クラシックやヒーリングミュージックを聴いていると、自然と呼吸が深くなり、気持ちが落ち着いてきた経験はありませんか? これは音楽が感情や記憶をつかさどる脳の領域を刺激し、ストレスホルモンの分泌を抑えてくれるためです。
また、リズムに合わせて軽く体を揺らしたり、鼻歌を歌ったりするだけでも、気分がほぐれて脳の疲れが和らいでいきます。ジャンルにこだわる必要はありません。少し激しいくらいのロックでも、自分が「気持ちいい」と思えるなら全然OKです。
楽器が演奏できるなら、好きな音楽を自分でプレイしてみるのもよいストレス対策になってくれるでしょう。どういった形にせよ、音楽はストレス解消に非常に効果を発揮してくれます。忙しい日常の合間に、好きな音楽で脳をひと休みさせてあげましょう。
◆音楽が脳に与える影響については、コチラの記事でもお読みいただけます
デジタルデトックスで脳の疲れをとる
長時間スマートフォンやパソコンを使っていると、目が疲れるし、肩や首も凝ってきます。目がしょぼしょぼして肩がガチガチな状態で、よいパフォーマンスを出すのはむずかしいでしょう。
仕事で使っているとしても、定期的にそういったデバイスと距離を置く意識は本当に重要です。たとえば、1時間パソコンを使ったら5分休むというだけでも、気持ちはものすごくリフレッシュします。
また本来なら、作業中にスマートフォンはNGです。よく机の上に置いている人がいますけども、チラッとスマートフォンが視界に入るだけでも集中力は途切れてしまいます。
米テキサス大学が2017年におこなったスマートフォンが認知機能に与える実験※では、以下3つのグループを比較しました。
- 机の上に置きっぱなしにしたグループ
- ポケットやカバンにしまったグループ
- 別の部屋に置いたグループ
結果は、別の部屋に置いた人たちの圧勝で、次にカバンにしまった人、最低だったのは机の上に置いていた人たちだったのです。
集中して作業をする際には、必ずスマートフォンを見えないところにしまってください。その時間は連絡がつかないものと割り切って、電源を切ってしまうのもよい方法です。
※参考: The Mere Presence of Your Smartphone Reduces Brain Power, Study Shows – UT News
今すぐ頭をスッキリさせたいときの対処法

忙しく仕事が詰まっているのに頭がぼんやりして集中できないときは、今すぐ頭をスッキリさせたいと思いますよね。この章では、すぐに試せて効果を感じやすい「頭を冴えさせる対処法」をまとめました。気分を素早くリセットしたいときに、ぜひ活用してみてください。
適度に短い休憩をはさむ
どんなに集中力のある人でも、長時間同じことをしていると、脳が疲れてきて集中力が落ちます。頭が冴えた状態をキープしたいなら、適度に短い休憩を挟んでください。
オススメは、ポモドーロテクニックです。ポモドーロテクニックとは、25分間の作業と5分間の休憩をワンセットにした時間術です。何時間も作業が続くと思えば途中で嫌になってしまいそうですが、わずか25分間と考えれば、多少疲れていても乗り切れます。
ポイントは、休憩の使い方にあります。休憩になると、多くの人はスマートフォンを触りだすでしょう。しかし、スマートフォンを使っている限り、脳は休まらずにかえって疲れてしまいます。
休憩時には、コーヒーを淹れる・トイレにいく・軽くストレッチをするなど、とにかく立ち上がって席から離れることをオススメします。パソコン作業で目が疲れるので、目を閉じる、あるいは遠くを見るなどして、目を休ませるのもよい休憩の取り方です。
それでも今ひとつ頭が働かないと思ったら、フルーツやナッツ、チョコレートなどをつまんで、脳に栄養を与えてあげてください。
そうすれば、あなたの集中力は大きく崩れることなく、効率よくタスクに取り組めるでしょう。
◆ポモドーロテクニックのメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
ストレッチ+軽いウォーキングで酸素を取り入れる
仕事や勉強で集中力が切れてきたときは、軽いストレッチやウォーキングがオススメです。体を動かすと脳に酸素が行き渡り、頭が一気に冴えてきます。長時間座りっぱなしで作業を続けている主なデメリットは以下の通りです。
- 血流が滞りやすくなり、むくみや冷え性の原因になる
- 肩こりや腰痛を引き起こしやすくなる
- 筋力の低下や姿勢の悪化につながる
- 代謝が落ちて太りやすくなる
- 糖尿病・高血圧・心疾患のリスクを高める
- 気分が沈みやすくなる(うつ傾向)
- やる気や作業意欲の低下を引き起こす
- 脳への血流が減少し、思考力や判断力が鈍くなる
- 呼吸が浅くなり、酸素不足で注意力が散漫になる
もちろん、座る時間が長いからといって、上記の症状が必ず発生するわけではありません。しかし、座りっぱなしが体や脳にマイナスな影響を与える可能性があるなら、面倒くさがらずしっかりと対策をおこなうべきです。
とはいっても、何時間も歩いたりハードな筋トレをしたりする必要はないので安心してください。肩を回したり、腰をひねったりする簡単なストレッチや、オフィスや自宅内を2〜3分歩くだけで十分です。
短時間の仮眠で脳を休める
午後の眠気や集中力の低下を感じたら、20〜30分ほどの仮眠が非常に有効です。これは感覚的に頭が冴えるというレベルではなく、さまざまな検証により仮眠の有益性が実証されています。
たとえば、全米睡眠財団(National Sleep Foundation)の記事※1に掲載されたNASAの研究では、26分間昼寝をしたパイロットは、昼寝をしなかったパイロットに比べ、覚醒度が最大54%上昇し、仕事のパフォーマンスが34%向上したそうです。
さらに、仮眠をとらなかったパイロットが2倍の眠気を示したのに対し、昼寝をした人たちはフライトの終盤に眠気を感じることがほとんどありませんでした。
このデータが示すように、短時間の仮眠は、忙しい日中でも脳の疲労を効率的に回復させる「最強のリセット法」といえます。
ただし、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023※2」のなかに、「30分以上の昼寝を習慣としている人は、昼寝習慣がない人と比べ、将来の死亡リスクが1.27倍に増加する」というデータが記載されています。
寝すぎ防止のため、タイマーなどを使い、30分以内というルールをできるだけ守るように注意しましょう。
※1:NASA Nap: How to Power Nap Like an Astronaut | Sleep Foundation
◆昼寝の効能については、コチラの記事でもお読みいただけます
ペパーミントやレモンなど香りの力を活用する
気分がぼんやりしているときは、ペパーミントやレモンの香りを嗅ぐと脳が刺激され、頭がスッキリ冴えてきます。香りは嗅覚を通じて大脳辺縁系にダイレクトに働きかけるため、感情や集中力にすばやく効果を発揮してくれるのです。
ペパーミントには覚醒作用やリフレッシュ、レモンには鎮静や気分を高める効果があるとされ、アロマテラピーの分野でも非常に高い人気を誇っています。
オフィスでディフューザーを使うのはむずかしいと思いますので、アロマスプレーやハンドクリームなどを活用するのがオススメです。ティッシュにワンプッシュして匂いを感じれば、気分が切り替わり「もうひと頑張りしよう」という前向きなスイッチが入りやすくなります。
香りの力は手軽に取り入れられるうえに即効性もあり、脳をリフレッシュさせたいときの頼れる味方になってくれるでしょう。
◆香りの効能については、コチラの記事でもお読みいただけます
ガムを噛んで集中力を高める
集中力を高めたいときには、ガムを噛むのが意外と効果的です。というのも、噛むことによって脳の前頭前野が刺激され、注意力や記憶力が一時的に向上するといわれているからです。
実際に、イギリスの大学による研究では、ガムを噛みながらタスクに取り組んだ被験者のほうが、噛まなかったグループに比べて集中力が高く、作業効率もよかったという結果が出ています。
ただし、ガムの効果は約20分程度と、比較的短時間に限定されます。常時噛んでいてもあまり意味がないので、ここぞという本番のときに使うのが効果的です。
また、ストレスやイライラがたまっているときにも、ガムを噛むことで気分が落ち着くことがあります。これはリズミカルな咀嚼の動きがリラックス効果をもたらすためです。
集中したい場面やリフレッシュしたいときには、ガムを一粒口に入れてみましょう。びっくりするくらい、気持ちがスーッと落ち着いてくれるかもしれませんよ。
※:The Cognitive Benefits Of Chewing Gum | WIRED
「478呼吸法」でリラックス&集中力アップ
まず結論から言うと、「478呼吸法」を上手に取り入れると、リラックスしながらも集中力を高める一石二鳥の効果が得られます。なぜなら、呼吸を整えることで副交感神経と交感神経のバランスが整い、脳が最適な状態に導かれるからです。
具体的には、次のような呼吸サイクルを繰り返します。
- 4秒間かけて鼻から息を吸う
- 7秒間息を止める
- 8秒間かけて口からゆっくり吐く
一定のリズムで呼吸をしていると、少しずつ心拍数が整い、気分が落ち着いてきます。焦りやストレスを感じていると、どうしても呼吸が浅くなりがちです。深くゆったりとした呼吸で、リラックスした気持ちを取り戻しましょう。
もちろん、常時478呼吸法をおこなう必要はありません。疲れて集中力が途切れたときに、上記のサイクルを3〜4回おこなえば十分です。わずか1分程度の呼吸法で、リラックスできるなら、やらない手はありませんよね。
別記事で「448呼吸法」や「ボックスブリージング」も紹介しています。ぜひそちらの記事も確認しておいてください。
◆448呼吸法については、コチラの記事でお読みいただけます
◆ボックスブリージングについては、コチラの記事でお読みいただけます
まとめ
本文中で説明したように、頭が冴える状態を維持したいなら、食生活をはじめとする生活習慣を整えるのが出発点になります。そうやって頭がしっかりと働く状態をつくったうえで、今回紹介したオススメの習慣に取り組んでみてください。そうすれば、必ず脳の働きは改善されるはずです。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読 







