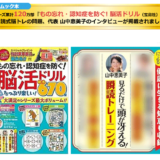記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
よく「直感を信じて動いてみたらうまくいった」という内容の話を耳にします。考えてみると、この直感というのは、非常に不思議な能力です。
普段私たちは、論理的に考えて失敗しないように行動しています。それなのに、その一方で頭にひらめいた直感を信じるケースも意外に多いです。
私たちは、なにを基準にものごとを判断するのが正しいのでしょうか。果たして無条件に直感を信じても大丈夫なのでしょうか。
今回は、あらためて直感を定義づけて、直感を引き出す方法や直感がうまく働かない原因について、わかりやすく解説していきます。
目次
直感とはどういう能力のこと?

知っているようでじつはよくわかっていないのが、私たちの直感です。直感を引き出す方法をお伝えする前に、まずは直感についてもう少し深掘りしていきたいと思います。
直感の定義 : なぜ人間は直感をひらめくのか
ひと言でわかりやすく説明すると、「直感とは、論理的な理由なしに頭に浮かんだ判断」を指します。普通は直感が生まれたプロセスを特別意識していないので、直感はいきなり出現したものと思い込みがちです。
しかしそういった直感は、決していきなり生まれたものではありません。状況を見て、過去の記憶や経験を瞬時に振り返った結果、導き出された最適解なのです。いわゆる、「経験則」に近いものだと考えれば、わかりやすいでしょう。
情報が極端に少なかった大昔には、この直感的な判断が非常に重要でした。理屈ではなく、「マズイ!」と感じたら、即座に行動しないと命を落としかねなかったのです。直感は、私たちが元々備えている生存本能と、大きく関係していると考えられます。
もちろん、複雑な事情の絡み合った現代社会において、直感を盲目的に信じる行為は非常にリスキーです。直感を大事にしつつも、しっかりと裏づけを取る慎重さは、常に意識しておくべきでしょう。
直感は日常生活でどのように使われているか
大人になれば、誰もが「自分は論理的思考でものごとを判断している」と思っているものです。ところがよく考えてみると、直感というか、第一印象でものごとを判断している状況が結構あることに気づきます。
たとえば、ショッピングにいき、無数にディスプレイされている商品のなかから、思わず手に取ってしまう商品ってありますよね。
この瞬間、深く論理的に必要性を考えている人など、ほとんどいません。これまでの自分の好みを瞬間的に振り返り、「これはいいかも……」と判断したから、手を伸ばしてしまったわけです。
初対面の人と会うときも、同様なプロセスが発生します。人は見た目ではないといいますが、顔つき・髪型・服装・体型などから受ける第一印象で、その人の好感度は大きく左右されるはずです。
もっとも、こういった印象は、実際に話してみると180度ひっくり返ることがよくあります。そう考えると、第一印象による決めつけは極力避けたほうが無難です。
直感と他の能力との関係性
直感は、いっけん論理的思考や分析力と対照的な能力のように見えます。しかし実際には、これらの能力と直感は密接に関連しており、相互補完的な役割を果たしているのです。
まず、論理的思考は情報を整理し、因果関係を明確にする重要な役割を担っています。この論理的な背景があるからこそ、直感的に「これは正しい」と判断ができるわけです。
逆に、直感は未知の領域や情報不足下での判断をサポートしますが、その後の具体的な行動に関しては、論理的思考と分析力が欠かせません。
さらに、感受性や共感力も直感と深く結びついています。他者の感情や状況を感じ取る能力があると、ちょっとした表情の変化や行動からより正しい直感的な判断が下せます。
このように、直感は決して独立した能力ではなく、他の多様な能力と連携することで成立しているのです。
直感がアップする方法

前述のとおり、直感はさまざまな能力との連携により成り立っています。もし、直感力をアップさせたいのなら、そういった周辺の能力を鍛えるのがもっとも近道です。ここでは、直感がアップする方法を11個紹介します。
とにかく判断のベースとなる経験値を増やす
新しい状況や問題に直面したとき、私たちは過去の類似経験を振り返り、無意識のうちに解決策や方向性を探し出そうとします。こういったプロセスに関しては、時間をかけてじっくりと検討する場合でも、直感でパッと判断する場合でもまったく同じです。
直感の精度を向上させたいのであれば、とにかく判断のベースとなる経験値を増やすことが重要になってきます。では、どのようにして経験値を増やせばいいのでしょうか。答えは非常にシンプルで、以下のようなことを心がけるだけです。
- 新しいことに挑戦する
- 異なる視点や文化に触れる
- 判断が正しかったかどうか検証する
あれこれ悩む前に、とにかくなんでもやってみること。とくに新しいことへの挑戦は、あなたの経験値を大きくジャンプアップさせてくれます。他人の意見に耳を傾けるのもいいし、海外にいくなど、異なる文化に触れてみるのも有効です。
また、自分の判断をあとから検証すると、大きな気づきが生まれます。こういったことを繰り返すうちに、自然と直感力は磨かれていくでしょう。
過去の実績に囚われない
ここまで何度もお伝えしているように、過去の成功や失敗は、直感のベースとなる重要な指針です。しかし、過去の経験に囚われすぎると、新しい発想の芽を摘んでしまう可能性があります。
たとえば、過去に何件も連続で契約が取れたという、成功体験があったとしましょう。時間が過ぎ、違うアプローチが必要になっても、なまじ大きな成功体験があると、その成功体験にしがみつく人も多いです。
また、過去に手痛い失敗を経験すると、似たような状況に再び対峙した際には、どうしても同様の判断を避けてしまいます。「もう、同じミスは犯したくない」と思うのでしょうね。しかし本当は、失敗した際の判断を少しだけ修正すれば、十分対応できたかもしれません。
このように成功・失敗を問わず、過去に強烈な体験をしていればいるほど、似たような状況下で適切な判断を下すのは困難です。直感の力を借りるには、過去の実績に縛られず、開かれた心と視点をもちつづける姿勢が重要になってくるでしょう。
論理的思考を意識する
前述のとおり論理的思考は、直感のベースとなる判断材料を揃えてくれる、非常に重要な能力です。また論理的思考は、直感の正当性を確認する、大きな助けになってくれます。
いくら論理的思考が直感のベースになるといっても、私たちは普段その関係性を特別意識しているわけではありません。そのため、時として根拠の薄い、思いつきに近い間違った判断をしてしまうことがあります。
こういった事態を防ぐには、普段から論理的思考を意識しておくのが一番です。そうすればかりに直感が間違った判断をしても、「あれ……なにかがおかしいぞ」と、論理的思考が警鐘を鳴らしてくれます。
論理的思考による裏づけがあると、第三者に説明するときも、理解を得られやすいですしね。なお、直感の裏づけという意味でいえば、批判的な視点「クリティカルシンキング」を身につけておくのもオススメです。
クリティカルシンキングについては、以下の記事で概要を解説しています。ぜひ、確認しておいてください。
即断即決を心がける
直感力を鍛えるには、「即断即決」が有効だといわれています。なぜなら、即断即決を繰り返すうちに、蓄積された経験や知識と直感の連携性がレベルアップするからです。
人は日常的に多くの判断を求められます。その際、情報収集や考慮に時間をかけて、慎重に判断するほうが賢明とされるケースも多いです。しかし、「考え過ぎ」という言葉があるように、慎重な思考が直感より優れているとは限りません。
科学的な調査やマーケティングリサーチが必要な分野はともかく、通常はまず決断を下すことを優先してみてください。
あとから検証して、その直感が間違っていれば修正を施し、その経験をまた次回に活かすというのが、直感を鍛える最短ルートだと思います。
また、「いったん決断を下したら、その決断が正解になるように行動をする」という考え方も大切です。そのときはその直感が間違っていたとしても、行動で結果を変えてしまうのです。そうすれば、直感が正しいかどうか、過度に悩む必要がなくなります。
新しいことに取り組んでみる
「経験値を増やす」でも触れたように、直感力を高めるには、未知の体験や新しい知識の取得が非常に有効です。新しい経験は、私たちの心と体の両方を刺激し、斬新な視点や思考パターンを生み出してくれます。
新しいチャレンジは、スポーツ・趣味・仕事、なんでも構いません。外国人と別言語で会話してみるのもおもしろそうだし、取りかかりとして、普段読まないジャンルの本を読むだけでも十分効果が期待できます。
また、新しいことにチャレンジすると、多少なりとも不安や恐れを感じるものです。そういったマイナスな気持ちを乗り越えると、自分に自信がつき、直感の精度もアップします。
なによりも、新しいチャレンジから得られる知識や経験は、何事にも代えがたい宝物です。やってみたいことがあれば、ぜひチャレンジしてみてください。
人にどう思われるかを一切考慮しない
直感を高めるためには、「他人の目」を気にせず、自分の内なる声に耳を傾けることが重要になってきます。それなのに、私たちはどうしても社会的な期待や評価を気にしてしまいがちです。
しかし、直感は自分自身の判断基準から生まれるものであり、他人の意見に左右されるものではありません。
とにかく、自分がなにを感じ、なにを考えているのか、そこだけに集中しましょう。そうすれば、必ずなんらかの反応が自分のなかから返ってきます。たとえそれが一般的な考え方に反するものであっても、その感覚があなたにとっての正解なのです。
もちろん、誰かと関わって生きている以上、第三者の意見や評価を完全に無視するのはむずかしいと思います。他人の反応は、私たちの直感にプラスの効果を与えてくれる場合もあるし、逆に直感を邪魔してくる可能性も高いです。
なので、そういった意見は参考程度にとどめ、あくまでも自分の直感に従って決断を下す機会を増やしてください。そうすれば、直感は徐々に研ぎ澄まされていくでしょう。
ものごとを反対方向から考えてみる
固定観念は、直感力の大敵です。自分のなかにある「◯◯はこうあるべき」という考え方が多ければ多いほど、間違った判断を引き起こしやすくなります。
固定観念を減らすには、ものごとを反対方向から考えるアプローチが非常に有効です。「◯◯でなければいけない」「◯◯で当然だろう」という考えをいったんストップして、代わりに自分の固定観念とは反対の方向から考えてみてください。
- 長い→短い
- 重い→軽い
- 多い→少ない
- 高い→安い
- 厚い→薄い
- 苦しい→楽
- むずかしい→簡単
世の中には、自分がむずかしいと思っていることを、サクサクと進めていく人がいます。「これは高い」と躊躇している間に、「効果を考えたら安いものだ」と、しっかり投資金額以上のリターンを手にしている人もいるのです。
もちろん、自分の考えに自信をもつのも大切です。でも、世の中にはあなたと別な視点でものごとを捉えている人が、数多くいることを忘れてはいけません。自分の視点が、常に正しいとは限らないのです。
逆転思考をうまく取り入れて、ぜひ柔軟な発想を身につけていきましょう。
クリエイティブな活動に取り組む
直感力を高めたい人は、なにかしらクリエイティブな活動に取り組んでみるのも、よいアイデアだと思います。
絵を描く・音楽を演奏する・詩やエッセイを書くなど、自己表現は自分の心の動きと向き合う、非常によいきっかけになってくれるはずです。
クリエイティブな活動は、また、新しいアイデアや発想を生み出してくれます。創造力は右脳が得意とする能力であり、直感もまた右脳が管轄する能力です。
そのほかにも、クリエイティブな作業をしている間、私たちは右脳のもつ「イメージ化」や「全体を把握する力」「感受性」をフル稼働しています。
つまり、クリエイティブな活動によって右脳がフル活用され、その結果、右脳が得意とする「直感」も鍛えられていくわけです。
ギターを習ってもいいし、プラモデルをつくってみるのもいいでしょう。内容はなんでも構わないので、自分の気に入ったアート活動にぜひ取り組んでみてください。
◆アートと右脳の関係については、コチラの記事でお読みいただけます
自然と触れ合う時間をもつ
私たちが暮らすこの日常生活には、対人関係・激務・睡眠不足など、ストレスを招く要素が数多く存在します。直感力を発揮するには、ストレスで弱った心をまず落ち着かせて、直感がうまく働くような下地をつくってあげなければなりません。
その下地づくりの方法として、「自然との触れ合い」は、非常にオススメです。森の散策・静かな湖畔でお弁当を食べる、あるいは単に公園でのんびりと過ごすだけでも、心がリセットされて直感がより鋭敏になっていくでしょう。
フィンランド森林研究所の研究※1では、公園と森林で15分間座ってのんびりするだけで、メンタルが回復したそうです。さらに、自然のなかにいた被験者は、都会にいた人たちより20%気分がよく、創造性がアップしたと報告されています。
国立公園のサイト※2にも、森林を眺めると「副交感神経活動(リラックスしている状態)が1.5倍、ストレスホルモン13%減少」すると書かれていました。
脳がリラックスしてストレスが軽減すれば、直感が働きやすくなるのも当然です。最低でも週に1回は、自然のなかで過ごすように意識してみてください。
※参考1:How Just 15 Minutes of Nature Can Make You Happier | Time
※参考2:データで見る国立公園の健康効果とは? | 国立公園に、行ってみよう! | 環境省
◆自然のリラックス効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
瞑想やリラクゼーションで内なる自分と向き合う
直感力を高める効果的な手段として、瞑想やリラクゼーションもオススメです。ただ、瞑想やリラクセーションには、それこそ何百という種類があるので、今回は一般的な瞑想を例に話をしていきます。
たとえば、あなたに転職のオファーがきたとしましょう。ずっと興味のあった分野の仕事で、話を聞いた瞬間にあなたはやってみたいと思いました。
しかし、時間が経つにつれ、「でも、慣れない分野でうまくいくとも限らないし……」「給料も最初は下がってしまうしなあ……」と、現状にとどまろうという思考が頭中に湧き上がってくるはずです。
残念ながら、瞑想をしてもこういった雑念はなくなりません。だから、なくそうとするのではなく、沸き起こったさまざまな思考をいったん思考の外に追いやってしまうのです。
そうすると、徐々に自分の内側にある素直な想い(直感)と、外的な思考の違いがわかってきます。
もちろん、リスク対策は必要ですが、直感の精度を上げるという意味では、瞑想は非常に有効な手段です。別記事でも、瞑想について紹介しているので、よかったら目を通してみてください。
◆瞑想と直感力の関係については、コチラの記事でもお読みいただけます
書く瞑想「ジャーナリング」を定期的におこなう
いつもいろいろな意見が頭を飛び交っていて、自分の本当の気持ちがわからないという人には、ジャーナリングをオススメします。ジャーナリングとは、自分の頭に浮かんだことを書き出す行為のことです。
不安や疑問点を頭のなかで考えようとすると思考が散らかってしまい、思考の内容を覚えておくだけでも、脳に大きな負担がかかります。
ところが、ジャーナリングで思考をどんどん書き出せば、覚えておく労力がいらず、そのぶん余裕をもって思考の整理や対策が可能です。さらに、眼の前に情報がすべて揃っているので、客観的に自分の考えを分析できます。
また、思いついたことを書き出す行為は、今の自分に集中する「マインドフルネス(瞑想の一種)」とも共通しています。瞑想のバリエーションとして、気軽に取り組んでみてはいかがでしょうか。
やり方については、とくにむずかしい決まりはありません。紙とペンを用意して、思いつくまま書きなぐってください。
とはいえ、慣れていないうちから、フリースタイルで書くのはむずかしいと思われます。「悩んでいること」「キャリアの方向性」「対人関係」など、なんらかのテーマを決めておくほうがいいでしょう。
直感力を邪魔する要因とは

いくら直感力を鍛えても、一方で直感力を邪魔する要因がそのままになっていれば、思うような効果は期待できません。最後にこの章では、直感力を邪魔する5つの要因について、解説していきます。
直感は信用できないと心のどこかで思っている
多くの人々は、直感をどこか不確かなものとして捉えています。そのため、直感という抽象的な感覚を信じきれず、行動に移せないケースが非常に多いのです。
これは、論理的な思考やデータに基づく判断を重視する学校や社会のしくみが、大きく関係していると考えられます。しかし、直感は過去の経験や知識から、無意識のうちに導き出した経験則です。
直感は論理的な思考では捉えきれない、本能から生まれるシグナルであると、まずはきちんと理解しておかなければなりません。
もちろん、ミスのないようにあとから論理的な検証はするべきでしょう。でも、無意識ではあっても、その人の経験と知識でフィルタリングされた結果が直感です。
無下に否定するのではなく、「論理と直感」両方のバランスを取りながら、よりよい判断を下すように心がけてください。
慢性的な疲労とストレスで精神的な余裕がない
人々の直感力は、心と体の状態に大きく影響されます。直感がよく外れる人は、たいてい慢性的な疲労やストレスを抱えているものです。
疲れていると、脳は最低限の働きをこなすので精一杯となり、新しい状況に対応する余裕がありません。こういう精神状況下では、直感を生み出すシステムにバグが生じるのは、当然の結果といえます。
さらに、強いストレスに長期間さらされていると、私たちの脳は「戦うか逃げるか」「0%か100%」といった極端な思考に陥りがちです。こういったモード下では、こまやかで多角的な視点をもつことがむずかしく、結果として直感力も低下してしまいます。
対応策としては、とにかくストレスを遠ざけ、心身ともによい状態に近づけていくしかありません。
マインドフルネス瞑想などを使って、じっくりと自分の現状と向き合ってみるのもいいでしょう。直感力と大きく関係しているセロトニンの分泌を促すために、日光浴や軽い運動、食生活・睡眠を改善するのも非常に効果的です。
◆マインドフルネスについては、コチラの記事でお読みいただけます
◆ストレスとセロトニンの関係については、コチラの記事でお読みいただけます
直感力を阻害する思考パターンが身についてしまっている
私たちの直感は、多くの場面で、よい結果へ導く有効なガイドラインになってくれます。しかし、あまりにも特定の思考パターン(前述の固定観念)が強く働いてしまうと、安易に直感力を信じるのは危険です。
- 必ず正解はあるはずだ
- 普通は◯◯だろう
- ◯◯など起こるはずがない
- 〜すべきだ
- ◯◯は好きじゃない
- ◯◯が好きだ
上記はあくまでも一例ですが、こういった思考が頭に浮かぶようなら、直感は最適解からズレてしまっている可能性が高いです。決めつけや好みは、偏った判断を生み出し、最適解を遠ざけます。
問題は、「こういった思考の歪みに本人はまったく気づいていない」ところにあります。気づいていないどころか、自分は正しいと思っているので、独力で改善するのは相当大変です。
もし自分の直感に自信がないなら、いちど自分の思考パターンを疑ってみましょう。そして、第三者に自分の思考について尋ねてみてください。もしかすると、あなただけが気づいていなかった悪い思考のクセに気づけるかもしれません。
情報が多すぎて頭がいつも混乱している
現代社会は、間違いなく情報過多の時代です。毎日私たちは、勉強や仕事に関するデータ・ニュース・ソーシャルメディアといった大量の情報にさらされています。
こういった情報が、仕事や生活に役立つ側面があるのは事実です。今さらインターネットのない時代に戻れと言われても、みんな困ってしまうでしょう。
しかし、直感という面にフォーカスすれば、多すぎる情報で頭が常に混乱している状態になり、本能的な感覚が鈍くなっているのは間違いありません。
選択肢が多いのは、一見よいことのように思えます。ところが、多すぎる選択肢は迷いを生み出すものです。2択くらいならともかく、情報が多すぎると、重要な情報と必要ない情報を選択するだけで脳が疲れてしまいます。
情報の選別に脳の働きの大部分を奪われてしまい、本当に重要なものを見抜く直感力が曇ってしまっているのが、現代の大きな問題のひとつです。
こういった状況を回避するためにも、定期的なデジタルデトックスをオススメします。情報から距離を置く時間を設けると、直感力が徐々に回復していくのに気づくはずです。
ルーチンワークが多すぎる
多すぎるルーチンワークも、直感力を鈍らせる大きな一因になります。作業効率を考えれば、なにも考えずにサクサクと作業が進むルーチンワークは非常に効率的といえるでしょう。
しかし、やることに慣れてしまうと、新しいアイデアや異なるアプローチを探求する余地が少なくなり、結果として直感力が低下します。直感力は、新鮮な刺激や未知の状況に反応して活性化されるものです。
もし、海外旅行で不慣れな場所に迷い込んでしまったら、全身の感覚を総動員して周囲の状況を確認しますよね。危ない場所ではないか・襲われるのではないか・次になにをすればいいか、防衛本能が直感を極限まで研ぎ澄ませている状態です。
これは少々極端な例ですが、普段と違う状況は、私たちの直感を思い切り刺激してくれます。もちろん、ここまで極端な経験をいつも味わう必要はありません。
「いつもと異なるルートで通勤する」「新しい趣味やスキルを学ぶ」または「仕事で新しい方法を試してみる」など、ほんの少しの変化であなたの直感力は大きく活性化するでしょう。
◆新しいことにチャレンジするメリットについては、コチラの記事でお読みいただけます
直感を鈍らせる最大の要因「固定観念」を捨てるコツ

直感力を鈍らせる最大の要因は、ズバリ固定観念です。最後に固定観念を捨て直感力を磨くコツを、4つ紹介します。
苦手なこと・嫌いなことにあえて取り組んでみる
直感力を鍛えるためには、自分のコンフォートゾーン(快適な領域)を超えて、苦手なことや嫌いなことにあえて挑戦してみてください。
コンフォートゾーンにいるのは、正直楽です。自分のできることや得意なことばかりやっていれば、失敗することもなく、いつも穏やかな気持ちでいられるでしょう。
しかし、コンフォートゾーンでの楽ちんな生活は、先ほどお話ししたルーチンワークとまったく同じ状態です。直感を鍛えたいなら、時々コンフォートゾーンから出て、苦手なことや嫌いなことに挑戦する時間が必要になります。
たとえば、普段絶対に読まないジャンルの本を読んだり、苦手意識のある交流会に参加してみたりと、普段やらないことならなんでも構いません。こういった普段体験しない状況は、私たちに適度な緊張感をもたらし、直感を研ぎ澄ませてくれます。
クリティカルシンキングを身につける
クリティカルシンキングも、直感力を高める重要なステップのひとつです。クリティカルシンキングとは、ものごとを批判的視点から捉えて、正当性を判断する思考法です。
クリティカルシンキングでは、疑問をもつことが基本になります。
- なぜなのか?
- 本当に正しいのか?
- ほかに選択肢はないのか?
私たちは、誰でも大なり小なり固定観念をもっているものです。自分の知識や経験は正しいと思い込んでしまうと、直感で導きだした判断に偏りが生じます。そして残念なことに、自分ではその偏りになかなか気づけません。
クリティカルシンキングというのは、いうなれば客観的かつ多角的な視点から、ものごとを捉える技術です。客観的にものごとを考える癖がつけば、自然と直感の精度はレベルアップしてきます。
なお、クリティカルシンキングとロジカルシンキングは、相互に補完しあう関係にあります。クリティカルシンキングで正しい判断材料を選択し、ロジカルシンキングで適切な判断を導き出す。
ぜひ、クリティカルシンキングと一緒に、ロジカルシンキングについても勉強してみてください。
さまざまな価値観に触れる
直感力を高めるには、多様な文化や価値観に触れ、自分の視野を広げる意識が非常に重要です。私たちの直感は、過去の経験や学んだ知識に大きく影響されます。そのため、気づかないうちに、思い込みでさまざまな可能性を否定してしまいがちです。
でも、世の中、自分の知らないことの方が多いと思いませんか?
自分の見ている世界がすべて正しいと思ってしまえば、直感が間違っていても気づかないままです。
ぜひ、いろいろな価値観に触れて、自分の視野を広げてください。たとえば、海外へ旅行に行ってみるのもいいでしょう。日本の常識は世界の非常識というくらい、まったく違う価値観が世界には溢れています。
もちろん、私たちの価値観が間違っているわけではありません。その辺はどうか誤解しないでください。大事なのは、自分と違う価値観や視点が世の中にたくさんあるという事実を、しっかりと理解することです。
◆「さまざまな価値観に触れる」については、コチラの記事でもお読みいただけます
読書をする
先ほど、さまざまな価値観に触れる重要性をお伝えしました。しかし、実際そう頻繁に旅行へ行けるわけでもないし、イベントに参加するといっても回数にはどうしても限界があります。
そこで、オススメなのが、読書です。読書は、私たちに新しい情報・異なる価値観・多様な経験を教えてくれます。わざわざ出かける必要もないし、時間のあるとき、いつでも気軽に取り組めるのが嬉しいですよね。
しかも、一冊1,000〜2,000円ほどの出費しかかからないわけですから、これほどコスパのいい方法はないと断言できます。
自分の好きな分野を深掘りしてもいいし、あえて知らないジャンルに挑戦してみるのも、価値観を増やすという意味では非常にオススメです。
もし、本を読むのが苦手なら、ぜひ速読に挑戦してみてください。速読ができるようになれば、本を読むのが苦痛ではなくなります。速読については以下の記事で詳しく解説しています。興味のある方は、ぜひ読んでみてください。
まとめ
日常生活やビジネスシーンでの判断に影響を与える直感力を最大限に活かすためには、経験値の積み重ねや論理的思考の養成が不可欠です。
マインドフルネスや思考パターンの改善などを取り入れて、直感を阻害する原因を減らし、今回紹介した「直感を鍛える方法」にしっかりと取り組んでいきましょう。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読