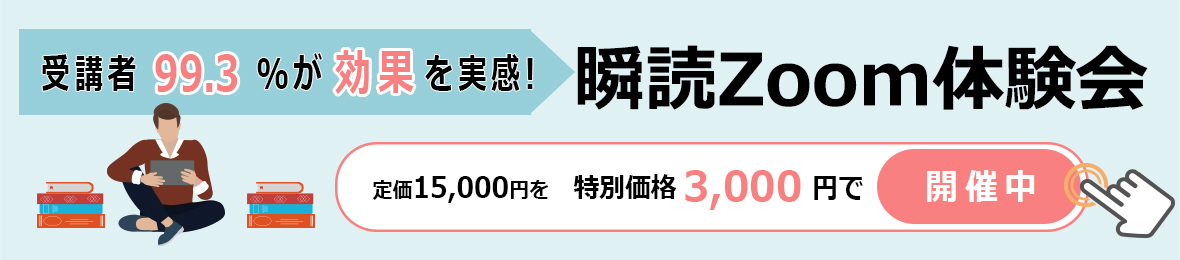記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
「やることをすぐに忘れてしまう」といったことが頻繁に起こるようになったら、短期記憶がうまく働いていない可能性が高いです。一時的に記憶をストックしておく機能が衰えると、記憶や会話、読み書きといった基本的な活動に大きく影響を及ぼします。
当記事では、短期記憶の基本的なしくみや短期記憶を改善する方法などについて、わかりやすく解説していきます。少しでも記憶力に不安を感じている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
短期記憶とは?まずはしくみを理解しよう

記憶力を改善したいなら、まずは記憶力についてきちんと理解しておく必要があります。とくに、短期記憶と長期記憶の違いを知っておくことは非常に重要です。それでは、ひとつずつ確認していきましょう。
短期記憶と長期記憶の違い
記憶は、記憶を保持できる時間によって、大きく短期記憶と長期記憶の2種類に分けられます。まず短期記憶ですが、記憶を保持できる時間は数分から、長くても数時間程度しか覚えておけません。記憶量的にも、5〜6個が限界といわれており、時間の経過とともにほとんどを忘れてしまいます。
一方、長期記憶は、年単位での記憶が可能です。今聞いた電話番号はすぐに忘れてしまいますが、自分の電話番号は何年経っても忘れませんよね。これは、使用頻度が多いため、脳が重要な情報と判断して、長期記憶として保存するように指令を出しているからです。
ようするに、短期記憶は「今すぐに使う情報」を覚えるためのもの、長期記憶は「ずっと覚えておきたい情報」を保存するためのものになります。
なお、短期記憶と深い関連のある「ワーキングメモリ」についても、しっかりと理解しておく必要があります。ワーキングメモリについては、次項で詳しく見ていきましょう。
一時的な作業をコントロールするワーキングメモリ
作業中だけ覚えておけばいい情報を保存して、処理する機能を「ワーキングメモリ」といいます。パソコンのキャッシュメモリと同様の役割を果たしていると考えれば、イメージしやすいかもしれません。
作業のための記憶装置なので、記憶できる量も時間も非常に短いです。諸説ありますが、7桁±2程度の量を数分間記憶しておくのが限界といわれています。
このように、非常に小さい容量の記憶ですが、役割は非常に重要です。もし、ワーキングメモリの機能が狂ってしまえば、会話もできないし、計算もむずかしいでしょう。会話をする際に、聞いた内容をすぐに忘れてしまえば、会話が成立しません。
買い物にいき、計算の途中でそれまで購入した金額を忘れてしまえば、「100円のキノコが2袋で200円、ニンジンが1袋200円だから、あれキノコはいくらだっけ?」といつまでも計算が終わらないでしょう。
またワーキングメモリには、一時保存された外界からの情報や過去の情報を取捨選択し、次の行動を決定していくという重要な役割があります。だから、ワーキングメモリを中心とした短期記憶力を磨いていくと、より適切な行動ができ、生活の質が向上します。
◆ワーキングメモリの働きについては、コチラの記事でもお読みいただけます
短期記憶がうまく働かないとどうなる?
短期記憶がうまく働かないと、日常のちょっとした行動にも支障が出てきます。というのも、短期記憶は「今必要な情報」を一時的に保管しておく働きをしているからです。
たとえば、買い物リストを思い出せない、会話中に話の流れを見失う、読みかけの本の内容をすぐ忘れてしまうといったトラブルが起きやすくなります。また、忘れてはいけない情報を何度も確認する必要があるため、タスク処理のスピードも低下してしまいます。
こうしたトラブルが積み重なると、自信が低下し、メンタルにも悪影響を及ぼしかねません。それどころか、認知症レベルにまで記憶力低下が進行すれば、通常の日常生活が送れなくなってしまう可能性すらあります。
短期記憶は、日常生活に直結する土台ともいえる機能です。うまく機能していないと感じたら、早めに対策を取るように心がけましょう。
短期記憶はトレーニングで改善できる
短期記憶は先天的な能力だけで決まるものではありません。個人差はありますが、意識的なトレーニングによって、短期記憶力は伸ばせます。その理由は、脳が「可塑性(かそせい)」という柔軟な性質をもっているからです。
可塑性とは、新しい体験や学習によって脳が刺激を受け、神経細胞のつながりが変化して脳機能が向上する状態を指します。
たとえば、何回も計算問題を解けば、計算に脳が適応して計算がスムーズにできるようになります。また自転車の乗り方を練習するうちに、段々と転ばなくなり、いつの間にか乗れるようになっている。こういう「失敗→学習」というプロセスも、脳の可塑性によるものです。
記憶力を鍛えたいなら、記憶力を使うトレーニングをたくさんおこなってください。そうすれば、脳の可塑性の働きにより、少しずつ記憶力が向上していきます。
「忘れっぽさ」は変えられないものとあきらめるのではなく、鍛えられる力として前向きに向き合うことが改善の第一歩となります。
生活習慣の見直しが短期記憶改善の第一歩

脳は精密なゆえに、非常にデリケートな器官です。そのため、生活習慣の影響を受けやすく、生活習慣が乱れると短期記憶力は低下してしまう可能性があります。
脳によい食生活に切り替える
脳の主なエネルギー源は、血液中に含まれるブドウ糖です。最近、ごはんや麺類といった糖質を制限している人も多いですが、過度の糖質制限はオススメできません。タンパク質・炭水化物・脂質を中心に、ビタミンやミネラルをバランスよく摂取しましょう。
また、脳によいといわれる栄養素も、積極的に摂るようにしたいですね。たとえば、オメガ3脂肪酸が多く含まれる魚(サーモンやサバなど)や、ビタミンEが豊富なナッツ類(アーモンドやクルミなど)は、脳の働きを助けてくれます。
また、ブルーベリーやほうれん草のように、抗酸化物質が多量に含まれる食品もオススメです。なかでも、ほうれん草に含まれるグルタチオンは、アルツハイマー病の原因となるアミロイドβを分解する働きがあるといわれています。
今回紹介した栄養素は、ほんの一例であり、脳によい食材はほかにも数多く存在します。いろいろと試してみながら、今日からぜひ、脳によい食材を意識して食事を楽しんでみてください。
◆脳によい食材(ブレインフード)については、コチラの記事でもお読みいただけます
運動を習慣化して脳を活性化する
運動を習慣化できれば、脳の血流が活性化され、短期記憶が改善される可能性がアップします。とはいえ、普段あまり運動していない人がいきなり激しい運動をすれば、体がダメージを受けてしまうでしょう。
そうなると、やはり軽いウォーキングやストレッチからはじめるのが無難です。軽いとはいっても、ウォーキングやストレッチは全身をしっかりと使います。
ストレッチはともかく、歩くときに使うのは下半身だけとつい考えがちです。でも、姿勢のキープに腹筋を使うし、腕を振れば上半身も一緒に鍛えられます。まずは、毎日20分程度でよいので、近所の散歩からはじめてみてください。
慣れてきたら、少しずつ筋トレにも取り組んでいきましょう。筋トレ自体の消費カロリーは微々たるものですが、筋肉が肥大することで、基礎代謝がアップします。スクワットのような運動で下半身を鍛えれば、ふくらはぎのポンプ機能により、全身の血流もよくなるでしょう。
当然、脳に供給される血液量も増えるため、栄養と酸素をたっぷりと受け取った脳の働きはどんどん活性化していきます。
◆運動の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
良質な睡眠を最低7時間以上確保する
睡眠中に脳は1日の情報を整理し、必要な情報を長期記憶として保存します。睡眠中といっても記憶の整理と定着がおこなわれるのは、レム睡眠中だけです。レム睡眠は、ひと晩に4〜5回しか発生しません。しかも、回数を重ねるごとに1回の時間が長くなっていきます。
そのため、夜ふかしをして睡眠時間が短くなるとレム睡眠の回数が減り、さらに明け方の長いレム睡眠を逃してしまうわけです。そうなると、記憶の整理と定着が十分におこなわれないまま、翌日を迎えることになってしまいます。
記憶の定着をしっかりおこなうためにも、最低7時間以上の睡眠は確保してください。もちろん、年齢によって必要な睡眠時間は異なります。年齢を重ねるごとに睡眠時間は短くなっていくものですが、もっとも短い高齢者(65歳以上)でも7〜8時間は必要とされているのです。7時間は、本当に最低限の睡眠時間だと考えてくださいね。
なお、睡眠時間と同様に、睡眠の質も非常に重要です。以下に良質な睡眠のポイントをまとめておきますので参考にしていただければと思います。
- 入眠と起床時間をできるだけ一定にする
- 寝る直前のスマートフォンを控える
- 寝る2時間前にはアルコールの摂取をやめる
- 枕の高さや布団の質を吟味する
- 部屋の温度と室温を適切な状態にコントロールする
- 遮光カーテンなどで明け方の太陽光をしっかりと遮断する
◆運動の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
メンタルケアで脳へのダメージを最小限に抑える
ストレスは、脳の正常な活動に大きなダメージを与える可能性が高いです。たとえば、カリフォルニア大学のサイト※には、「慢性的なストレスは、海馬の神経細胞を縮小させ、記憶力や学習能力を低下させる可能性がある」といった研究データが掲載されています。
本来なら、ストレスの原因を明確にして、迅速に対応できればベストでしょう。しかし、人間関係・お金・健康といったさまざまなストレスは根深いものが多く、すぐに解決できるものばかりではありません。
そのため、ストレスから受けるダメージを軽減するためのマネジメント法を、しっかりと身につけておく必要があります。
オススメは、呼吸法と瞑想です。呼吸法は即効性があるので、心がイライラしてどうしようもないときは、まず呼吸法を試してみるのをオススメします。瞑想なら、知名度と取り組みやすさから、座禅やマインドフルネス瞑想がオススメです。
また、ストレス解消には、夢中になれる趣味も非常に役立ってくれます。今、なにも趣味がないという人は、楽器演奏でもスポーツでもなんでも構いません。嫌なことを忘れて没頭できる趣味が見つかるまで、いろいろと試してみましょう。
※参考: Chronic stress primes brain for mental illness | University of California
◆呼吸法ボックスブリージングの効能については、コチラの記事でお読みいただけます
◆瞑想の効能については、コチラの記事でお読みいただけます
集中できる環境づくりを意識する
短期記憶を改善するなら、集中力が必須条件になります。ところが、私たちの周りを見渡してみると、びっくりするほど誘惑だらけです。なので、まずは集中しやすい環境をいかに整えられるかが、短期記憶改善のポイントになってきます。
最初に手をつけるべきは、机周りです。仕事や勉強をする机周りが散らかっていると、集中力は大きく低下します。気にしないようにしていても、散らかった文房具や本が視界に入ると、「あー、片づけしなきゃ」と意識をもっていかれてしまうのです。
机の上に置くのは、パソコンとライトだけというくらい、徹底的に視界に入るノイズを減らしてしまいましょう。
また、集中力という意味では、音や照明、椅子の調整も非常に重要です。周りの音が気になって作業に集中できないなら、場所を変えるか、ノイズキャンセリングイヤホンの使用も検討すべきでしょう。
明るすぎる(暗すぎる)部屋は、目の疲労を促進し、集中力を奪います。椅子も同様です。薄くて硬い椅子は、腰や背中の痛みを招きやすく、集中力が続きません。
◆集中力を高める環境づくりについては、コチラの記事でもお読みいただけます
短期記憶を鍛える!今すぐ試せる9つの方法

短期記憶を鍛えるには、とにかく脳によい刺激を与えることが重要です。今回は、短期記憶を鍛える方法を9つ紹介します。
1. ゲーム要素の多い脳トレで楽しく記憶力アップ
短期記憶を鍛えるなら、パズルなどゲーム感覚の強いトレーニングが効果的です。前述の通り、脳は適切な刺激を受け続けると、脳の可塑性により脳細胞が成長します。
ゲームの要素があると楽しみながら脳トレができるので、「覚える→思い出す」回数を大きく増やせます。
クロスワードパズルや間違い探しといった定番の脳トレ以外にも、料理や麻雀のような作業系の脳トレも、記憶力強化には非常に効果的です。
どういった脳トレに取り組むにしても、記憶力改善を成功させるには、脳トレアプリの活用が欠かせません。スマホやタブレットで使える脳トレアプリなら、通勤中やスキマ時間にも手軽に取り組めるのが魅力です。
また、脳トレアプリにはAIが搭載されているものも多く、自分のレベルを正確に分析して、最適な問題を出題してくれます。こういった進捗管理機能のおかげで、得意なことばかりやったり、苦手なことを後回しにしたりといったことが回避できるのです。
せっかく脳トレに取り組むのなら、最善の結果を出せるように、ゲーム要素の強い脳トレアプリを活用していきましょう。
◆短期記憶改善にオススメのアプリについては、コチラの記事でお読みいただけます
2. アクティブリコールで記憶の引き出しを強化
記憶力を高めたいなら、思い出す練習の習慣化が欠かせません。思い出す練習を意識的におこなうのが、アクティブリコールという学習法です。
たとえば、ノートや参考書を閉じた状態で「どこまで覚えているか」を自分に問いかけてみる。目次を見て内容を思い出す。覚えた内容を他人に説明するといった作業が、アクティブリコールに該当します。
どの方法に取り組むにせよ、テキストを読むだけと比べて、記憶の定着度が格段にアップするのに気づくでしょう。これは、うろ覚えのなか、一生懸命記憶を遡ろうとして、脳が強い刺激を受けているから起きる現象です。
人によっては、いちいち確認するなんて面倒くさいと感じるかもしれません。でも、手間をかけただけの価値はあります。記憶力を高めたい人は、ぜひアクティブリコールを取り入れてください。
なお、とくにオススメのアクティブリコールとして、次の項目で自己テストを紹介します。
◆アクティブリコールについては、コチラの記事でもお読みいただけます
3. 自己テストで覚えたつもりから脱却する
先ほどアクティブリコールでも紹介した自己テストは、覚えたつもりを回避する最強の方法です。記憶は「インプットしただけ」では定着しにくく、アウトプットによって深まる性質があります。
そのため、インプットとアウトプットを同時におこなう自己テストが、非常に役立ってくれるわけです。やり方は以下のように、非常にシンプルです。
- テキストを読んだら一旦閉じる
- 覚えたい内容について自分で質問する
- テキストを見ないで答える
テキストを閉じて「さっき読んだポイントはなんだったのか」と自分に問いかけてみましょう。最初の頃は、おそらく数秒前に読んだ内容が口から出てこずに、びっくりしてしまうはずです。
もし、まったく思い出せなくても問題ありません。うまく答えられなければ、そこが理解や記憶があいまいな部分です。自己テストによって、覚えるべき箇所が明確になったのですから、あとはそこを重点的に復習すればいいだけです。
うろ覚えな記憶をすぐに忘れてしまうのは、当然のことといえます。記憶の定着度を高めるために、自己テストで理解度の確認をこまめにおこなってください。
4. スペースド・リピティションで効率よく復習
短期記憶のなかでとくに重要だと脳が判断した情報は、最終的に長期記憶として保存されます。この記憶の移行に問題が生じると、物忘れなどが頻繁に発生しやすくなってくるんですね。
短期記憶から長期記憶へのスムーズな移行には、復習がもっとも重要なポイントになります。なかでも、スペースド・リピティション(間隔学習)は、記憶の効率的な定着に対して、非常に効果が期待できる復習方法です。
間隔学習という名前の通り、復習の間隔の取り方が、この復習法の大きなポイントになります。1回目の復習のあと、同じ間隔で復習を繰り返すのではなく、徐々に復習の間隔を長く設定してください。
- 1回目:最初の学習後24時間以内
- 2回目:前回の復習から1週間後
- 3回目:前回の復習から3週間後
上記はあくまでも一例ですが、とにかく「忘れた頃に記憶を上書きする」のが、スペースド・リピティションをうまく回すコツです。
そういう意味では、フラッシュカードを使ったインプットは、スペースド・リピティションと非常に相性がよいといえます。覚えにくい内容はこまめに復習をして、記憶に残らない内容だけを何回も繰り返す方法に、フラッシュカードは最適です。
◆オススメの復習間隔については、コチラの記事でもお読みいただけます
5. ジャーナリングで記憶の整理を習慣化する
記憶力を高めたいなら、思考を「書き出す」習慣を取り入れてみましょう。なかでもオススメなのが、「ジャーナリング」です。
日々の出来事や考えていること、または感じたことをそのままノートに書き出す行為をジャーナリングといいます。書く内容によっては、日記とほぼ変わらないともいえますが、内容に一切制限がないのがジャーナリングの大きな特徴です。
頭のなかにある思考や気持ちを書き出すには、脳内の情報を整理する必要があるため、自然と記憶の再構築が始まります。たとえば、「今日の◯◯は大失敗だったな……」と反省をするできごとがあったとしましょう。
失敗の内容、原因、自分の行動への振り返り、今後の対策、そのとき感じた気持ち、記憶の扉が開かれて、どんどん書くことが湧き上がってくるはずです。この深く記憶を遡る作業が、私たちの記憶力に刺激を与え、成長させてくれます。
また、頭のなかのモヤモヤを外に出せば、余計なストレスが減り、脳の働きも安定します。ストレスは、記憶力や集中力といった脳の認知機能に悪影響を及ぼす大きな原因のひとつです。頭のなかをいつもクリアに保っておくためにも、ぜひジャーナリングに取り組んでみてください。
◆ジャーナリングの効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
6. 会話や人との交流で記憶を刺激する
他人との会話は、短期記憶に適度な刺激を与える絶好のトレーニングになります。というのも、会話中はそれまでの会話の内容をしっかりと覚えておく必要があるからです。
当たり前ですが、話の内容をしっかりと覚えておかないと、会話は成立しません。話した内容を覚えておき、状況に適した情報を記憶から取り出す流れが、短期記憶を鍛えてくれます。
そういう意味では、いつも同じメンバーが集まる場所よりも、新しい出会いのある交流会やイベントのほうがオススメです。初めて受け取る情報を記憶に留めておかなければならないので、記憶がより高い負荷を受けます。
名前や役職といった情報をしっかりと覚えておかないと、相手に失礼です。多少の失礼は許される家族や友達と違い、関係性の浅い人との交流には、よい意味での緊張感が生まれます。
いずれにせよ、人と話す行為は、記憶力向上の絶好の機会です。イベントや交流の場があれば、面倒くさがらず、積極的に参加していきましょう。
7. 新しいことに挑戦して脳に刺激を与える
短期記憶の衰えを予防したい人は、ぜひなにか新しいことに挑戦してみてください。ジャンルは、楽器を習う・外国語を学ぶ・絵を描くなど、なんでも構いません。新しいことに挑戦すると、脳は常に新しい情報を処理しなければならないため、記憶力や集中力が向上します。
たとえば、ギターを習う場合、覚える→試す→間違える→修正するというプロセスを何度も繰り返すようになるでしょう。この一連の流れによって、神経細胞をつなぐシナプスが増え、そして定着してくれます。
つまり、練習の繰り返しにより、神経細胞が強化され記憶力が向上するわけです。新しく覚えたことを1回でできる人はまずいませんから、必然的に何回も繰り返すようになります。だから、記憶力を改善したい人は、どんどん新しいことに取り組むべきなのです。
最初はなかなかうまくできなくて、イライラすることもあるでしょう。しかし、繰り返し学ぶ過程で、必ず上達を感じるときがきます。ぜひ、焦らずいろいろなことに挑戦してみてください。
8. 音楽やリズムを使って記憶に残す
音楽やリズムは、記憶を定着させる強力なツールです。というのも、リズムやメロディは感情や身体の動きと結びつきやすく、記憶に残りやすい性質をもっているからです。
たとえば、英単語や歴史の年号を語呂合わせやメロディに乗せて覚えた経験はないでしょうか?ただ機械的に覚えるよりも、記憶に残りやすく、メロディがフックになって記憶を呼び起こしやすいのも大きなメリットです。
また、楽器の演奏なども、記憶力の向上によい影響を与えてくれます。楽器を演奏する場合、譜面を覚えたりリズムを感じ取ったり、アレンジを考えたりといった作業が不可欠です。1曲だけでなく、何曲もこういった作業をおこなうので、自然と短期記憶が鍛えられます。
まったく音楽に興味がなければむずかしいかもしれませんが、少しでも音楽が好きなら、音楽やリズムを積極的に活用していきたいですね。
◆楽器演奏の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
9. 視覚情報と結びつけて記憶する
覚えたい情報を「目で見える形」に変えるだけで、記憶への定着率はぐっと高まります。というのも、人間の脳は視覚的な刺激に強く反応するしくみをもっており、文字だけよりも図・色・イメージを使った情報のほうが印象に残りやすいのです。
たとえば、勉強中の内容をイラスト化したり、色分けしたマインドマップにまとめたりすると、脳内で情報が整理され、思い出しやすくなります。プレゼンで使用するスライド資料に図表があるだけで理解しやすくなるのは、この原理によるものです。
あまり馴染みがなく難易度の高い内容ほど、視覚と結びつけて覚える工夫が効果を発揮してくれます。記憶に自信がないときは、まず目で見てわかる形に変換することから始めてみましょう。
◆視覚を活用したインプット法については、コチラの記事でもお読みいただけます
記憶力アップのために知っておきたいコツ

先ほど記憶力を鍛える方法について説明をしました。どれも効果が期待できるものばかりですが、ただ漫然と取り組んでいては効果が半減してしまいます。ここでは、より効率的に記憶力をアップさせるためのコツを6つ紹介していきます。
アウトプットを増やして記憶を定着させる
短期記憶を長期的にしっかりと定着させるためには、アウトプットを意識的に増やすことが大切です。受け取った情報をそのままにしておくだけでは、短期記憶の性質上、すぐに忘れてしまいます。
しかし、インプットした情報を復唱したり、書き出したり、実際に行動に移したりしてみてください。そうすれば、脳が重要な情報と判断して、長期的に保存しようと働き出します。
なかでも、新しく学んだことを人に教える行為は、非常に効果的なアウトプット方法です。「誰かに伝えるつもりで学ぶ」と、自然と要点を整理するようになり、記憶が整理されます。理解していないことは、教えられませんからね。
そのほかにも、以下のような方法でアウトプットが可能です。
- 要点ノートを作成する
- ブログやSNSで発信する
- ディスカッションをする
- テキストを見ず記憶を頼りに説明する
勉強の際に過去問題集を解くのも、記憶を確認するという意味で、非常に効果的なアウトプットの方法といえます。
「インプットしたら、できるだけ早くアウトプットをする」このルールを徹底できれば、記憶の定着度は飛躍的にアップするでしょう。
◆インプットの重要性については、コチラの記事でもお読みいただけます
記憶のゴールデンタイムに重要な作業をおこなう
人の記憶力は、いつでも一定なわけではありません。どのような人でも、1日のうちに記憶力の波があるものなのです。だから、記憶力がよく働くタイミングでインプット作業をおこなうと、記憶の定着度は大きく向上します。
オススメは、「記憶のゴールデンタイム」とよばれる時間帯です。記憶のゴールデンタイムは、1日に大きく2回存在します。ひとつは起床後2〜3時間、そして就寝前の1〜2時間です。なかでも、朝のインプットは、記憶の定着に最高の方法になります。
LSBF(ロンドンの有名私立大学)のサイト※を調べてみると、脳は午前10時〜午後2時にもっとも注意力が高まるという記述がありました。さらにより深い学習をおこないたいなら、午前4時から午前7時の時間帯がベストタイムであるとも書かれています。
ひと晩ぐっすり眠り、きちんと朝食を摂った脳は、リフレッシュして元気な状態です。時間と共に脳は少しずつ疲労していくので、元気いっぱいな状態のうちに新しい理論や複雑な概念を学ぶようにすれば、効率よく記憶できます。
※参考: What is the best time for studying—day or night? | LSBF in Singapore.
◆就寝前のゴールデンタイムについては、コチラの記事でお読みいただけます
情報をグループ化して整理する
短期記憶の容量には限りがあり、いちどに覚えられる情報はごくわずかです。しかし、情報を「グループ化」して整理すると、効率よく記憶に残せるようになります。
買い物リストを例に考えてみると、わかりやすいかもしれません。キャベツ・味噌・ラップ・牛乳・鶏むね肉・玉ねぎ・チーズのように、バラバラに書かれていたら覚えるのが大変だし、売り場の移動が増えて非効率です。
これを「野菜」「調味料」「台所用品」「乳製品」のようにカテゴリごとに整理すると、バラバラに覚えるよりもスムーズに記憶できます。さらに、野菜の買い物が終われば野菜に関する情報を覚えておく必要がないので、次のグループの記憶に脳のリソースを回せます。
とはいえ、実際には、このように単純にグループ化できるものばかりとは限りません。私たちを取り巻く状況はもっと複雑に絡み合っていて、グループ化がむずかしいケースも多いものです。
なので、グループ化に慣れていないうちは、必要に応じて図解やマインドマップなどの利用をオススメします。情報を可視化すると、関連性がわかりやすく、グループ化が楽にできるようになるはずです。
◆マインドマップのメリットについては、コチラの記事でお読みいただけます
イメージと関連づけて記憶する
人の脳は、 無機質な文字や数字よりも、イメージ(映像)を記憶しやすいという特徴があります。たとえば、「リンゴ」という言葉を見たとき、「リンゴとはバラ科リンゴ属の落葉高木の果実で、上下に窪みがあり、赤い果皮に包まれているものが多い……」などと考えませんよね。
それよりも、頭のなかに赤くて丸い果物を思い浮かべて、その映像をリンゴとしてフワッと理解するでしょう。百聞は一見にしかずということわざ通りのことが、記憶のメカニズムにも当てはまるのです。
この仕組みを活用すると、記憶力を大きく向上できます。たとえば、名前を覚えるのが苦手な人は、名前とその人の特徴やイメージを結びつけると効果的です。
「山田さんは山登りが好きな人」「ブルーの服をよく着る川村さん」など、視覚的な要素と組み合わせることで記憶が定着しやすくなります。(実際の情報と違っていてもOK)
また、 ストーリー仕立てにして覚えるのもオススメです。一見無関係な情報をうまくつなげてひとつの物語にすると、ただ記憶するより、忘れにくくなります。
◆イメージ化が記憶に与える影響については、コチラの記事でもお読みいただけます
メモを活用して空き容量を増やす
短期記憶の容量には限りがあり、いちどにたくさんの情報を覚えようとしても、仕組み的に無理があります。そこで役立つのが「メモ」です。必要な情報をメモしておけば、脳に負担をかけずに情報を管理できるようになります。
たとえば、仕事で受けた指示やアドバイスを頭のなかで保持しようとすれば、覚えておくことに脳のリソースの大半を取られてしまうでしょう。しかし、メモさえしておけば、極端な話、内容を覚えておく必要がありません。確認したければ、メモを見返せばいいだけですので。
私たちが考える以上に、記憶保持の負担は大きいものです。メモは 「第二の脳」のようなものだと考えてください。
すぐに確認できる場所に情報をまとめておけば、「覚えておかなきゃ」というプレッシャーから解放され、脳に余裕が生まれます。結果として、新しい情報をスムーズに吸収でき、短期記憶の効率を大幅に高められるのです。
◆メモの効能については、コチラの記事でもお読みいただけます
短時間の昼寝が記憶定着を助ける
午後になると疲れてきて、頭がボーッとするという人には、短時間の昼寝が効果的です。昼寝をすると、脳がリフレッシュされ、記憶力も蘇ります。
昼寝のポイントは、「深く寝すぎないこと」です。30分以上寝てしまうと、脳が深い眠りに入ってしまい、目覚めたあとにぼんやりする「睡眠慣性」が発生しやすくなります。昼寝をする際には、以下のポイントに注意して、逆効果にならないように気をつけてください。
- 昼寝のベストタイムは13〜15時
- 15時以降の昼寝を避ける
- 昼寝の時間は長くても30分以内
- ベッドを使わず椅子に座って仮眠を取る
「あれっ、今寝てた?」くらいのごく短い睡眠でも、脳は想像以上にスッキリするものです。時間が取れない場合は、机に突っ伏して5分ほど目を閉じるだけでも効果があります。
◆昼寝の効能については、コチラの記事でもお読みいただけます
まとめ
本文中でもお伝えしたように、短期記憶は日常生活に必要な基礎となるべき能力です。短期記憶が衰えると、会話や読み書きにも支障が出てしまいます。
いつまでも記憶力を維持していくためにも、今回紹介した日常生活の改善や短期記憶の改善方法にぜひ取り組んでみてください。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読