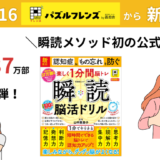記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
「資料や関連書籍を今よりも速く読めたら、もっと効率よく勉強や仕事ができるのに…」そんなふうに思ったことはありませんか?
速読は一部の人だけの特別な技術ではなく、正しい練習をすれば誰でも身につけられるスキルです。この記事では、速読トレーニングのポイントや練習法などを右脳速読法「瞬読」の事例を中心に、初心者にもわかりやすく紹介します。
目次
速読の練習を始める前に知っておきたいこと

速読の練習を始める前に、まず知っておいてほしい大切なポイントがあります。「速読=特殊な才能が必要」と思われがちですが、実際は正しい方法で練習すれば誰でも身につけられるスキルです。
また、速読にもいくつかの種類があり、それぞれアプローチや目的が異なります。この章では、速読の基本的な考え方と種類についてやさしく解説していきます。
速読は一部の人だけの特技ではない
速読は、ごく一部の人にしかできない特別なスキルではありません。速読は「目の使い方」と「脳の処理の仕方」を訓練すれば、誰でも身につけられる技術です。
もともと読書が苦手だった人でも、視線の動かし方や視野を広げるトレーニングを続けて、1分間に読める文字数が2〜3倍に伸びたというケースも少なくありません。それどころか、分速1万文字を超えるスピードで読める人も多数存在します。
もちろん、誰にでもできるとはいっても、きちんとしたメソッドに沿って、一定期間速読の練習を続けることが大前提です。逆を言えば、継続さえできれば本当に誰でも速読はできるということになります。
速読は決して特別なスキルではない。速読の練習法をお伝えする前に、まずはこの事実をしっかりと認識しておいてください。
速読の主な種類と特徴
速読にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やトレーニング法が異なります。代表的なものとしては、以下の3パターンが挙げられます。
- 広い視野で文章をまとめ読みする「視読型速読(しどく)」
- 文章を映像として処理する「右脳速読」
- 重要な情報だけを素早く拾い読みする「スキミング型速読」
ただ、上記はまったくの別物ではなく、共通するスキルも多いです。たとえば、文章を映像化して理解する右脳速読も、広い視野をもって文章をまとめ読みします。ある程度文章をまとめて読めないと、映像をイメージできませんので。
また、すべての文章に目を通しながらも、イメージ化のために最低限必要なポイントをピックアップする点は、スキミング的速読と共通しています。
逆に、違いも数多くあります。たとえば、一般的な視読型速読の場合、読書スピードを上げるために、目を速く動かさなければなりません。一方、右脳速読は、複数の文章もしくはページを丸ごと映像化するので、それほど頻繁な目線移動は発生しないのです。
このように、それぞれ相違点はあるものの、「練習すれば上達する技術」である点は共通しています。そういった点を踏まえて、あとはいかに自分に合ったスタイルを見つけられるかが速読を身につける最大のポイントです。
◆速読法による違いと特徴については、コチラの記事でもお読みいただけます
速読で得られる主なメリット
速読を身につけることで、読書のスピードだけでなく、思考や判断の質まで大きく変わります。主なメリットとしては以下の3つが挙げられます。
- 限られた時間でより多くの情報が手に入る
- 情報処理能力がアップする
- 記憶への定着がスムーズになる
まず、速読最大の利点は「時間の節約」です。同じ1時間でも、通常の2〜3倍の情報を読めるようになるため、学習や仕事の効率が飛躍的に上がります。あるいは読む時間が短くなった分、ほかのことに時間を使うことも可能です。
また、読書スピードが速くなるにつれて、どこが重要な箇所なのか、瞬時に判断できるようになってきます。これは脳の情報処理能力が向上したことを意味し、素早い判断力の恩恵は速読にとどまりません。
さらに右脳速読の場合、右脳のイメージ変換力を活用して映像として記憶するので、より強く記憶に残ります。
このように速読は、単に速く読む技術ではなく、効率性や記憶力向上といった複数のメリットをもたらしてくれる実践的なスキルなのです。なお、そのほかのメリットについては別記事で紹介しています。ぜひそちらの記事にも目を通してみてください。
◆速読の主なメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
速読の練習に適した環境と準備について
速読の効果を高めるには、まず練習する環境の整備が欠かせません。雑音やスマホ通知に邪魔される場所では集中力が途切れやすく、どんなに努力しても成果は出にくいからです。
スマホをカバンのなかにしまって、机の上にあるのは読む本と照明だけという状態にできれば、意識の散漫をかなり防げます。周囲の音が気になる人は、自室や静かな図書館で本を読みましょう。ノイズキャンセリング機能のついたイヤホンを使用するのもよい方法です。
また、照明の明るさや椅子の座り心地といった要素も、意外と集中力に影響を与えるものです。長時間使用しても体に負担のかからない照明と椅子を選んでください。
さらに、目の疲れを防ぐために、適度な休憩も重要なポイントです。勉強のために読むかそれとも娯楽のために読むのかによって変わってきますが、30〜60分をひとつの区切りと考えておけば間違いないでしょう。
◆読書環境については、コチラの記事でもお読みいただけます
速読の基本練習の重要ポイント

速読を身につけるには、まず基本的なトレーニングから始めることが大切です。いきなり速く読もうとしても、視線の動かし方や読み方のクセが変わらなければ、なかなかスピードは上がりません。
右脳速読の具体的なトレーニング方法を紹介する前に、まずは、速読の基本練習のポイントを紹介します。
視野拡大トレーニングで1行全体をとらえる
前述の通り、どの速読でも複数の行をまとめて読む「視読」がベースとなっています。しかし、いきなり複数行をまとめ読みするのは、むずかしいと感じてしまう人もいるかもしれません。
視野拡大の練習をする場合、まずは1行のまとめ読みを目標にしましょう。ほとんどの人は、文字を1語ずつなぞるように読んでしまい、それがスピードの大きな妨げになっています。視読によってこのクセを改善できれば、単純に考えて読むスピードは数倍になるはずですよね。
具体的な練習は、それぞれ速読法ごとに専用のメニューがあるので、それに沿って練習すれば無理なく視読ができるように設計されています。
もちろん、最初はむずかしく感じるかもしれません。ですが、少しずつ範囲を広げていけば、自然と読むスピードが上がりますので安心してください。
◆視読の身につけ方については、コチラの記事でもお読みいただけます
時間制限付き読書で処理スピードを上げる
速読力を高めるには、時間を区切って読む練習がとても効果的です。なぜなら、時間制限があることで集中力が高まり、自然と処理スピードが上がっていくからです。
時間制限がないと、途中で内容を確認しようとして、戻り読みをする回数が増えます。戻り読みをしていたら、決して読書スピードは上がりません。時間が限られていると、脳は無駄な戻り読みを減らし、必要な情報を効率よく処理しようとするモードに切り替わります。
右脳速読法の場合、最終的な読書スピードは「1ページ1秒」が基本です。右脳速読の目的は「文章を右脳で一気にイメージ化すること」であり、ゆっくり読んでしまうと、1文字ずつ読む従来の読み方と変わらなくなってしまいます。
もちろん、初めは1ページ3〜5秒程度からスタートし、徐々にスピードを上げていけばOKです。焦らず、少しずつ読書スピードをアップしていきましょう。
音読から視読への切り替えがカギ
速読を身につけるには、「音読」から「視読」への切り替えが大きなカギを握っています。多くの人は文章を読む際に、頭のなかで音読をしているものです。実際に声は出していなくとも、頭のなかで音読をしていたら、それは口から声を出しているのと変わりません。
人が話すスピードは、1分間に300〜400文字が平均といわれています。公共放送のアナウンサーは、理解しやすさを優先して、300文字を目安に話す人が多いそうです。
速読を習得したいなら、まず音読をやめる意識が最重要ポイントになってきます。音読をせずに、視読でまとめ読みできれば、1分間に2,000〜3,000文字で読むことも十分に可能です。
さらに、映像化でまとめ読みの範囲を拡大すれば、それこそ1〜2万文字での速読も夢ではありません。
音読がやめられるか不安な方も安心してください。視読の練習をしてまとめ読みができるようになると、読書スピードが上がるため、自然と音読をしなくなります。
◆音読から視読への切り替えについては、コチラの記事でもお読みいただけます
右脳速読トレーニング4ステップ

速読のなかでも、文章をイメージでとらえる「右脳速読」は、直感的でスピーディーな読み方として非常に注目されています。
すべての速読法の練習法を紹介することはスペースの関係上むずかしいので、今回は私が指導する右脳速読法「瞬読」の練習法をご紹介します。視読を基本にしながら、文章を映像化し、右脳と左脳のバランスを整える独自のプロセスを順を追って身につけていきましょう。
◆右脳速読のトレーニングについては、コチラの記事でもお読みいただけます
ステップ1:まとめ読み(視読)を身につけるトレーニング
ステップ1では、まず「視読=まとめ読み」の力を養います。なぜこのステップが重要かというと、視読を習得すると、目を速く動かす負担を最小限に抑えながら全体を把握できるからです。
目を速く動かすことをベースとするごく一般的な速読の場合、長時間速読をするとどうしても目の周りの筋肉が疲れてしまいやすいです。そうなるとやはりスピードは落ちてしまうので、目を極力動かさない右脳速読独特の視点をこのステップで学びます。
具体的には、ランダムに配置された文字群(例:「メカラ」「ラーンメ」など)を見て、正しい単語や文章に変換する練習をおこないます。このとき、やはり1秒以内が目安です。1秒以上かかると、どうしても左脳で1文字ずつ読む読み方に戻ってしまいます。
3〜5文字程度の単語を視読できるようになったら、次は文章単位の視読(ステップ2)の練習に進みましょう。
ステップ2:文章をイメージに変換するトレーニング
ステップ2では、読んだ文章を頭のなかで映像として変換する「イメージ変換トレーニング」をおこないます。右脳速読は、単に文字を速く読むわけではありません。まとめ読みした文章を、瞬時に映像化して記憶していきます。
文字として理解するより、映像として認識するほうが、圧倒的に処理スピードが速いからです。小説を読むより、漫画のほうが圧倒的に速く読めますよね。右脳速読もそれと同じ原理だとイメージすれば、わかりやすいのではないでしょうか。
具体的には、たとえば、「英語のテストで100点を取った」という文章を読み、瞬時に数字や答案用紙を頭のなかに思い浮かべるように練習します。その際、生徒の服装や髪型などは、あまり重要ではありません。
100点という数字、英語の答案用紙が映像として浮かべば、それで核となる情報はしっかりと理解できています。完璧を目指すのではなく、重要な箇所だけをピックアップして効率よく映像化するのが、イメージ変換トレーニングをマスターするポイントです。
ステップ2の練習が淀みなくできるようになったら、視読の基本はほぼマスターできたと考えてよいでしょう。あとはステップ3に進み、視読の範囲をどんどん広めていきます。
ステップ3:視読の範囲を広げるトレーニング
ステップ3は、ステップ1・2で培った視読力とイメージ変換力を、実際の書籍で実践する「本読みトレーニング」です。この段階では、目の動かし方ではなく、「できるだけ多くの文字を一度に目でとらえる」ことを意識します。
最初は1行ずつでも構いませんが、繰り返すうちに、1行→2行→1ページと少しずつ視野を広げていきます。最終的に見開き1ページ(2ページ分)を1秒で映像に変換できたら、右脳速読はほぼ完成です。
1ページ1秒だと、一般的な実用書の場合、5分程度で1冊を読めるペースです。もちろん、いきなり5分で1冊はむずかしいので、まずは1冊を15分程度で読み切るスピードを目標にするのが現実的でしょう。
いずれにせよ、この段階までくればあとは実践あるのみです。身につけた視読とイメージ変換のスキルで、どんどん速読力を磨いてください。
ステップ4:右脳と左脳のバランスを整えるトレーニング
右脳速読を定着させるには、右脳と左脳のバランスを整えるトレーニングが欠かせません。なぜなら、右脳で高速処理した映像を、左脳で言語化・整理するプロセスがあって初めて「理解」として定着するからです。
具体的には、視読でイメージ化した内容を、文章として紙に書き出します。視読では、主に右脳の特性を使ってイメージ化をおこないました。今度は、映像を言葉に直す作業で、左脳を刺激するわけです。
そうやって、右脳と左脳のバランスを取り、脳全体がスムーズに活動するように調整していくのが、ステップ4トレーニングの目的です。
もちろん、左脳によるアウトプットが目的なので、きれいにメモする必要はありません。なぐり書きで十分ですが、できれば手書きをオススメします。スマホにメモするよりも、末梢神経の集まる手を使う分、より強く脳に刺激を与えられるからです。
書き出しをずっと続ける必要はありませんが、少なくとも練習期間中は必ずおこなうようにしてください。
速読の練習でやりがちな失敗とその解決策

どんなに効果的な速読法でも、続かなければ意味がありません。最初は順調に進んでいても、思うようにスピードが上がらなかったり、内容が頭に入らなかったりして挫折してしまう人は少なからずいます。そこでよくある失敗パターンとその解決策を5つ紹介します。
ただ速く読むだけの「飛ばし読み」は逆効果
速読を意識しすぎるあまり、文章を飛ばし読みしてしまう人は少なくありません。しかし、飛ばし読みはうまくやらないと、理解を浅くし、大切な情報を見落とす原因になります。
とくにビジネス書や実用書のように要点が段落や一文に凝縮されている文章では、たった一文を飛ばすだけで内容の全体像を誤解してしまうことも考えられます。
対策としては、まず飛ばし読みはしないことが基本です。速読メソッドに沿って、ひと通りすべての文章に目を通したうえで、重要な箇所をピックアップするトレーニングをしていきましょう。そうすれば、自然と飛ばし読みのクセは解消できます。
とはいえ、特定の情報だけを調べたい場合などには、飛ばし読み(スキャニング)は非常に有効です。目的に応じて、飛ばし読みと通常の速読をうまく使い分けていきましょう。
理解度の伴わない速読は意味がない
速読を練習するときに、読書スピードを意識しすぎるのは非常に危険です。スピードを過剰に追いかけてしまうと、どうしても内容の理解がおろそかになってしまいます。それでは、「速読」ではなく、ただの「読み流し」です。
速読は単なる速さではなく、「理解とスピードの両立」を目指すトレーニングだと考えてください。かりに1冊を10分で読み切ったとしても、あとから要点を思い出せないのであれば本を読む意味がありません。
それなら、多少読書スピードが落ちても、しっかりと内容を理解できたほうがよいでしょう。たしかに瞬読では、分速1万文字以上のペースで速読できる受講生が数多くいます。しかし、読書スピードには個人差があるものです。
過剰に読書スピードを求めず、ひとまず2倍(分速1,000文字前後)の速さを目標にしてみてください。きちんとしたメソッドに沿った速読法であれば、2倍という数値は比較的簡単にクリアできるレベルです。
本選びを間違えると練習効果が半減する
速読の効果を高めるには、練習で使う本の選び方が非常に重要です。難解な専門書や興味のない内容では集中力が続かず、どうしても理解度が浅くなってしまいます。
最初のうちは、ストーリー性のある小説や自己啓発書など、テンポよく読める本がオススメです。とくにベストセラーは、誰にでも読みやすく書かれているものが多いので、速読の題材としては非常に適しています。
速読に慣れてきたら、徐々にビジネス書や専門書へとステップアップしていきましょう。そうすると、より高度なイメージ化のトレーニングができます。
また右脳速読のように「文章をイメージ化して記憶する」トレーニングでは、イラストや写真が多い本は避けてください。脳が本来のイメージ化プロセスをサボってしまい、右脳速読のトレーニング効果が著しく低下してしまうからです。
速読のトレーニング段階では、「どのような本で練習するか」が成果を左右します。読みたい本ではなく、できるだけシンプルな本を使って成果を最大化していきましょう。
短期間で結果を求めすぎると挫折につながる
速読の効果は、一朝一夕で身につくものではありません。短期間で成果を求めすぎると、思うように成果が出ず、途中で挫折してしまう人も出てくるでしょう。
速読は筋トレや語学学習と同じで、継続することで少しずつ脳の処理スピードや理解力が高まっていくタイプのトレーニングです。
最初のうちは、「読むスピードが上がらない」「理解が追いつかない」と感じるのが当たり前だと思ってください。しかし、毎日15分でも続けていくうちに、段々と目が文字の流れに慣れ、文章の構造を瞬時にとらえられるようになってきます。
とはいえ、目を必要以上に動かす必要のない右脳速読の場合、わずか3時間の体験会で参加者の99%が読書スピード2倍を達成しています。もちろん、それ以上のスピードを求めるなら、継続的なトレーニングは必要です。
ですが、必要以上にスピードを追い求めなければ、速読は想像よりも遥かに低いハードルであることをぜひ知っておいてください。
成長が感じられないと簡単に挫折してしまう
速読を続けていると、努力に対して思うような成果を感じられない時期が必ずあるものです。この伸び悩みの期間をどう乗り越えるかが、継続できるかどうかの分かれ道になってきます。
人は結果が見えないとどうしてもモチベーションが下がりやすく、この停滞期に焦ってやめてしまう人が多いです。ですが、停滞期こそ脳が新しい読み方を吸収している最中なのです。成長が見えにくいだけで、実際には着実に速読力がついています。
そうした停滞期を乗り越えるには、「成長を見える化する工夫」が効果的です。読書スピードを定期的に計測したり、理解度テストや要約メモを残したりすることで、少しずつ進歩していることを確認できます。
また、以前より内容を覚えやすくなった・集中が続くようになったなど、感覚的な変化に気づくことも継続への励みになります。
速読の上達には、焦らず変化を観察する心構えが欠かせません。たとえ現時点で、分速1万文字がクリアできなかったとしても、すでに2倍の速さで読める自分を褒めてあげてください。
速読に関するよくある質問

ここまで記事を読んできた方のなかにも、速読に対してまだまだ疑問や不安を感じている方もいらっしゃるはずです。そこで最後に、速読に関するよくある質問について、わかりやすくお答えしていきます。
速読は誰でもできますか?
結論から言えば、速読は特別な才能がなくても誰でも身につけられる技術です。ページをペラペラめくるスピードの速さに驚き、多くの人が「特別な才能を持った一部の人だけのもの」と思いがちです。
しかし実際は、視野の広げ方や文章の処理方法のトレーニングをおこなえば、必ずスピードは上がっていきます。スポーツや楽器演奏と同様に、正しい方法でトレーニングをおこなえばきちんと成果が表れるものとお考えください。
1回あたりの練習時間はどのくらい必要ですか?
速読の練習は、1日15〜30分程度からスタートして、慣れてきたら少しずつ時間を増やしていくのがオススメです。もちろん、練習時間は長い方が早く結果は出ます。ただ、最初から長時間頑張ってしまうと、集中力が落ち理解力も低下しやすいため、逆効果になりかねません。
短時間でいいから、集中してトレーニングに取り組む方が結果は出やすいです。1日の練習時間よりも、長期間トレーニングを継続することに意識をフォーカスしていきましょう。
マスターするまでの期間はどのくらいが目安になりますか?
速い人なら1週間程度のトレーニングを受けて、分速2,000文字以上のスピードで読めるようになる人もいます。ただ、速読を身につけるまでの期間は、人によって大きく異なります。
あくまでもひとつの目安ですが、本格的にスピードと理解の両立が安定するまでには、3〜6か月ほどかかるのが一般的です。
なお、できるだけ短期間で速読をマスターしたい人は、ある程度集中してトレーニングをおこなう方が、やはり結果は早く出ます。そういう場合は、「瞬読オンライン90日間集中プログラム」の利用をご検討ください。
年齢制限はありますか?
基本的に、速読には年齢制限がありません。脳は年齢に関係なく新しい刺激に反応するため、子どもから高齢者まで誰でもトレーニングが可能です。実際、瞬読では、下は小学生から上は70代まで、幅広い年齢層の方が受講しています。
ただし子どもの場合、文字をしっかり読めるようになる年齢まで、速読は意識しない方がいいです。小学4年生くらいになるまでは、絵本や図鑑などを中心に、まず読書に慣れ親しむことを優先しましょう。
また、ある程度年齢を重ねると、速読に対して高いハードルを感じてしまう人が多いようです。でも安心してください。速読の習得に年齢は関係ありません。瞬読では、77歳の方が30分で1冊読めるようになった事例もあります。
どのくらいの速さで読めるようになりますか?
速読の到達スピードには、正直かなり個人差があります。しかし、速読が苦手な人でも練習を重ねれば、一般的な読書スピード(1分間に400〜800文字程度)の2倍以上まで伸ばすことは十分可能です。
実際、体験レッスンを受講した99%以上の人が、読書スピード2倍以上アップを実現しています。さらに7〜10日くらいのトレーニングによって、分速1万文字以上を達成している人も瞬読にはゴロゴロいます。
もちろん、自分では読書スピードをコントロールできません。過剰にスピードを追い求めずに、まずは2倍以上を目指してトレーニングに取り組んでみてください。
一度覚えたら一生使えるのでしょうか?
基本的に、速読は一度身につけたら一生使える技術です。とはいえ、スポーツや楽器と同様に、しばらく練習をしなければ感覚が鈍り、スピードも落ちてしまいます。
それでもいったん基礎的な読み方を覚えてしまえば、少しのトレーニングで短期間のうちに感覚を取り戻せます。ある程度のレベルに達したあとも、定期的なフォローアップを忘れないようにしてください。
独学でもできるようになりますか?
速読は、独学でも十分に習得可能です。瞬読でも、独学で速読をマスターできるドリル本をご用意しています。瞬読ドリルでは、7日間がひとつの単位になっており、7日目までのドリルをこなせるようになれば、分速4,000文字での速読が可能です。
ただし、独学はどうしても自己流になりやすいため、途中で行き詰まることもあり得ます。もし伸び悩みを感じたら、いちど本格的な講座の受講を検討してみてください。疑問点や不安な点があっても、わかりやすく指導してもらえるので、効率的に速読をマスターできます。
▷▷瞬読書籍はこちらから確認できます
▷▷瞬読zoom体験会についてはこちらから確認できます
速読の代わりに理解度が下がることはありませんか?
多くの人が「速く読むと内容を理解できなくなるのでは」と、心配してしまうようです。ですが、正しい方法で練習すれば、理解力を保ったまま速読ができるようになります。
右脳速読は文字をただ速く読むのではなく、文章のまとまりをイメージでとらえていく読書法です。イメージで理解していくので、大事なポイントがしっかりと頭に入っていきます。
なお瞬読のレッスンを受講すると、じつは単に瞬読という新たな速読法を身につけられるだけではありません。通常の何倍もの速さで速読した本の重要なポイントを、しっかりと書き出せるようになります。
これはまさに、理解度を保ちながら速読ができる証明と言えるでしょう。詳細については、ぜひ体験会でご確認いただければと思います。
まとめ
速読は、特別な才能がなくても正しい方法と継続的な練習で誰でも身につけられるスキルです。速読の指導者として、視読・イメージ化・視野拡大などを段階的に身につけ、速読の楽しさと便利さを多くの人に感じてほしいと願っています。
今回紹介した情報を基に、ぜひ速読の練習に取り組んでみてください。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読