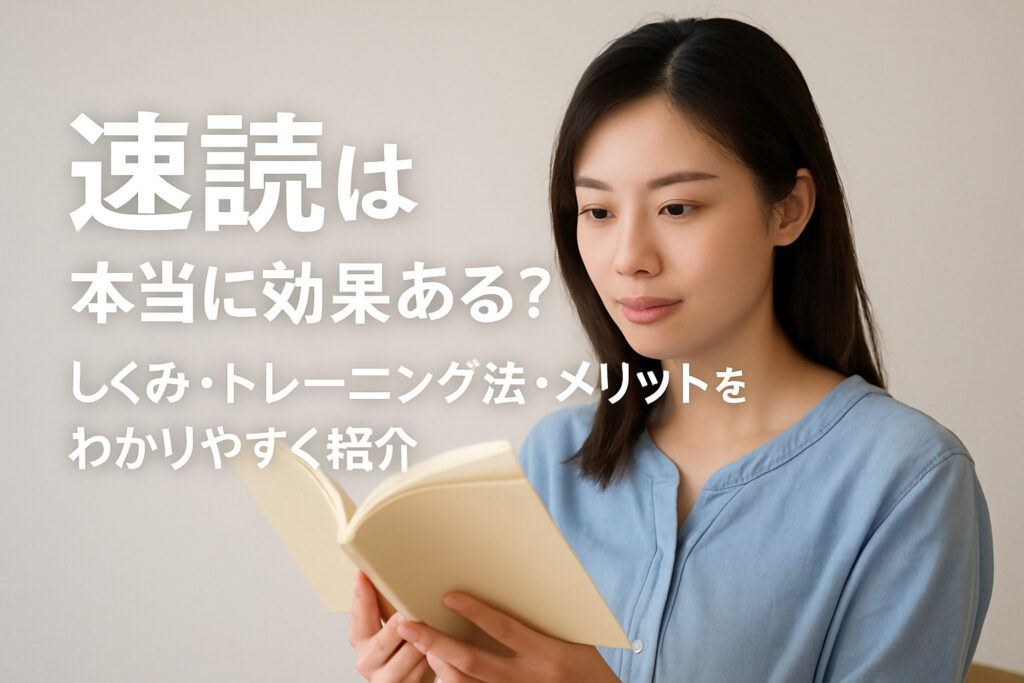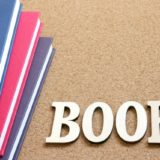記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
厳しい競争社会を勝ち抜くために、たくさんの本を読み、自分をレベルアップしたい。ところが、現実には、忙しすぎて月に1冊の読書すらままならない。このように、自分の理想と現実のギャップに悩みを抱える人は、世の中にたくさんいます。
そういう状況を打破するために速読を身につけたいと思っても、不安を抱えたままでは、なかなか一歩目を踏み出せません。
そこで当記事では、初心者が必ず知っておくべき「速読のしくみ」や「速読のメリット」などについて、わかりやすく解説していきます。
速読をこれからはじめたい、もしくは速読をはじめたばかりの人は、ぜひ今回の記事を読んで、速読に対する不安を解消していただければと思います。
目次
速読は本当に効果があるのか

まず速読初心者が不安に思っているのは、「速読は本当に効果があるのか」という点でしょう。結論からいえば、きちんとした理論のもと指導がおこなわれている速読法ならば、必ずなにかしらの結果は出ます。
たとえば、ある速読団体では分速2,100文字を上級者の目安としています。一般的な読書スピードが分速400〜800文字といわれるなかで、これは約5倍に相当する速さです。
5倍までいかなくても、今の2倍や3倍のスピードで本が読めるようになれば、インプット量が飛躍的に増え、仕事や学習の効率アップにもつながるでしょう。
一方で、速読に対する懐疑的な意見も存在します。速読が脳機能に与える影響については、まだまだ解明されていないことが多いのです。解明されていない点が多いことを理由に、なかには速読を完全に否定する人さえいます。
とはいえ、多くの実践者が速読のメリットを実感しているのもまた事実です。まずはそのしくみやトレーニング方法を理解し、速読の可能性をひとつずつ確認していきましょう。
◆速読の効果については、コチラの記事でお読みいただけます
速読で本が速く読めるしくみ

速読とひと言でいっても、さまざまなメソッドがあり、それぞれアプローチが異なります。ここでは、速読の主流である3つのアプローチと、すべての速読法に共通する「視読(しどく)」という概念について解説します。
速読法1「眼筋を鍛えて目を速く動かす」
日本で長く主流だった速読法のひとつに、「眼筋トレーニング型」の速読があります。これは、目の周囲にある6つの筋肉(上直筋・下直筋・内直筋・外直筋・上斜筋・下斜筋)を鍛えて目の動きをスムーズにし、読書スピードを上げようという考え方です。
目を速く動かせるようになれば、視線の移動も当然速くなり、読む速度が向上するというわけです。ただし、人間の目の動きには物理的な限界があり、たとえ訓練しても3〜5倍が上限といわれています。また、そのスピードを長時間保つのはむずかしく、どうしても目の疲労を感じやすくなります。
このタイプの速読法は、トレーニングがシンプルでわかりやすい反面、継続や習得に個人差があるのも特徴です。受講を決める前に、眼筋トレーニングが自分に合うかどうか、まずは体験レッスンの受講をオススメします。
速読法2「読み方を工夫する」
読書スピードを上げる方法のひとつに、「読み方を工夫する」というアプローチがあります。たとえば、必要な部分だけを重点的に読む「飛ばし読み」や「斜め読み」は、情報の取捨選択によって効率的に読み進められる手法です。
具体的には、目次や見出し、キーワード、接続詞などを意識して、重要な箇所を探し出していきます。たしかに、書籍には導入部や事例など、結論と直接関係ない部分も多く、そういう箇所を飛ばしても大筋の理解に影響はありません。
文章すべてを丁寧に読むのではなく、あくまでも大枠の理解を目的にすれば、読む時間をぐっと短縮できるのです。
こうした読み方は、速読トレーニングの補助的なテクニックとしても有効です。読み飛ばしだけで読書を終えるのではなく、必要な部分を見極める意識で全体を速読でサクッと読めるようになれば、より効率的な読書が可能になります。
速読法3「右脳のイメージ変換能力を活用」
速読のなかでも、近年とくに注目されているのが、右脳の特性を活かした速読法です。言語を処理する左脳に対して、右脳はイメージ変換や全体把握が得意とされています。
この特性を利用し、文字情報を瞬時に映像として捉えて、スピーディーに読書を進めるのが右脳速読の大きな特徴です。
通常の読書では、文字を一語ずつ追いながら理解していきますが、右脳速読では文章全体を視覚的なイメージに変換しながら読み進めます。これにより、理解のスピードと処理の効率が同時に大きく向上するわけです。
右脳速読を実践している人のなかには、1分間に1万文字以上のスピードで読めるようになったというケースが数多くあります。もちろん個人差はありますが、トレーニングを重ねれば、誰でも2〜3倍以上のスピードによる読書が可能です。
◆有名速読法の特徴と違いについては、コチラの記事でお読みいただけます
すべての速読法に共通する「視読」とは
速読の土台となるのが、「視読(しどく)」という読み方です。あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、視読では文字を1文字ずつ追うのではなく、複数の単語や行を「ひとつのかたまり」として視覚的に捉えていきます。
どの速読法においても、この「一度に目に入れる情報量を増やす」トレーニングは共通しています。読むスピードを上げるには、視野を広げて一度に処理できる情報を増やす作業が欠かせないのです。
ただし、視野の広げ方や捉え方は、速読法ごとに結構な違いがあります。従来の速読法では、視線の動きを速くして広範囲をカバーしますが、目が疲れやすくなるというマイナス点はどうしても避けられません。
一方、右脳速読では、文章のイメージ化により、目の動きは最小限で済みます。そのため、眼に対する負担の少ないスムーズな読書が可能です。
いずれにせよ、どの速読法でも、視読は速読の根底を支える重要な基本スキルといえるでしょう。
◆視読の身につけ方については、コチラの記事でお読みいただけます
右脳速読のトレーニング内容を紹介
速読を検討中の方は、実際どのようなトレーニングをするのか、多少なりとも不安を感じているはずです。そこで右脳速読「瞬読」を例に、速読の具体的なトレーニングの流れをステップごとに紹介します。
◆速読のトレーニングについては、コチラの記事でもお読みいただけます
ステップ1:変換力トレーニング

右脳速読トレーニングのファーストステップは、ランダムに配置された文字を頭のなかで並び替えて、知っている言葉に置き換える変換力トレーニングです。
「サギウ→ウサギ」「メリカア→アメリカ」のように、一見意味のなさそうな文字群から、正しい言葉に置き換えていきます。
人間の脳は、「無秩序な状態を嫌い、正常な状態に修正しようとする」本能的な働きを備えています。ステップ1では、この変換力を鍛えるのが目的です。
ポイントは、前述の「視読」です。1文字ずつ読むのではなく、全体をひとかたまりとして捉え、正常な配列を描き出していきます。
また、このトレーニングは制限時間が重要です。1秒以内の変換を目標にしてください。時間をかけすぎると、左脳が文字を一語ずつ分析しはじめ、右脳による変換トレーニングの意味が薄れてしまいます。
なお、この時点では、まだイメージ化まで考える必要はありません。とにかく、文字列をかたまりとして見て、正しい文字列へ瞬間的に変換できる状態をひたすら目指してください。
ステップ2:イメージ力トレーニング

ステップ1で身につけた「文字を瞬時に正しい配列へ変換する力」を土台に、今度は文章をパッと映像として思い描く「イメージ力」を鍛えていきます。
たとえば、「猫の絵が描かれたエプロンを着たお母さんが、フライパンでハンバーグを焼いている」という文章があるとしましょう。
このとき、「猫のエプロン」「お母さん」「ハンバーグ」といったキーワードを瞬時にピックアップし、それらをひとつの絵として思い浮かべます。
すべての情報を正確に覚える必要はありません。エプロンの柄が多少違っていても、フライパンの色が思い出せなくても問題ないのです。大まかなシーンがイメージできていれば、それで十分です。
このトレーニングを繰り返すうちに、文章のキーワードを素早く捉え、映像として記憶に残す力が自然と育っていきます。なお、ステップ1同様に、ステップ2も時間制限が重要です。左脳読みにならないよう、1文1秒を目安にトレーニングをおこなってください。
ステップ3:本読みトレーニング
ステップ3では、いよいよ実際の本を使って、視読とイメージ化を同時におこなうトレーニングに入ります。文章を「読んで理解する」のではなく、ページ全体をパッと見て「シーンとして把握する」感覚を身につけていきます。
もちろん、いきなり1ページ丸ごとイメージする必要はありません。1〜2行ずつから始めて少しずつ読む範囲を広げながら、最終的には見開き1ページをまとめてイメージ化できる状態を目指しましょう。
「そんなの無理……」と思うかもしれませんが、これまでのトレーニングで身につけた変換力とイメージ力によって、必ずできるようになります。
最終的には、一般的なビジネス書や実用書を10分程度で読み終えることも十分に可能です。焦らず、自分のペースで少しずつ読む範囲を広げていきましょう。
ステップ4:アウトプットトレーニング
右脳速読の最終ステップは、読んだ内容をアウトプットするトレーニングです。速読で読み取った内容について、アウトプットを通じて理解度を確認していきます。
具体的には、本の内容を紙にまとめる作業がメインになります(口頭で説明してもOK)。なぜ読んだ内容をわざわざ書き出すのかというと、アウトプットによって左脳が活性化するからです。
内容を論理立てて説明する作業は、言語脳と称される左脳を思い切り使います。だから、「速読を右脳・まとめを左脳」でおこなうと、脳全体の能力を底上げできるのです。
また、右脳で捉えたイメージ情報を左脳で整理すれば、記憶の定着度も大幅に向上します。毎回書き出すのは面倒かもしれませんが、目標とする読書スピードに到達するまでは、できるだけアウトプットをおこなってください。
できれば、まとめはパソコンではなく、手書きをオススメします。パソコンやタブレットでもよいのですが、手で書く行為自体に、脳を刺激する作用があるからです。
とはいえ、無理にきれいな文書を書く必要はありません。人に見せるためではなく、目的はあくまでも「自分の脳がバランスよく機能しているかどうか」の確認です。
速読のメリット

ここまでの話で、速読の大まかなしくみについて、ご理解いただけたと思います。あとは、実際に速読習得に向けて動き出すだけです。しかし、速読を学ぶ前に、まずは速読のメリットを、もう少し具体的に知りたいという人も多いでしょう。そこでこの章では、速読の主なメリットを6つほどお伝えしていきます。
本が速く読める
速読のもっとも大きなメリットは、いうまでもなく「本が速く読める」ことです。前述のとおり、一般的な速読では分速2,000文字前後、右脳速読なら1分間に1〜2万文字が平均的な読書スピードになります。
かりに分速2万文字なら、一般的なビジネス書を、5分もかからずに最後まで読めてしまいます。
趣味で小説を読みたいという人もいますが、小説にあまり速さは求めませんよね。多くの社会人は仕事や人生に役立つ知識を手に入れるために、本を読むことが多いはず。この場合は、読書スピードは本当に大きな武器になります。
現在は技術やスキルの変化が激しくなり、昔のようにひとつのスキルを武器に生きていくのが非常にむずかしい時代です。いくつになっても常に新しい知識を学び続ける必要があります。
そう考えると、短期間に大量の情報をインプットできる速読は、今もっとも必要とされるスキルのひとつだといえるでしょう。
◆速読で学力がアップする理由については、コチラの記事でお読みいただけます
情報の選択肢が増える
前述のとおり、速読を習得すれば、短時間で多くの情報処理が可能です。そうすると、今まであまり手をつけてこなかったジャンルの情報にも、広くアンテナを伸ばす余裕が出てきます。
これ、サラッと説明していますが、じつは非常に重要なポイントです。人間はどうしても自分の知っている範囲内で、ものごとを考えてしまいます。しかし世の中には、自分の知らない知識や情報のほうが圧倒的に多いものです。
もしかしたら、その知らない情報のなかに、最適な答えが存在するかもしれません。そういった新しい情報を素早く大量に仕入れる手段が、速読なのです。
残念ながら、普通の読書スピードだと、本を大量に読むのはなかなか大変でしょう。月に1冊も読書をしない人が60%以上もいるという文化庁のデータ※が、その事実を物語っています。
速読で大量に書籍が読めれば、自分のなかに新しい知見が広がり、その分正確で失敗の少ない判断が下せるようになります。そうやって構築された広い視野は、結果を求められるビジネスの世界を筆頭に、私たちへ多大な恩恵をもたらしてくれるでしょう。
読書スピード以外の能力も習得できる
これは右脳速読法に限定されますが、右脳を日常的に使うと、左脳も含めた脳全体が活性化します。その結果以下のような、速読以外の能力も連動して向上するわけです。
- 理解力
- 記憶力
- 判断力
- 動体視力
- 空間認識能力
瞬読の受講生のなかにはK-1選手もいらっしゃいますが、瞬読によって一瞬の判断力や全体を把握する能力が、確実にレベルアップしているとの感想をいただいています。
また意外なところでは、ビジネスコミュニケーションがうまくいくようになったという報告もありました。会う人の事前情報を速読で徹底的に読み込むようにしたところ、相手が好意を持ってくれて、人間関係がどんどんうまく回るようになったそうです。
こういった副次的に得る能力は、目を速く動かすだけでは得られない貴重なスキルといえます。
◆速読がスポーツに有効な理由については、コチラの記事でお読みいただけます
時間的ゆとり
速読を身につけると、日々の情報処理スピードが大きく変わります。たとえば、通常の2倍、あるいは3倍の速さで本や資料を読めるようになれば、リサーチにかかっていた時間を大幅に短縮できます。
必要な情報を効率よく集められれば、その分ほかの業務や活動に時間を回せるようになるのです。
忙しさに追われて自己投資の時間が取れない……そういった悩みを抱えるビジネスパーソンにとって、速読は時間管理の強い味方になります。空いた時間で資格の勉強をするのもよいでしょう。英語やプログラミングなど、新しいスキルに挑戦することだってできます。
もちろん、仕事だけでなくプライベートを充実させるのもOKです。家族との時間を増やしたり、趣味に没頭したりできれば、人生がより豊かになります。速読を上手に活用して、人生のレベルアップを図っていきましょう。
コミュニケーション力の向上
速読で情報や知識を大量に吸収できるようになると、コミュニケーション力も向上します。自分の知識が豊富になり、相手の話に対する理解力や共感力が高まり、相手との対話がスムーズに進みやすくなるからです。
なかでも、小説やコラムは、自分と異なる考え方や発想に触れる絶好の機会です。ビジネス書や実用書ばかりでなく、ぜひそういった本も読んでみてください。
また新しく得た幅広い分野の情報は、異なるバックグラウンドをもつ人たちとの交流に、非常に役立ちます。今までならまったく対応できなかった分野の話でも、自ら適切な話題を提供できるし、受け答えにストレスを感じることもないでしょう。
そうなれば、学校での友人・子どもの保護者とのお付き合い・ビジネスでの対人関係など、新しく人間関係を構築する際に、間違いなく大きなアドバンテージになるはずです。
◆読書とコミュニケーション力の関係については、コチラの記事でもお読みいただけます
自分に自信がつく
速読の副産物的なメリットとして、自分に自信がつくという面が挙げられます。速読というひとつのメソッドを習得し、普通では考えられないスピードで本が読めるようになった自分に、あなたはきっと大きな自信を感じているはずです。
もちろん、速読で得られる桁違いの情報量も、自信の源になってくれます。これまで知識不足で対応できなかったことにも、堂々と意見を述べ、求められれば的確なアドバイスもできるようになるからです。
はじめて会う人にも堂々と対応できるので、あなたを信頼してくれる人がどんどん増えていきます。豊富な知識と見識をベースにして、今後は学業や仕事でも、ますます結果を出せるようになっていくでしょう。
こういったプラスのスパイラルがいったん回り出せば、悪いことは弾き飛ばされて、よいできごとがびっくりするほど流れ込みはじめます。たかが速読かもしれませんが、人よりも速く大量に情報が吸収できるようになると、本当に自信がつくものですよ。
速読と他のスキルの相乗効果

速読ができるようになると、読書のスピードアップだけでなく、脳のさまざまな能力のレベルアップが期待できます。今回は、集中力や情報処理能力といった6つの能力をピックアップして、速読がもたらす影響について解説していきます。
速読と集中力
諸説ありますが、本当に集中できるのは15分、頑張って継続しても90分が限界といわれています。まだ精神的に幼い子どもは集中力を維持するのが困難なので、小学校の授業は45分に設定されているのです。
ところが、速読ができるようになると、集中できる時間が少しずつ長くなっていきます。それは一体なぜなのでしょうか。
速読をするには、集中力が必要です。瞬読の場合、1分間に数万文字読む人もいます。速読中、短時間に大量の文章を読むわけですから、当然ほかのことには意識が向きません。速読をしている間は、内容の理解に全力で集中しています。
私たちの生活には、SNSや動画、ゲームなど、集中力を阻害する要因が数多く存在します。いくら頑張って勉強していても、SNSの通知がピコンと鳴ったら、一瞬で集中力は吹っ飛んでしまうでしょう。
集中力を維持するのがむずかしい現代だからこそ、そういった誘惑を断ち切って集中する時間を確保する意識が必要です。速読は、私たちの集中力を取り戻す、よいきっかけになってくれます。
◆集中力を高める方法については、コチラの記事でお読みいただけます
速読と情報処理能力
速読は、私たちの情報処理能力にも、よい影響を与えてくれます。学校や会社内を見渡してみると、誰かひとりはビックリするほど頭の回転が速い人がいるものです。そういう人は、ほかの人が悩んでしまうことでも、パッと解決策を提示してきます。
大量に蓄積された知識のなかから、「今必要な情報はなにか」をすぐに判断して、素早くピックアップする。頭の回転が速いというのは、いうなれば「情報処理能力が非常に高い」ということです。
速読をマスターすると、情報処理能力が向上して、必要なときに必要な情報を素早く取り出せるようになります。
速読をする際には、最低でも1分間に2,000文字分の情報を処理しなければなりません。一般的な人の読書スピードは、分速500文字程度なので、4倍以上も速く情報を処理しているわけです。
日頃から速読で、情報の高速処理トレーニングをおこなっていれば、間違いなく情報処理能力は向上します。情報処理能力はもって生まれた才能ではなく、適切な負荷により磨かれる能力です。情報処理能力を高めたいなら、速読は非常に有効な手段になってくれるでしょう。
◆情報処理能力を高めるポイントについては、コチラの記事でお読みいただけます
速読と記憶力
速読によって、記憶力の向上にも大きな効果が期待できます。速読をする際には、短時間で大量の情報を読み取らなければなりません。そのためには、やはりある程度の集中力が必要です。漠然と本を読むより、集中して読む方が、当然記憶に残りやすくなります。
また速読をマスターすると、文章全体の流れや重要なポイントを素早く把握して、効率的に情報を整理できるようになってきます。インプットした情報をすべて覚えておくのは、現実的に不可能です。そのため重要なポイントだけを効率よくインプットできれば、記憶の定着度は確実によくなります。
なかでも、右脳を活用する瞬読の場合、情報をイメージとして理解します。単なる文字情報ではなく、映像として理解することで、記憶の定着度はさらに高まるでしょう。速読は、ただ「速く読む」だけでなく、「読んだ内容を忘れにくくするスキル」でもあるのです。
◆記憶力のしくみについては、コチラの記事でお読みいただけます
速読と判断力
速読は、判断力を鍛えるための有効なトレーニングでもあります。速読を実践するなかで、膨大な情報から必要な部分を素早く選び取る力が養われます。記憶の項目でも触れたように、読んだ情報をすべて覚えることはできません。
大量の文章を読み、そのなかから重要なポイントをピックアップする。この過程を繰り返すうちに、自然と必要な情報を選択する判断力が磨かれていくわけです。
そうやって判断力がレベルアップすると、とくにビジネスシーンで役立つ機会が多くなります。日々の業務に追われるビジネスパーソンには、最初から最後までじっくりと参考図書を読む時間がありません。
限られた時間で、必要な情報を見つけ出す力が求められます。だから、必要な情報をパッパッと拾い上げていく判断力が高いと、ビジネスシーンで非常に有利なのです。
◆判断力を鍛える方法については、コチラの記事でお読みいただけます
速読と問題解決力
問題解決能力も、速読によって向上する能力のひとつです。速読で問題解決能力が高まる理由には大きく以下の2点が考えられます。
- 解決の糸口となる知識が大量にストックされている
- 必要な情報を素早くリサーチできる
問題を解決するには、まず解決方法を見つけ出さなければなりません。普段から速読で大量の本を読んでいる人は、脳内にストックされた情報量が通常より圧倒的に多いと考えられます。そのため、「あっ、それなら◯◯をしてみたらどうだろうか……」と、解決の糸口を見つけやすいのです。
かりに、今ある知識では対応できなくても、速読ができれば、関連する資料やデータを迅速に確認できます。
さらに、速読の習慣化によって、物事を全体像から細部までバランスよく把握する力が身につきます。適切な解決策は、過不足ない情報が揃ってはじめて導き出せるものです。そういう意味でも、速読は問題解決能力のレベルアップに大きく役立ってくれるといえるでしょう。
速読と発想力
速読は、発想力を高めるための強力なツールです。速読ができるようになると、大量の情報を短時間で取り込めるようになります。
斬新で質のよい発想を生み出すには、まずベースとなる情報が必要です。いくら天才的なひらめきをもつ人でも、考える材料がなければよいアイデアは生み出せません。
しかし、速読をしない人が大量の本を読むのは、なかなか大変です。読むのが速い人でも、月に4〜5冊読むのが限界ではないでしょうか。速読ができれば、1日に1冊、あるいは数冊読むことも十分可能です。
さまざまなジャンルの本を多読すれば、異なる分野の知識を組み合わせて、まったく新しいアイデアが生まれるかもしれません。さらに右脳速読なら、日頃から右脳を使う機会が多いので、自然と発想力が磨かれます。
新しいプロジェクトや課題に取り組む機会の多い人は、ぜひ速読にチャレンジしてみてください。きっと、自分の発想力が広がっていくのを実感できるはずです。
◆発想力を鍛える方法については、コチラの記事でお読みいただけます
こんな人に速読はオススメ!

先ほど速読のメリットをお伝えしましたが、うまく活用すると本当に速読は人生に役立ってくれます。どういう人に速読がオススメなのか、具体的なシチュエーションを4つ挙げて紹介していきます。
急いで仕事に関する情報を調べる必要がある
日々ビジネスの第一線で働いていると、必ず即断即決を求められるケースに遭遇するはずです。その際、「いったん持ち帰ってじっくりと検討します」などと言えば、間違いなくビジネスチャンスを逃してしまいます。
純日本式なら、慎重さが美徳に受け止められることもありますが、グローバルなビジネスの場になればそうはいきません。とはいえ、どうしてもその場では判断のつかないこともあるでしょう。
そういった状況でも、あなたが速読をマスターしていれば、少しだけ時間をもらってすぐに必要な情報を確認できます。
これは、少々極端な例をお話ししましたが、現代のビジネスにスピード感が欠かせないのは間違いのないところです。普通の人がリサーチに3日かかるところを、1日で済ませられれば、その時間的アドバンテージが大きな利益をもたらしてくれるかもしれません。
そういったアドバンテージをつくるために、速読は本当に大きな武器になってくれるはずです。
試験の時間がいつも足りなくなる
試験の時間がいつも足りないという人には、速読をオススメします。理由は簡単。問題文を速く読むことで、余った時間を考える時間に回せるからです。
言うまでもなく、試験は時間との戦いです。ゆっくりと解けば簡単に解答できる問題も、厳しい時間制限があると焦って簡単に間違えてしまいます。
2023年度大学入学共通テストの国語を例に挙げると、古文や漢文を含めた問題文の総文字数は、約24,000文字です。これを通常の読み方と速読で、必要な時間を比較すると以下のようになります。
- 分速400文字の場合:60分
- 分速1,000文字の場合:24分
- 分速2,000文字の場合:12分
解答時間は全部で80分なので、普通に読んでいたら、解答に割ける時間はわずか20分しかありません。一方、分速2,000文字のペースで読めれば、解答に60分以上使えるし、見直しの時間も確保できます。
もちろん、いくら速読ができるといっても、普段よりはどうしてもゆっくりと読むようになるでしょう。それでもこの時間的余裕は、プレッシャーのかかる試験において、非常に大きな優位性をもたらしてくれるはずです。
◆速読と解答時間を増やすメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
読んだ内容がイマイチ頭に入ってこない
「ちゃんと読んでいるはずなのに、どうも内容が頭に入ってこない」読書をしていて、そんな風に感じたことがありませんか?
もし、読んだ内容の理解度が低いと感じているなら、右脳速読がオススメです。右脳速読は、読んだ内容をイメージとしてインプットするので、頭にスルッと入っていきます。
文字だけの専門書より、イラストやグラフを多様した入門書の方が、圧倒的に理解しやすいですよね。ビジュアルの助けを借りて、脳により強い刺激を与えているので、脳が情報を忘れにくいんです。
右脳速読は、こういった働きを頭のなかで自ら作り出す読書法だと考えると、理解しやすいのではないでしょうか。
もちろん、読解力をアップする方法は、速読だけではありません。多読や要約ノートの作成など、さまざまな方法を別記事で紹介しています。よかったら、そちらの記事もチェックしてもらえると嬉しいです。
◆読解力を高める方法については、コチラの記事でもお読みいただけます
スポーツやアートで結果を出したい
スポーツやアートに関しても、右脳速読が非常にオススメです。右脳速読をオススメするのには、大きくふたつの理由があります。
- 必要な情報を素早く入手できる
- 右脳速読で右脳が司る動体視力や空間認識能力が鍛えられる
スポーツやアートの分野で優れた結果を出すためには、技術や才能だけでなく、必要な情報のインプットが不可欠です。こまかい技術や練習方法といった理論をきちんと勉強しておかなければ、効率よいレベルアップは望めません。
今は書籍や動画で、情報がいくらでも手に入る時代です。しかし、あまりにも情報が多すぎて、そのぶん情報の選択がむずかしくなっています。速読はあなたに必要な正しい情報の取得に、大きく役立ってくれるはずです。
また、右脳速読をマスターすると、自然と右脳が得意とする能力も鍛えられます。スポーツやアートに必要な能力といえば、やはり動体視力と空間認識力でしょう。あと、意外かもしれませんが、直感力もスポーツやアートには欠かせない能力です。
「次、味方がこう動くのではないか」「ここに黄色を使えば絵が引き締まる」といった具合に、直感力がないとスポーツやアートはうまくいきません。
こういった能力を意図的に鍛えるのは非常に困難ですが、右脳速読を身につけると意図することなく自然とレベルアップしていきます。
◆右脳を活性化させる方法については、コチラの記事でお読みいただけます
速読の効率をアップする6つのポイント

速読をマスターすれば、たしかに読書スピードはアップします。しかし、読書に対する基本的な知識がないと、せっかくの速読も効果を発揮しきれません。この章では、速読の効率アップに関係する読書のポイントを6つ紹介します。
脳内音読のクセをなくす
視読でガンガン速読をしたいなら、とにかく脳内音読をやめることです。脳内音読は、今回紹介した視読の対局にある読み方だと思ってください。
音読をすると、読書スピードは著しく遅くなります。個人差はありますが、人の話す速度は、1分間におよそ500文字前後が平均です。対して、右脳速読なら、その20倍以上の速度で読書する人がたくさんいます。
音読を続ける限り、分速500文字よりも速く読めるようにはなりません。だから、なんとしてでも、音読のクセをやめなければならないのです。
ただ普通の人は、読書の際に、音読なんてしていませんよね。その代わり、頭のなかで文字を読んでいます。この脳内音読は、音読の意識がないぶん普通の音読よりもやっかいです。
脳内音読をやめるには、前述の右脳速読トレーニングをオススメします。読んだ内容を瞬時に映像化していくトレーニングを繰り返すうちに、1文字ずつ追いかける音読のクセは自然と消えていくでしょう。
◆黙読のメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
基本的な文章の構成を理解しておく
商業出版されている本は、多くの場合、ジャンルに適した構成パターンにもとづいて書かれています。もちろんすべての本が、こういった構成どおりなわけではありません。セオリーから外れた構成の本もたくさんあります。
それでも、本を速く読みたいなら、代表的な構成パターンを知っておくべきです。構成の知識があると、次の展開をある程度予測できます。次にどのような話がくるかがわかっていれば、途中で話を見失うこともなくなります。
もっとも有名な構成といえば、「起承転結」でしょうか。でも、この構成が使われるのは、小説くらいだと思います。ビジネス書など、一般的な実用書の場合、「序論・本論・結論」のような構成にもとづいて書かれることが多いです。
最近では、Web媒体の記事が書籍化されることも多く、結論を最初に示す「PREP法(プレップ法)」による文章もよくみかけます。別記事「6.文章構成の基本を知っておく」で紹介している「4.結論・理由・事例・まとめ」が、PREP法です。
基本的な文章構成については、ぜひ以下の記事をご参照ください。
目次で内容を予測する
本を読むのが苦手な人のほとんどは、目次をあまり読んでいません。これは本の理解度という観点からみると、非常にもったいない行為といえます。
目次は、はじめてその本を読む人のために、本の概要をまとめたものです。知らない土地をドライブするには、地図が不可欠。本が知らない土地だとすれば、目次は地図に相当します。
騙されたと思って、しっかりと目次に目を通してみてください。理解度が飛躍的にアップしますよ。
まえがきを読むと著者の主張が明確に
前述の目次と似た話になりますが、スムーズに読書を進めるためにも、まえがきにはぜひ目を通しておきたいですね。
まえがきを読まない人も多いですが、目次同様、非常にもったいないと思います。まえがきは、著者の本に対する想いや主張が直接読める貴重なページです。わずか数ページですぐに読めてしまうので、次回からはぜひまえがきを読んでみてください。
もちろん、なかにはあまり参考にならないまえがきもあるので、その場合はサラッと流して構いません。
また娯楽目的の小説と違い、実用書なら最初にあとがきを読んでしまうのも、ひとつの方法です。目次・まえがき・あとがきを事前に読んでおけば、話の流れを予測しやすくなり、読書のスピードアップにきっと大きく貢献してくれるでしょう。
読書後に要約メモを作成する
本を読んだら、章ごとに要約メモを書いてみるのをオススメします。
ただ本を読むだけでは流れてしまう思考が、文章にすることで明確になるからです。また手を動かす方がキーボード入力するよりもうまくまとめられるというデータ※もあります。
※参考:The pen may be mightier than the keyboard
私自身も読んだ内容を手書きにてアウトプットする過程で、思考が一段と明確になるのをはっきりと感じています。要約メモ作成は、理解度アップに超オススメですよ。
速読に集中できる環境をつくる
速読を効果的におこなうためには、集中できる環境を整えることが大切です。集中できる環境づくりのポイントは、以下の4点になります。
- 騒音対策
- 適切な明るさ
- 整理整頓
- スマートフォン対策
カフェのような環境を好む人もいますが、やはりできるだけ静かな場所の方が集中して速読に取り組めます。もしどうしても外部の音が気になる場合は、ノイズキャンセリングイヤホンを使うか、気持ちを落ち着けてくれる静かなBGMを流すのも効果的です。
照明も、集中力に大きく関係します。日本の照明は天井灯が多く、明るすぎて目が疲れやすいです。明るすぎず暗すぎない、目に優しい卓上ライトをメインで使うようにしてください。
また、作業スペースの整理整頓も非常に重要です。机の上が散らかっていると、どうしても気が散りやすくなるので、速読に必要ないものは見えない場所に片づけてしまいましょう。
同じ理由で、スマートフォンも別の場所にしまってください。スマートフォンが視界に入ると、一気に集中力がもっていかれてしまいます。速読の時間だけでもいいので、SNSやゲームの誘惑から意識を遠ざけましょう。
◆スマートフォン対策については、コチラの記事でもお読みいただけます
速読初心者Q&A

速読にまだ慣れていない初心者のうちは、わからないことがたくさんあるはずです。ここでは右脳速読法「瞬読」について、よく問い合わせを受ける質問にお答えしていきます。
読みやすいのはどのような本?
右脳速読に適しているのは、文字中心のシンプルな本です。わかりやすくビジュアル(写真・イラストなど)を多用した本は、とくに初心者のうちはオススメしていません。
写真やイラストが多い本はたしかに理解しやすいかもしれませんが、肝心の右脳で文字をイメージ化する作業がやりづらいのです。
またできれば、ページ数や文字数などに細心の配慮がされている、ベストセラーから挑戦するのがよいでしょう。ジャンルはビジネス書や実用書などが取り組みやすいと思います。
まったく知識のない本でも読めるの?
残念ながら、まったく知識のない本の速読はできません。知識のない人が、難解な医学書や工学書を読んでも、まったく意味がわからないでしょう。そういった本を速読しようとしても、それはムリというものです。
またそういう意味では、母国語ではない言語で書かれた本を速読するのも、かなりムリがあります。どうしても基礎知識がない分野の速読にチャレンジしたいのなら、少なくともひと通りの知識を勉強してからにしましょう。
速読は子どもでも問題ない?
子どもでも問題はありませんが、瞬読のトレーニングが受けられるのは、文字をある程度読めるようになる「小学校中学年」以上になってからです。それまでは、絵本や図鑑などを純粋に楽しむのがよいでしょう。
中学年以上になってトレーニングを開始したら、読む本は図書館のオススメ本などがいいと思います。オススメなだけあって、そういう本は文体も内容も非常に読みやすいです。
またいったん速読をはじめたら、今度は逆に、絵本や図鑑などビジュアルメインの本は避けてください。右脳によるイメージ化の妨げになります。
速読を習得するコツは?
速読は筋トレと同じような側面があります。瞬読ではわずか1〜3時間のトレーニングで結果の出ることも多いのですが、1回だけで止めてしまうのは少々もったいないです。
毎日少しずつ、できるだけ長期間トレーニングを続けたほうが、安定した速読スピードを期待できます。(もちろん、ムリに毎日トレーニングする必要はありません)
また適度な休憩も、トレーニングの効率には必要です。「15分やって5分休憩」をワンセットにして、30分・45分と時間を決めてやると、トレーニングにメリハリがつきます。
1分間にどれくらい読めるようになる?
瞬読で読めるスピードには、個人差があります。短いトレーニングで分速40万字というびっくりするような速度で読める人もいれば、2倍が限界という人もいるのが現実です。
ただ、これまでの実績をみる限りでは、まず分速1万文字を目標にするのが現実的だと思います。このレベルまでいけば、10分もかからずに1冊の本が読めるでしょう。
また1年間トレーニングを続けた受講生のじつに92%が、分速2万文字を達成しています。
トレーニングの時間が確保できるならば、2万文字を目標にしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は初心者が悩みがちな「速読のしくみ」や「速読のメリット」について、じっくりと解説してきました。
またはじめたばかりの人が疑問に思うであろうポイントにも、しっかりとお答えできたと思います。
右脳速読法「瞬読」について、もう少し詳しく知りたいと思われた方は、ぜひオンライン体験会にご参加ください。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読