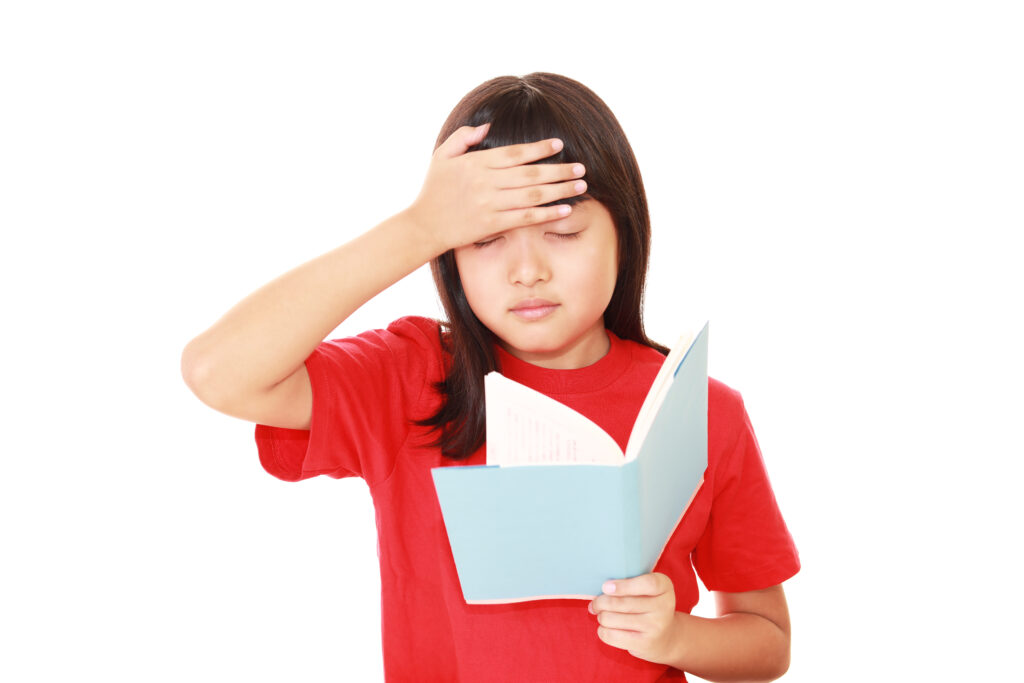記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
速いスピードで月に何冊も本を読んでいる人の話を聞くと、「自分だけおかしいのかな?」と不安になることはありませんか?じつは、読むスピードには個人差があり、少しくらい遅くてもとくに問題はありません。
とはいえ、多くの人が、「もっと速く読めたら仕事や勉強にも役立ちそう」と考えてしまうものです。この記事では、読むのが遅くなる理由とスピードアップを実現する方法について、わかりやすく紹介します。
目次
読書スピードに関する基本的な考え方

冒頭で述べたように、本を読む速さに正解はありません。大切なのは、自分に合ったペースで本と向き合い、そこからなにを得るかです。この章では、「読むのが遅い=悪いこと」ではないという前提のもと、読書に対する考え方を整理していきます
読む速さは人それぞれ違って当然
速く読める人もいれば、じっくり読むことで理解を深める人もいる。読むスピードには、個人差があって当たり前です。それなのに読書スピードを気にしすぎると、本来の目的である「内容を楽しむこと」や「学びを得ること」からズレてしまいます。
そもそも、読書は誰かと読書スピードを競うものではありません。結末が気になって最後から読んでしまう人もいますし、最初から一言一句漏らさずに読み込むのが好きな人もいます。
読み方にルールなどありませんから、読書スピードについても他人のことは一切気にせずに、自分に合ったペースで楽しめばいいのです。もちろん、速く読めるに越したことはないでしょう。読書スピードを上げる方法については、最後の章でご紹介します。
速さよりも「なにを得るか」が大事
読書で本当に大切なのは、読む速さではなく「読書から得る知識」です。いくら早く読み終えても、内容が頭に残らなければ意味がありません。
せっかく本を読むなら、なにかしら得るものが欲しいですよね。あくまでも私見にはなりますが、「心に残った一節がある」「明日から試してみたいアイデアが見つかった」という読者は、じっくりと読むタイプに多いように感じられます。
もちろん、読書スピードが速いからといって得るものがないわけではないし、読書スピードの速さにはメリットが数多く存在します。ですが、読書スピードの速さはあくまでもひとつのメリットであり、そこにこだわる必要はないのです。
無理に速さを追いかけるよりも、読み込みの深さに軸を置く読書スタイルがあっても、全然構いません。
目的に合わせて読み方は変わってくる
読書の目的によって、最適な読み方は自然と変わってきます。すべての本を同じスピード、同じ姿勢で読む必要はありません。
たとえば、小説を楽しみたいときは、情景や感情の描写をじっくり味わいながら読む「丁寧読み」が向いています。一方で、調べものや資料の確認が目的なら、必要な情報だけを拾い読みする「スキミング」や「スキャニング」が有効です。
速読のできる人なら、目的に関係なく、ザーッとすべての内容に目を通して、そこから必要な情報をピックアップするスタイルが効率的でしょう。
このように、目的を明確にすれば、「この本はじっくり読む」「この本は流し読みでOK」と判断できるようになり、効率的に読書ができます。つまり、「読むスピードが遅いか速いか」ではなく、「今の目的に合った読み方ができているか」の方が大切なのです。
読書はもっと自由でいい。読書スピードにとらわれず、目的に応じて臨機応変に読み方をスイッチできるようになりたいですね。
なぜ読むのが遅くなってしまうのか?

読書スピードが遅い人には、やはりそれなりの理由が存在します。自分がどのような理由で読むのが遅いのか、それがわかれば解決のヒントが見えてくるはずです。今回は、代表的な原因を4つ紹介します。どれが自分に当てはまるか、チェックしてみてください。
内容をすべて覚えようとしている
本を読むのが遅くなる大きな原因のひとつに、「すべての内容を完璧に覚えようとしてしまう」ことがあります。真面目な人ほど、ひとつひとつの言葉や例えを丁寧に追い、1ページごとに完璧な理解を求めてしまいがちです。
でも、本には重要な部分とそうでない部分があり、すべてを記憶する必要はありません。たとえばビジネス書であれば、自分の仕事に活かせるヒントや考え方だけ拾えれば十分です。
小説はエンターテイメントが目的なので、じっくり全文に目を通す人も多いでしょう。それでも、読んだ箇所をすべて覚えておく必要はないです。物語の展開や印象的な場面だけ頭に入っていれば、それで十分役目を果たしてくれます。
そもそも、頭のなかだけで読んだ内容を全部覚えておくことなど不可能です。忘れている箇所があれば、必要に応じて読み返せばいいだけ。「忘れても全然OK」と割り切り、まずは読み進めることに注力しましょう。
読書に慣れておらず途中で集中力が切れてしまう
読書が遅い人には、ほぼ全員「読書に慣れていない」という特徴があります。読書に慣れていないと集中力が長く続かず、何度も同じところを読み返したり、途中でスマホに手が伸びたりしてしまうのです。
たとえば普段あまり本を読まない人が、いきなり分厚いビジネス書や難解な小説を読もうとしたら、おそらく10分ほどで嫌になってしまうでしょう。これは能力の問題ではなく、単に「読書の持久力」があるかないかだけの話です。
読書に慣れていないうちは、短いエッセイやライトな実用書など、取り組みやすい本を選ぶと集中力も持続しやすくなります。読書も筋トレと同じです。続けていけば自然と集中力もつき、スピードも上がっていきます。
焦らずに、まずは「読み切る」体験を少しずつ積み重ねていきましょう。
◆集中力の磨き方については、コチラの記事でお読みいただけます
語彙力や背景知識が不足している
読書スピードが遅くなる原因のひとつが、語彙力や背景知識の不足です。知らない言葉や初めて聞く概念が多いと、内容を理解するのに時間がかかり、読書のテンポが極端に落ちてしまいます。
たとえば、経済や医療、ITなどの専門的な本を読むとき、関連する基本知識がないと、いちいち用語の意味を調べなくてはなりません。場合によっては、調べた内容がなかなか理解できないこともあり、当然読書スピードは極端に下がってしまいます。
とはいえ、これは決して悪いことではなく、いうなれば「知識の幅を広げている証拠」です。慣れてくれば、知っている知識や語彙が増えてくるので、少しずつ読むスピードは速くなります。
知らない言葉や知識に出会ったら、それは成長のチャンスです。語彙や知識の不足を恐れず、調べながらでも読み続ける姿勢が、このあとの読書スピードアップにもつながっていきます。
スマホやSNSに意識をもっていかれる
通知音やタイムラインの更新など、スマホは常に私たちの注意を奪う恐ろしい存在です。本を読んでいる途中にスマホやSNSが気になってしまうと、集中が途切れてしまい、結果として読むのが遅くなります。
たとえば、2〜3ページ読んだ頃に、LINEの通知が来てチェック。ついでにXやInstagramも開いてしまい、気づいたら1時間が経過していた……そういった経験は誰にでもあるはずです。こうした中断が積み重なると、読書への没入感が薄れ、スピードも内容の理解も極端に落ちてしまいます。
対策としては、まず通知オフは大前提です。そのうえで、読書中はスマホを手の届かない場所にしまってください。電源を切っていても、スマホの気配を感じるだけで集中力は途切れてしまうという研究データ※もあります。だから、電源を切ってポケットにしまうのもNGです。
読書スピードの遅さに悩んでいるなら、読書中は電源を切って、カバンなどのなかにしまっておくことをオススメします。
※参考: The Mere Presence of Your Smartphone Reduces Brain Power, Study Shows – UT Austin News
◆デジタルデトックスについては、コチラの記事でもお読みいただけます
読むスピードを上げるための具体的な方法
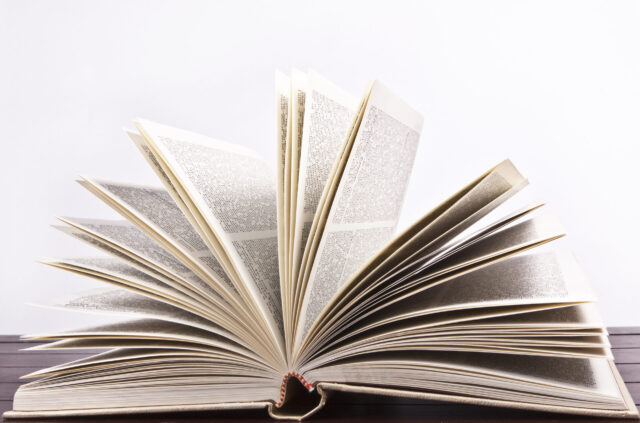
自分の読書スピードがなぜ遅いのか、その遅い理由がわかったところで、最後に読むスピードを上げるための具体的な方法を5つ紹介します。
読む前に「目的」と「注目すべきポイント」を決めておく
読み始める前に「目的」と「注目すべきポイント」を決めておくと、読書スピードは大きくアップします。理由はシンプルで、ゴールが明確になっていれば、関係のない情報に振り回されずに済むからです。
当たり前ですが、すべてを丁寧に読もうとすると時間がかかります。しかし、「この本から◯◯について学びたい」と決めておけば、必要な部分だけに集中できます。
たとえば、「会議を効率化するアイデアを得る」のが目的だとしましょう。効率化に関するビジネス書のなかには、会議以外のさまざまな状況に対する内容が書かれているはずです。なかには、会議には使えないアイデアも書かれているかもしれません。
そういった箇所は軽く流して、会議の効率化に直結する情報だけ読めば、読書に必要な時間を大幅にカットできます。このように読むべき箇所が明確になれば、そこにだけ集中すればよいので、スピードも理解力も自然と上がっていきます。
◆目次チェックのメリットについては、コチラの記事でお読みいただけます
スキミングとスキャニングを意識する
読書スピードの改善には、「スキミング」と「スキャニング」の意識的な使い分けが効果を発揮してくれます。スキミングとは全体をざっと読み流して内容の大枠をつかむ方法、スキャニングは特定の情報だけを拾い読みする方法です。
この2つを上手に活用すれば、最初から最後まで丁寧に読まなくても、要点だけを効率よく把握できます。
たとえば、ビジネス記事を読むときに、「まず見出しで全体像をスキミングし、興味のあるデータや具体例だけをスキャニングで読む」というスタイルなら、読む時間を大幅に短縮できます。
もちろん、熟読が必要な場面もあるでしょう。ですが、「すべて読む」ことにこだわらず、「必要なところだけ読む」意識をもつことで、読書はぐんとスムーズになります。
◆スキミングとスキャニングについては、コチラの記事でもお読みいただけます
脳内音読をやめる
読書スピードを上げたいなら、まずは脳内での「音読」を減らすことから始めてみましょう。私たちは文章を読むとき、無意識に頭のなかで声に出して読んでいます。じつは、この「脳内音読」とでもいうべき習慣が、スピードの妨げになっているのです。
脳内音読の速度は人が話す速さとほぼ同じ、1分あたり約400文字程度といわれています。それでは、どうしても読むのが遅くなってしまいます。
そこでぜひ取り入れたいのが、速読で用いられる「視読」と呼ばれる読み方です。視読とは、文字をひとつずつ読むのではなく、単語やフレーズをかたまりとして読む方法です。視読ができるようになれば、分速2,000文字以上も夢ではありません。
もちろん、いきなり音読をゼロにするのはむずかしいでしょう。ですが、「なるべく広い視野で文章を読む」と意識するだけでも、効果があります。少しずつ視読を取り入れながら、読書スピードを高めていきましょう。
◆視読の身につけ方については、コチラの記事でお読みいただけます
まずは「1冊読む」経験を重ねる
読むスピードを上げたいなら、まずは「1冊を読み切る経験」を重ねることを強く意識してください。読むのが遅いと感じている人の多くは、途中で挫折してしまうことが多く、読了の達成感を味わえていないケースがほとんどです。
しかし、どんなに時間がかかっても1冊を読み通せば、「最後まで読めた」という自信がつき、自然と次の読書がラクになります。
たとえば200ページの本を1日10ページずつ読めば、3週間足らずで1冊読了できます。たしかにゆっくりかもしれませんが、それでも途中でやめなければ、必ず最後まで読み終えられるはずです。
読むスピードは、経験とともに自然に上がっていくものです。まずは1冊、自分の力で読み切ること。それがすべての第一歩になります。
読書が苦手な人は「聴く読書」も活用しよう
活字を読むのが苦手と感じる人は、「聴く読書(オーディオブック)」を取り入れてみるのもひとつの方法です。どうしても本を読むのに集中できない人でも、耳からならスッと内容が入ってくるケースが意外にたくさんあります。
またオーディオブックは、通勤や家事の合間のように、目が使えない場面でも読書の時間を確保できるのが大きなメリットです。
Audibleやaudiobook.jpなどのオーディオブックサービスでは、ベストセラーやビジネス書、文学作品まで幅広くラインナップされています。プロのナレーターによる朗読は聞きやすく、内容への理解もしっかり深まります。
読書が苦手、あるいは読書のためにまとまった時間が取れないなら、「聴いて理解する」スタイルを選んでもまったく問題ありません。「読む」ことにこだわらず、オーディオブックの活用を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
◆オーディオブックのメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
まとめ
本を読むスピードに悩んでいる人は多いですが、大切なのは速さではなく、自分に合った読み方で「なにを得るか」です。読書スピードを改善したい人は、読むのが遅くなる原因を知り、少しずつ改善に取り組めば、無理なくスピードも上がっていきます。
読書は競争ではありません。焦らず、自分のペースで楽しむことを大切にしましょう。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読