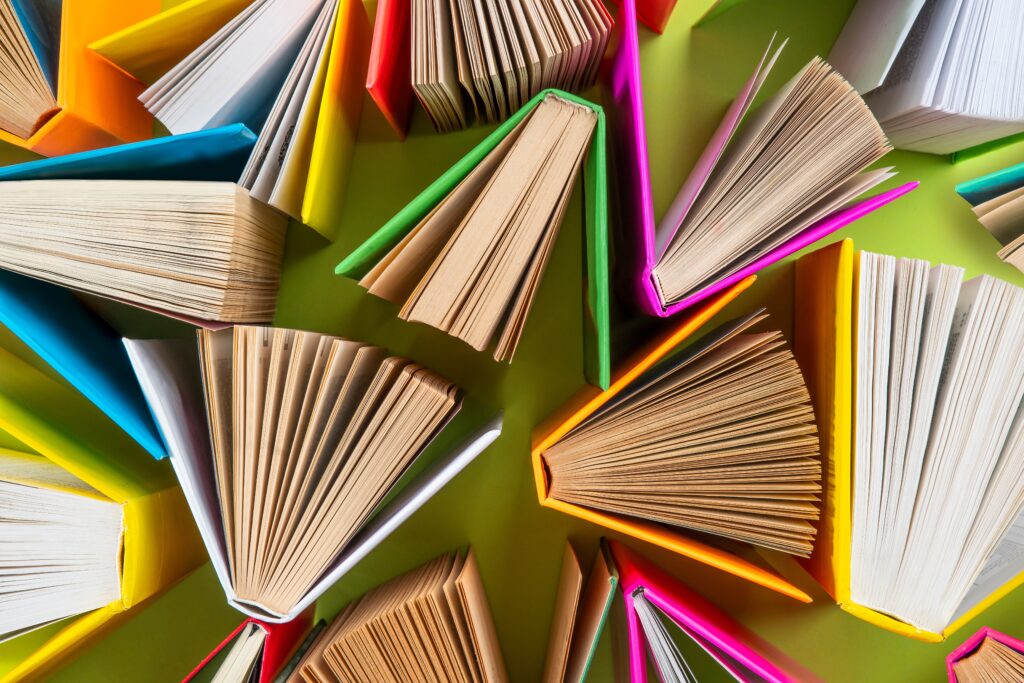記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
速読法に興味はあるけれど、「本当に理解できるの?」「どんな種類があるの?」と疑問を持つ人は多いはずです。近年は、資格試験や仕事の効率化のために速読を取り入れる人が増え、さまざまな手法が注目されています。
本記事では、速読法の基本からメリット、代表的な種類、さらに初心者が抱きやすい疑問までをわかりやすく解説します。
目次
そもそも速読法とはなにか?

速読法とは、文章を通常よりも速く読み進めながら、内容の理解もしっかりと保つための読書技術です。単純にページを速くめくるのではなく、視野を広げて1回に読む量を増やし、頭のなかの音読を減らして、情報処理のクオリティを高めていきます。
一般的な読書スピードは1分間に約400〜800文字ですが、速読ができるようになると、最低でも2倍、速い人なら5倍以上の速さで読めるようになります。
なぜ速読が注目されているかというと、現代社会では膨大な情報を効率よく扱う力が求められているからです。たとえば資格試験の学習では数百ページのテキストを繰り返し読む必要があり、ビジネスの現場でも資料やメールを短時間で理解することが求められます。
速読法を身につければ、必要な情報を素早く整理し、時間を有効に活用できます。そのことに気づいた人たちが速読法を習い、仕事や勉強、あらゆる面で速読法を活用しているのです。
◆速読の仕組みについては、コチラの記事でもお読みいただけます
速読法を身につけるメリット

速読法を習得する最大のメリットは、限られた時間で効率よく情報を吸収できる点にあります。現代は仕事でも学習でも大量の文字に触れる機会が多く、処理に時間がかかるとほかの作業に支障が出てしまいます。
速読法を身につければ、読書や資料確認にかかる時間を短縮でき、その分を復習や実践への振り分けが可能です。
たとえば資格試験の勉強では、同じテキストを繰り返し読む回数を増やせるため、理解度や記憶定着が高まります。また、ビジネスの現場では大量の資料やメールを短時間で処理でき、判断のスピードも上がります。
つまり速読法は、読む時間の節約にとどまらず、学びや仕事の成果を生み出す大きな武器になってくれるわけです。
またほかにも、集中力の向上、コミュニケーション力の向上、自分に自信がつくといった副産物的なメリットもあります。
速読の主な種類

一口に速読といっても、そのアプローチはさまざまで、特徴や得意とする場面が異なります。この章では代表的な速読法の種類を取り上げ、それぞれの概要を説明していきます。
単語や文章をまとめて読む「視読」
すべての速読法の基本となるのが、「視読(しどく)」と呼ばれる読み方です。視読とは、単語をひとつずつ読むのではなく、数語から1行をひとかたまりに読んでいく手法のこと。
前述の通り、一般的な読書スピードは1分間に約400〜800文字になります。これまでと同じく、単語をひとつずつじっくり読んでいたら、読書スピードもそのままです。そこで、視野を拡大するトレーニングをおこない、いっぺんに読める言葉の範囲をどんどん広げていきます。
たとえば「今日は天気がいいので散歩に出かけた」という文章を読むとき、「今日は/天気が/いいので/散歩に/出かけた」ではなく、「今日は天気がいいので」「散歩に出かけた」と複数の単語をまとめて読んでいくのです。
さらに、速読に慣れてくると、「今日は天気がいいので散歩に出かけた」と、1回に文章を丸ごと読めるようになります。(もっと慣れてくるとページ丸ごと読める人もいます)
このように、視読は速読法の基本であり、どの速読法でも必ず学ぶ重要なテクニックなのです。
◆視読の身につけ方については、コチラの記事でお読みいただけます
大まかな内容を素早く把握「飛ばし読み」
「飛ばし読み」とは、文章をすべて丁寧に読むのではなく、要点となる部分だけを拾い読みして内容を大まかにつかむ方法です。この読み方は、限られた時間で全体像を把握したいときに非常に有効です。
じつは、本のなかには本筋に直結しない説明や例え話も多く含まれており、すべての文章が等しく重要なわけではありません。そこで、本筋とは関係ない箇所を省いていくと、情報処理のスピードを一気に高められます。
ビジネス書や実用書の場合、見出しや太字部分、段落の冒頭と末尾だけを確認するだけで、大まかな論旨を理解できるケースがじつは非常に多いです。構成のしっかりしている本なら、目次だけで主要な論点がわかってしまうことも少なくありません。
もちろん小説のように細部まで味わう読書には向きませんが、学習や仕事で必要なポイントを素早く押さえるには、非常に効果的な読書法といえます。
写真を撮るように読む「フォトリーディング」
フォトリーディングは、ページ全体をカメラで撮影するように一瞬で視覚に取り込み、潜在意識に情報を蓄積していく速読法です。通常の読書が文字を順番に追って理解していくのに対し、フォトリーディングではページ全体を「イメージ」として記憶するのが特徴です。
この方法では、内容を最初から細部まで理解するのではなく、必要なときに情報を呼び起こすことを前提にしています。たとえば参考書を一度フォトリーディングで取り込み、その後に重要なポイントを確認しながら流し読みし、最終的にマインドマップなどに整理する、というのが基本的な流れです。
準備や整理の手間はかかるものの、うまく活用すれば膨大な情報を短時間で処理できる可能性を秘めた手法だといえるでしょう。
目を酷使せず誰でも速読が可能に | 右脳速読法「瞬読」とは
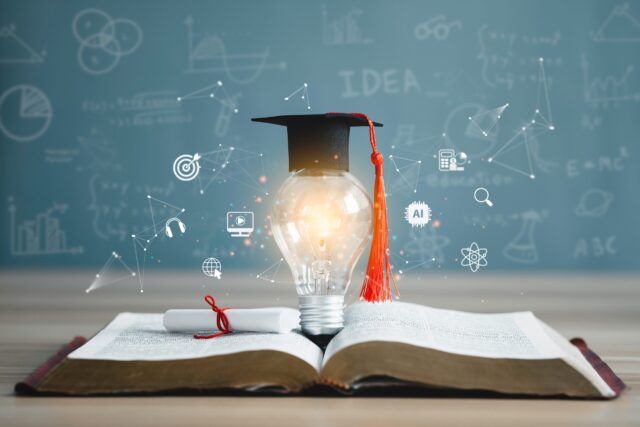
これまでの速読法とは根本的にアプローチが異なる、右脳速読法「瞬読」について、概要をご紹介します。
瞬読とは、右脳のイメージ処理能力を活用し、文字を映像として頭に取り込むことで速読を実現する方法です。従来の「目を早く動かす速読」とは異なり、目の負担を抑えながら理解と記憶を両立できるのが特長です。
人間の右脳はもともと写真や映像のように情報を一度に処理する力を持っており、瞬読ではその特性を活かして文章を「イメージ化」して理解します。
たとえば「会議室で新商品の企画を発表する場面」を読んだとき、ただ文字を追うのではなく、スーツ姿の発表者やスクリーンに映る資料、聞き入る上司の表情を思い浮かべれば、理解が格段に深まります。
右脳速読では、このイメージ化の力を意識的に活用するため、理解度と記憶の定着度を同時に伸ばせるのが強みです。右脳速読の詳細については、Zoom体験会で確認ができます。効率よく速読を習得したい方は、ぜひいちど確認してみることをオススメします。
◆右脳速読法については、コチラの記事でもお読みいただけます
速読法なんでもQ&A

速読法を学びたいと思っても、不安があるとなかなか一歩を踏み出せないものです。そこで最後に、よくある疑問点についてお答えしていきます。ただ、右脳速読法だけに該当する内容もあるので、その点はご了承ください。
速読は誰でもできる?
結論からいうと、速読は特別な才能がなくても誰でも習得できます。なぜなら、速読は一部の人にしか備わっていない特殊能力ではなく、目や脳の使い方を工夫することで誰でも身につけられる技術だからです。
実際に多くの速読法では、「一度に見る文字数を増やす」「頭のなかで音読せずに読む」といった練習を通じて、段階的に上達していきます。最初はふたつの単語をまとめて読むことすらできなくても、慣れてくれば、最終的にページ丸ごと1〜2秒で読み取ることも可能です。
もちろん、人によって習得のスピードは異なります。ですが、メソッドに沿ってしっかりとトレーニングをおこなえば、誰でも必ず速読はできるようになります。
視力は関係あるの?
速読の習得において、視力の良し悪しは大きな障害にはなりません。なぜなら、速読は視野拡大と効率のよい情報処理を核としたスキルだからです。視力よりも、むしろ文章を頭のなかで音読する習慣や、視野の狭さの方が速読の妨げになります。
視力が悪くメガネやコンタクトで視力を矯正している人でも、通常の読書ができるなら、速読トレーニングにはまったく支障ありません。
もちろん、目が疲れやすいときはこまめに休憩を入れたり、適切な明るさで読書したりする工夫が必要です。しかし、それは通常の読書でも同じこと。速読に必要なのは視力ではなく、読み方の工夫と脳の使い方を変える意識ということをぜひ頭に入れておいてください。
何歳でも速読はできる?
速読は年齢に関係なく、誰でも習得が可能です。実際に右脳速読法「瞬読」では、下は小学生から上は70代まで幅広い年代の受講生が練習に励み、成果を上げています。
若い世代は、頭が非常に柔らかく、新しい速読法をスポンジのように吸収していく人が多いです。一方で年齢を重ねた世代は、若干柔軟性に劣るものの、経験や語彙力がある分、理解度が非常に深いというメリットがあります。
速読は、あくまでも読み方の技術です。きちんとしたトレーニングにより誰でも年齢関係なく上達できます。ただし、読めない文字が多い小学校低学年の受講は、基本的にご遠慮いただいています。(受講目安は小学4年生以上)
速く読んでもきちんと理解できるの?
速読を正しい方法で実践すれば、理解力は落ちません。むしろ情報の整理がスムーズになり、内容が頭に入りやすくなるケースも多いのです。
たとえば「今日は天気がよくて、家族で公園に行った」という文章も、一語ずつ読むより「今日は天気がよくて、家族で公園に行った」という文章を丸ごと捉えた方が、イメージが浮かびやすく理解度もアップします。
もちろん練習不足の段階では、重要なキーワードを気にするあまり、読み飛ばしてしまうこともあるかもしれません。ですが、繰り返し取り組むうちに、重要なポイントを押さえつつ、全体像をしっかりと理解できるようになってきます。
習得までにどれくらいかかる?
右脳速読法「瞬読」では、体験レッスンを受けただけでも99%以上の人が読書スピードを2倍以上に伸ばしています。基本的な目線の動かし方や右脳によるイメージ化ができるだけでも、ほとんどの人が速く読める感覚を味わえるはずです。
ただし、それ以上のスピードを安定して維持し、理解度を落とさずに読めるようになるには、一定の練習期間が必要になります。個人差はありますが、3〜6か月ほど継続して取り組むと、独力で速読を使いこなせるようになる方が多いようです。
もし、より効率的に学びたいというなら、90日間集中プログラムをオススメします。専属トレーナーの個別サポートもあり、短期間で一気に右脳速読をマスターできます。
どんな種類の本でも速読できる?
ごく一般的な本であれば、基本的にどのようなジャンルでも速読は可能です。ビジネス書や実用書、学習参考書など、文字が中心となる書籍は速読の対象として適しています。
ただし、注意点もあります。未知の専門知識が多く出てくる専門書の場合、基礎知識が不足しているとゆっくり読んでも内容を正しく理解できません。そういった場合は、文字だけいくら速く読めても理解度が追いつかず、速読の意味がなくなってしまいます。
また、漫画のようにビジュアル要素が多い本は、絵にイメージ化を邪魔されてしまう可能性が高いです。小説のような娯楽性の高い本も、速読には向いていません。
そもそも想像力を働かせてじっくり楽しみながら読むための本なので、高速で情報をインプットしていく速読とは基本的にコンセプトが異なります。少なくとも学習段階では、題材として選ばない方が無難です。
独学でも速読を習得できる?
結論からいえば、速読は独学でも習得可能です。実際に右脳速読法「瞬読」では、自宅で学べるように専用のドリル本をご用意しています。こういった書籍を使えば、基礎的なトレーニングであれば独学でも十分に取り組めます。
なぜなら、「視野を広げる」「音読を減らす」「文章をイメージで捉える」といったスキルを自主学習で学べるように、専用のドリル本は設計されているからです。
とはいえ、効率よく上達するには、やはり指導を受けた方が近道なのも事実です。レッスンなら、自己流では気づきにくいクセや誤りを、専門の講師からのアドバイスで早めに修正できます。
独学から速読に入った人も、できれば体験会を受講して、右脳速読のメソッドを実際に受けてみることをオススメします。
まとめ
速読法は、単に本を速く読むためのテクニックではなく、効率よく知識を吸収し、仕事や学習の成果を高めるための実践的なスキルです。速読法を学ぼうと思ったら、視読や飛ばし読み、フォトリーディング、右脳速読など多様な選択肢が存在します。
今回紹介したQ&Aを参考に、自分に合った方法を選び、無理なく自分の生活に取り入れていただければと思います。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読