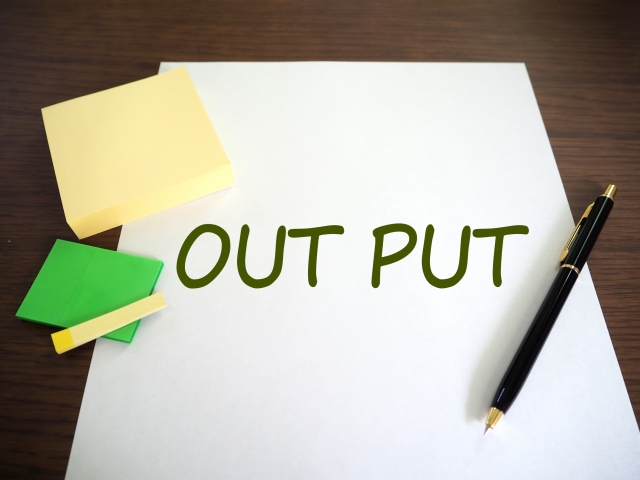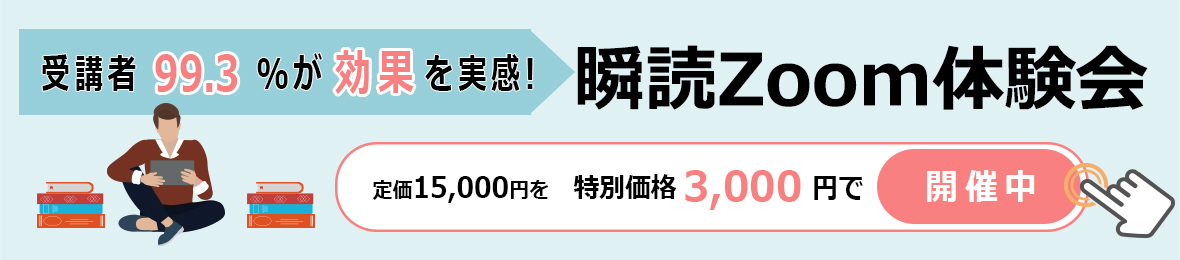記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
せっかく読書をしても内容をすぐに忘れてしまう、とお悩みのかたは非常に多いです。たしかに忙しい合間を縫って本を読んだのに、「アレっ、なに書いてあったっけ?」となれば、がっかりする気持ちもよくわかります。
でも安心してください。「反復」と「アウトプット」を読書にうまく組み込めば、覚えておける量は間違いなくアップするはずです。
今回の記事では、アウトプットに焦点を当て、アウトプットが有効な理由や効果的なアウトプット方法について詳しく解説していきます。読んだ内容をできるだけ忘れたくない、インプットした知識を実践していきたいという人は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
読書後のアウトプットが有益な3つの理由

まずは「どうして読書にアウトプットがオススメなのか」、その理由をしっかりと押さえてしまいましょう。アウトプットが必要な理由は、以下の3つにまとめられます。
- 理解度が深くなるから
- 知識が定着しやすくなるから
- 重要なポイントを的確に読み取る力がつくから
それではひとつずつ解説していきます。
理解度が深くなるから
読んだ内容を深く理解したいなら、アウトプットを取り入れるのが一番の近道です。なぜなら、人は情報を「使おう」とするときに、初めて本当の意味で理解しようとするからです。
たとえば、本の要点をノートにまとめたり、人に説明しようとしたりする場面では、内容を自分の頭で再構成する必要があります。このプロセスが脳をフルに働かせ、ただ読むだけでは得られない深い理解をもたらしてくれるわけです。
反対に読みっぱなしのままだと、「なんとなくわかった気がする」程度で終わってしまい、なかなか記憶に定着しません。だからこそ、アウトプットを通して学んだことを整理し直すことが、重要になってくるのです。
知識が定着しやすくなるから
アウトプットを意識すると、読書で得た知識がしっかりと頭に残りやすくなります。読んだ直後の情報は一時的に「短期記憶」として保存されます。ですが、そのまま放置しているとせっかく読んだ内容もほとんど記憶に残りません。
試しに読んだ本の内容を、翌日なにも見ずに思い返してみてください。おそらく、本の内容の90%近くは、すでにおぼろげな記憶になってしまっているはずです。
脳は、いったんインプットした情報を何度も思い出したり使ったりすることで、「これは重要な情報だ」と判断します。そうなってはじめて、その情報は長期記憶へと移行していくわけです。
知識を定着させるためには、読むだけで終わらせず、積極的にアウトプットをすることが何より大切なのです。
◆記憶のメカニズムについては、コチラの記事でもお読みいただけます
重要なポイントを的確に読み取る力がつくから
アウトプットを意識して読書をすると、「重要なポイントを見抜く力」が自然と身についてきます。たとえば、誰かに読んだ内容を伝えようと思えば、重要なポイントだけを簡潔に伝えないとなかなか理解してもらえません。
だから、「どの箇所を説明すれば本の内容がきちんと伝わるだろうか」と意識して本を読むようになり、その結果として重要なポイントを見抜く力が磨かれるわけです。もちろん、最初は、思うように重要な箇所を見つけられないかもしれません。
しかし、何度も経験を重ねるうちに、「どこが要点なのか」「どの部分は軽く読み流していいのか」が、徐々に判断できるようになります。重要なポイントを素早く読み取れるようになれば、読書にかける時間も大幅に短縮できます。
効果的な読書後のアウトプット方法
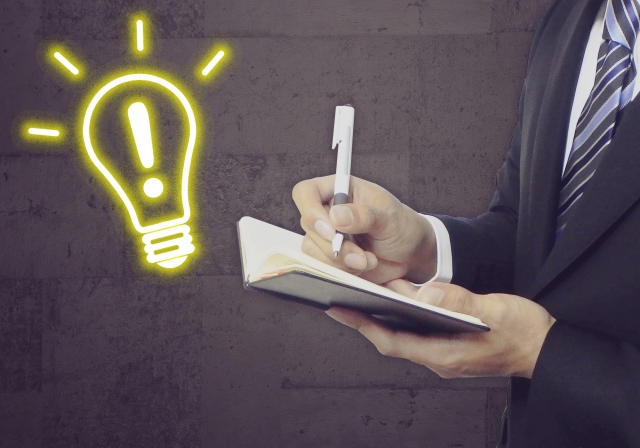
アウトプットのメリットがわかったところで、今度は効果的なアウトプット方法について解説していきます。ここで解説するポイントは以下の4点です。
- 読んだ直後に「3行まとめ」を書く
- 読書で学んだ内容を人に説明する
- SNSや書評サイトを利用する
- インプットした知識はすぐに実践する
ひとつずつ解説します。
読んだ直後に「3行まとめ」を書く
読書の内容をしっかり記憶に定着させたいなら、読んだ直後に「3行まとめ」を書いてみるのはどうでしょうか。読んだ内容を自分の言葉で要約すると、脳内で情報が整理され、理解度と記憶定着の両方が高まります。
まとめ方に決まりはありませんが、「要点」「感想」「実践」の3つの視点から考えるとまとめやすいです。
たとえばビジネス書なら、まず要点を書き出します。次に、その要点に関する「〇〇という理論が参考になった」といった感想と、実践にどう活かしていくかを書き出せば、まとめとしては十分でしょう。
ただ読むだけだと、時間の経過とともにどうしても記憶は薄れていくものです。その点、重要なポイントを簡潔にまとめておけば、頭に入りやすいぶんだけ長期間記憶に残ってくれます。読みっぱなしを防ぐためにも、この3行アウトプットをぜひ習慣にしてみてください。
◆読書ノートのつくり方については、コチラの記事でお読みいただけます
読書で学んだ内容を人に説明する
読書の効果を最大限に引き出すには、学んだ内容を誰かに説明してみるのがオススメです。他人に読んだ内容をしっかりと伝えるには、話の流れやポイントを自分なりに整理しなければならないので、理解度が格段に深くなります。
とはいえ、正式な発表会ではないので、友人や同僚に「この本、こんなことが書いてあってね」と話す程度で十分です。完璧に説明できなくても構いません。
むしろ失敗点が多いほど、「理解度の浅い点はどこだったのか」「もっと上手に説明するにはどうすればいいのか」という気づきが生まれます。
可能であれば、質問に回答したり、感想を教えてもらったりしましょう。第三者の客観的なフィードバックは、自分の読書方法をレベルアップするための大きなヒントになってくれるはずです。
◆読書後のアウトプットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
SNSや書評サイトを利用する
読書のアウトプットを習慣化したいなら、SNSや書評サイトの活用をオススメします。というのも、他人に見られる場所で感想や学びを発信すると、「どう伝えればわかりやすいか」といった点を意識するようになり、自然と要点を整理する力がついてくるからです。
たとえば、X(旧Twitter)でひと言感想を投稿したり、noteに読書記録を残したりするだけでも、立派なアウトプットになります。また、読書メーターのような書評サイトでは、同じ本を読んだ人の感想をチェックできるので、自分の視点を広げるよいきっかけになってくれるでしょう。
こうした外部ツールをうまく活用できれば、読書が「個人的な行為」から「誰かとつながる体験」へと変わっていきます。具体的なSNSや書評サイトの使い方については、次のセクションで詳しく紹介します。
インプットした知識はすぐに実践する
読書で得た知識は、できるだけ早く実践に移すことをオススメします。なぜなら、行動に移すと知識が「体験」へと変わり、記憶にも深く刻まれるからです。
たとえば時間管理の本を読んだなら、読んだその日のうちに、ひとつだけでもすぐに試してみましょう。「1日の最初に重要なタスクをやる」「ToDoを3つだけに絞る」など、一つひとつは小さなことでも、実行すればその小さな学びが自分の経験として蓄積されていきます。
すべてを完璧に実践する必要はありません。まずは、今の仕事や生活に当てはまるものから少しずつ取り入れるのがコツです。うまくいったら、また次の内容に取り組み、できることをコツコツと増やしていきましょう。
このように、本を読んで終わりにするのではなく、本から得た知識を実際に体験して知恵に変えていくのが読書の本当の醍醐味です。ぜひ、今日から本から得た知識の実践を意識してみてください。
アウトプットにオススメのSNS

3行まとめを書いたり読書で学んだ内容を人に説明したりするのは、非常に有効なアウトプットです。しかし、慣れてくると、そういった方法だけでは物足りなくなってしまう人も少なくありません。
そういう場合は、前述の通り、SNSや書評サイトの活用をオススメします。ここでは、代表的なプラットフォームごとに、その特徴とポイントを紹介していきます。
X(旧Twitter)
SNSで初めてアウトプットをおこなうのであれば、オススメはなんといってもXでしょう。Xには原則140文字の文字制限があるので、いきなり長文を書くのに抵抗がある人でも、比較的簡単にアウトプットができるはずです。
ただし逆をいえば、140文字しか文字数がないので、なにを書けばいいのか悩む人も出てくるかもしれません。そういうときは、「#名刺代わりの小説10選」「#読書垢」といったハッシュタグをつけて、オススメの小説紹介などからスタートするのがオススメです。
Xには、あなたの情報発信を気に入った人がフォローしてくれたり、気に入ったツイートを相手のXで紹介してくれたりというおもしろさがあります。もちろんほかの人が書いた記事を、リツイート(他人の記事を自分のタイムラインで紹介)することも可能です。
おもしろいツイートをしている人がいたら、まずは積極的に絡んでみてはいかがでしょうか。
TwitterとInstagramはどちらもハッシュタグと画像を使って投稿できますが、Instagramは文字制限がないので、その気になればかなりこまかいレビューも可能です。
またInstagramの人気ハッシュタグになると、「#読書記録」160万件以上、「#読書好きと繋がりたい」6.8万件のように、びっくりするような投稿数になります。
そして元々の特徴として、Instagramは「インスタ映え」という言葉があるくらい、画像投稿がメインのSNSです。画像で独特の世界観を演出できれば、数百人・数千人単位の人に読んでもらえる可能性も出てきます。
もしInstagramでアウトプットをするなら、文章だけでなく、本の見せかたなどにも気を使ってみるとおもしろいかもしれませんね。
note
今非常に注目されている媒体に、「note」があります。noteは厳密にいうと、SNSというよりはブログに近い媒体ですが、Instagramのように画像や動画をメインにした投稿もできます。
もし長文でのアウトプットが苦手なのであれば、Twitterのように140文字程度の短いつぶやきを発信してもOKです。さらに文章も苦手というならば、とりあえず音声だけの投稿もできます。
ようするにnoteなら、ほかのどの媒体よりも自由に投稿できるのです。本格的なブログはWordPressなどの知識も必要ですが、noteならWordやメモ帳に書く感覚で、初心者でもすぐにアウトプットができます。
ちなみにnoteの記事は、有料版として1記事単位あるいは月額単位で、販売も可能です。読書のアウトプットの段階ではあまり関係ないかもしれませんが、いずれ自分のもつノウハウ記事などを書いて販売してみるのも楽しそうですよね。
本格的にアウトプットするなら書評サイトがオススメ

SNSの場合、読書に特別興味がない人も偶然見にくるかもしれませんが、書評サイトになると、基本的に「読書が大好きな人」しか参加しません。当然ながら、レビューを読む側の感性もそれだけ鋭くなってきます。
そういった目の肥えた参加者は、気にいったレビューがあると「いいね」をつけてくれたり、コメントを書いてくれたりします。もし自分のアウトプットをしっかりと読んでもらいたいのならば、書評サイトに投稿してみるとよいでしょう。
有名な書評サイトはそれこそたくさんありますが、今回はとくにオススメの3サイトをご紹介します。
読書メーター

※参考:読書メーター: 読んだ本を記録して、新しい本に出会おう
数ある書評サイトのなかでもとくにSNS機能が充実していて、お気に入りのレビュワーと交流がしやすいのは、読書メーターの大きな魅力といえます。
現段階でサイト内コミュニティは2,400以上あり、もっとも人数の多い「もっと読書友達がほしいよ!!の会」には、なんと6,400人近くのメンバーが参加しているそうです。ここなら、いろいろな意見をもった人から、的確なフィードバックがもらえるかもしれませんね。
以下に読書メーターの主な特徴をまとめておきますので、参考にしてください。
・ほかの参加者とコミュニケーションが図りやすい
・読んだ本を自動的にグラフ化してくれる機能がある
・これまでに読んだ総読書冊数や読書ページ数も自動でカウントしてくれる
ブクログ

ブクログも前述の読書メーターと同じように、自分の読書を本棚形式で管理したり、ほかの人の本棚を覗いたりも自由にできます。
ただ読書メーターと違い、あまり他者との交流機能が充実していないため、あくまでも相互にレビューを読むだけと割り切ったほうがよいでしょう。あまり大げさにせず、淡々とアウトプットしたいなら、ブクログがぴったりかもしれませんね。
・本棚のデザインがオシャレで、満足感が高い
・カテゴリやハッシュタグで、仕分けができる
・テーマに応じたオススメセットリストは、新しい本の開拓に便利
本が好き!

※参考:本が好き!
読者メーターと同じように、参加者同士のコミュニティ機能がとても充実している書評サイトです。個人的に、「本当に本の好きな人が集まる書評サイト」という感じが1番するサイトかもしれません。
このサイトは独特な仕掛けがたくさんあって、まず目を引くのが、レビュアーのランク分け制度でしょう。ランクは4級から1級まであり、さらに最高ランク「免許皆伝」になると、献本がたくさん受けられるようになります。
献本も「本が好き!」独自のシステムで、簡単にいえば、出版社からプロモーションとしてタダで本がもらえる制度のことです。もちろん受けた献本については、必ずレビューを書かなくてはなりませんが、これは本好きには非常にありがたいシステムですよね。
また5chに似たコミュニティページは、本好きのトークが飛び交っていて、非常に楽しい空間となっています。楽しみながらアウトプットしたい人には、「本が好き!」オススメですよ。
・コミュニティ機能がとても充実している
・ユニークな制度がある(ランク分け・献本など)
・旬な情報がすぐに手に入る
・ほかの人の本棚から、気に入った本を見つけやすい
また番外編として、Amazonレビューに感想や書評を書いてみるのも、個人的にはとてもオススメできるアウトプット方法だと考えています。
なぜならSNSや書評サイトのように、読書履歴などの情報が残らないので、気軽にアウトプットできるからです。とくに近年、Amazonのレビューを参考にして購入を決定する人も増えているので、レビューを書くのにも張り合いがあると思います。
いずれにしても、外部の媒体を使ってアウトプットすると、大きなフィードバックが得られるはずです。まずはどれでもよいので、ぜひ積極的に利用してみてください。
読書のアウトプットを効果的におこなうポイント
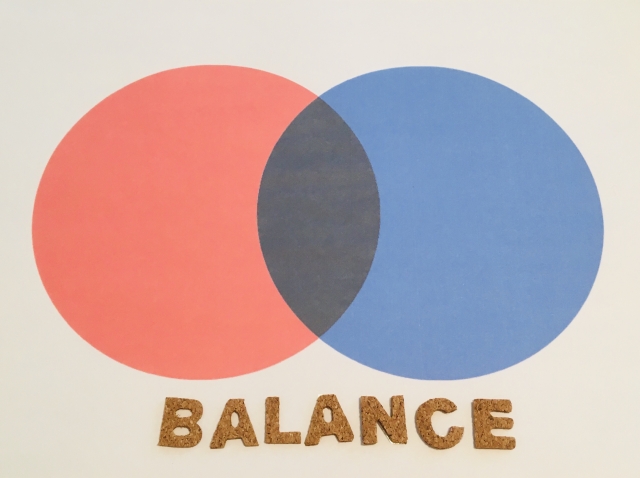
ここまでお伝えした読書のアウトプットを効果的におこなうために、最後に4つのポイントを解説していきます。
インプットとアウトプットをバランスよくおこなう
読書を学びにつなげるには、インプットとアウトプットのバランスが非常に重要です。知識をただ詰め込んでも、しばらく経てばほとんど忘れてしまい、使える情報として記憶に定着してくれません。
だから、ここまで何回もお伝えしたように、積極的なアウトプットが大切になってくるわけです。たとえば本を1冊読んだあとに、印象に残ったフレーズを手帳にメモしたり、家族や同僚に話してみたりするだけでも、頭のなかにその知識がしっかりと根づいてくれます。
一方で、肝心の読書をおろそかにして、アウトプットに偏ると、新しい知識が得られずに成長が頭打ちになることも考えられます。
できるだけ読書量を増やしつつ、読書から得た知識はしっかりと実践で身につけていく。このインプットとアウトプットのバランスが崩れると、読書の効果は半減してしまいます。読書を通して学びを深めるには、ぜひインプットとアウトプットの両輪を意識するようにしてください。
◆インプットとアウトプットのバランスについては、コチラの記事でもお読みいただけます
時間をムダにしないインプットのコツとは
読書の効果を最大化するには、「読む本を選ぶ能力」が欠かせません。残念なことに、世の中にはあまり質のよくない本も数多く出版されているのが現実です。そういった情報の質が低い本に時間を費やしてしまうと、有益な情報を得る貴重な時間を失ってしまいます。
有益な本を選ぶ方法としては、読者評価が高く何度も増刷されている本、信頼性のある著者の本を優先的に選べば、大きな失敗はほとんど防げるでしょう。とはいえ、いかに有名な著者の本だとしても、読み進めるのが苦痛に感じる本は、無理せず途中で手放す勇気も必要です。
また、「本を最初から最後まですべて読まなければいけない」という固定観念も、効率のよいインプットの大敵です。学びたい目的が明確なら、その目的について書かれている箇所だけを読めば目的は達成できます。
コスパという点を軸に考えれば、欲しい情報が手に入ったら、無理にほかの項目を読む必要はありません。もったいない気はしますが、読まなかった部分は、また時間のあるときにゆっくり読めばよいのです。
限られた時間をムダにしないためにも、常に効率のよいインプットを意識するようにしましょう。
手書きによるアウトプットのメリットとは
最近では、手書きではなく、パソコンやスマホで文字を入力する人が非常に多いです。しかし、読書後のアウトプットには、デジタルでのインプットではなく、「手書き」をオススメします。
なぜなら、手で書くという行為は脳の複数の領域を同時に刺激し、記憶の定着や深い理解を手助けしてくれるからです。
当然デジタル入力に比べて、時間はかかるでしょう。ですが、その分じっくり考えるクセがつくので、結果的にインプットした情報がしっかりと記憶に定着してくれます。また手書きには、「あとで見返したときに書いたときの感情や状況を思い出しやすい」というメリットもあります。
アウトプットの手段に正解はありませんが、「記憶に残したい」「思考を整理したい」と感じたときは、ぜひ手書きでのアウトプットも試してみてください。
同ジャンルの本を数冊読み比べる
理解を深めて効率よくアウトプットするには、同じジャンルの本を複数冊まとめて読むのが効果的です。似たテーマの本を連続して読むと、共通点や差異がなんとなくわかってくるので、押さえておくべき基礎的なポイントをしっかりとキャッチできます。
数冊読み比べて、共通して書かれている内容は、本当に重要なポイントです。誰にとっても必要な情報ということですから、そういう大事な情報はメモを取り、しっかりと理解するようにしましょう。
一方、同じ題材について書かれた本でも、著者によって結構内容が変わってくることもあります。場合によっては、まったく正反対の主張が書かれていることもあるので、同ジャンル本の読み比べは必ずやっておくべきです。
とくに新しい分野に挑戦するときには、わからない知識が多く、こういった判断がつかないので注意が必要です。
◆同ジャンルの本を複数冊読むメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます
まとめ
実際のところ、読書のあとにアウトプットをする人はそれほど多くありません。単純に面倒くさいのもあるし、アウトプットの有効性を知らないというのも大きな理由です。
当記事を読んだあなたは、すでにアウトプットの重要性をしっかりと理解しています。今回ご紹介した効果的なアウトプットの方法を参考にして、ぜひなんらかのアウトプットに取り組んでみてください。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読