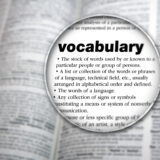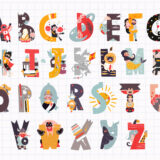記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
読書は脳によい刺激を与えてくれるとよく耳にしますが、読書が脳に与える影響について明確な情報をもっている人は案外少ないものです。
もし本当に読書が脳によい影響を与えてくれるなら、もっともっと本を読みたいと思いませんか?
今回の記事では、読書が脳にもたらすメリットやその理由、また脳への影響を高める読書のコツなどをご紹介していきます。
目次
読書が脳にもたらすメリット10選

まずは、読書が脳にもたらすメリットをきちんと理解しておきましょう。読書のメリットはそれこそたくさんありますが、今回は10個ほどピックアップして紹介していきます。
◆読書量を増やす最適な手段速読については、コチラの記事でお読みいただけます
知らなかった知識が身につく
読書をすれば、今まで知らなかった知識や考えかたが身につきます。仕事でどうしてもわからないことがあっても、関連する本を読めば、その解決策が簡単にみつかるかもしれません。
当たり前の話ですけど、よく考えてみればわずか1,000〜2,000円程度の出費で知らないことがわかるというのは、とてもすごいことですよね。
とくに新型コロナウイルスの影響で、直接人と接する機会が減っていますから、本から得られる情報はますます貴重になってきます。
とはいえ、少しネットを検索すればさまざまな情報が溢れているなか、どうして本が有益なのでしょうか。それは、その利便性と信頼性にあります。
ネットに散らばっている情報は断片的なものが多く、体系立ててまとめた情報を入手するのは、案外むずかしいし手間もかかります。また、ネットでは基本的に誰でも情報発信ができるので、その情報に対する信頼性の問題も見逃せません。
その点本なら、必要な情報がコンパクトにまとめられており、最低限の内容は出版社がある程度保証してくれていると考えられます。
◆読書と知識の関係については、コチラの記事でお読みいただけます
今よりも広い視野で考えられるようになる
読書は、他人の考え方を知る最高のチャンスです。試しに興味のある分野の本を、何冊か読んでみてください。おそらく、今までの自分では考えもつかなかった新しい視野が、自分のなかに芽生えはじめているはずです。
普段の生活では、よほど仲のいい友人でもない限り、その人の考え方をじっくりと聞く機会などほとんどないでしょう。ましてや、なんらかの突出した実績をもつ成功者の考え方に触れることなど、特別のコネでもなければあり得ないことです。
ところが本ならば、そういった人たちの考え方や方法論などが、簡単に手に入ります。しかも前述のとおり、一般的な実用書であれば、わずか2,000円足らずの出費しか必要ありません。そう考えると、読書がいかにコスパに優れた情報収集法であるかが、わかりますよね。
なお、もしこれから特定の分野に関する本を読む予定ならば、異なる著者の本を最低でも5冊は読んでみてください。同じ専門家でもまったく真逆の提言をしていることも多く、両方の意見を知ることで、より幅広い考え方が身につきます。
批判的思考能力の強化
読書には、批判的思考を強化してくれる働きがあります。批判的思考、すなわち情報の真偽を見極める力は、情報過多の現代において、非常に重要なポイントです。
インターネットの普及にともない、入手できる情報量が飛躍的に増加しました。なにかわからないことがあると、キーワードを打ち込んで検索すれば、ほとんどの答えがみつかる時代です。
しかし、あまりにも情報量が多すぎて、正しい情報とウソの情報を区別しにくくなっています。情報不足ではなく、情報の選択が現代社会の大きな問題点になっているのです。
そこで重要になってくるのが、読書です。読書は批判的思考を鍛えるよい機会をもたらしてくれます。最近は動画での情報収集が好まれる傾向にありますが、動画は情報がサーッと流れてしまい、検証がやりにくい媒体です。
その点読書なら、ゆっくりと情報を確認しながら読めます。「なにかおかしい」「違う可能性もあるのではないか?」と、引っかかる点がみつかれば、何度も読み返して簡単に検証ができます。
世の中に出回っている情報の多くは、その人の立場や利害関係が組み込まれているケースが非常に多いです。そういった情報を鵜呑みにせず、正しい情報を活用していくためにも、ぜひ読書で批判的思考を身につけましょう。
◆批判的思考については、コチラの記事でもお読みいただけます
新しいアイデアが生まれる
仕事で使える新しいアイデアがなにかないか。社会人なら、一度はそんな風に思ったことがあるでしょう。しかし、いつも同じ生活・行動をしていたら、斬新なアイデアは決して生まれません。
とはいえ、いつも新しい場所に出向き、新しい価値観に触れるなど、なかなかできるものではないですよね。そこで、役立つのが読書です。
なんといっても、本には私たちの知らない情報や価値観が、ふんだんに書かれています。そういった未知の情報から受けた数々の刺激は、きっとあなたに新しいアイデアを生み出すきっかけをつくってくれるはずです。
語彙が増え読解力が向上する
読書には、語彙力増強の役割があります。赤ちゃんの頃は、親の話す言葉を何回も聞いて、少しずつ言葉を覚えていきました。しかしある程度の年齢になり文字が読めるようになると、子どもは自分のペースで本を読み、知らない言葉をどんどん覚えていきます。
本のよいところは、友達と話す言葉とは違う複雑な表現が、数多く使われている点です。たとえば、単に成功したという表現と「試行錯誤した結果ようやく成功した」という表現では、含まれているニュアンスがかなり違います。
語彙力の高い人は、試行錯誤という言葉から、何回も繰り返してようやく成功を掴み取った努力のイメージを感じ取ります。しかし、そもそも試行錯誤という言葉を知らなければ、そういったニュアンスの違いは理解できません。
若者がよく使う「ヤバい」という言葉に代表されるように、私たちは使い慣れている言葉でできるだけ対応しようという傾向が強いです。
「ヤバい」を凄いという意味で使うなら、じつは「素晴らしい」「驚異的だ」「見事だ」のようにさまざまな表現があり、それぞれ少しずつニュアンスが異なります。こういったバリエーション豊かな語彙力を習得できるのが、読書の大きなメリットなのです。
共感力や想像力が高まる
人と関わりながら生きていくなかで、きちんとコミュニケーションが取れるかどうかは、非常に重要なポイントです。自分のことしか考えられず、相手がどういう気持でいるのかを想像できない人は、やはり人からもそうやって扱われてしまうでしょう。
読書は、読む人の共感する力や想像力を鍛えてくれます。とくに小説やエッセイには、そういった効果が強いですね。
なんといっても、対面での会話と違い、本には人の表情や話し方といったビジュアルからの情報がありません。
その代わり「あー、わかるわかる」「どうしてそうなるかな……」など、書かれた内容に自分の想像や感情の入り込む余地があるので、自然と共感力や想像力が鍛えられるわけです。
また、登場人物が誰かと話している情景を読むたびに、自分のなかに「表現方法のストック」ができてきます。「なるほど、こういう伝え方もあるのか」という気づきが、コミュニケーションに、きっとよい影響を与えてくれるでしょう。
◆読書と共感力の関係については、コチラの記事でお読みいただけます
集中力が鍛えられる
読書は、私たちの集中力を鍛えてくれます。読書が集中力を鍛えてくれる理由は、大きく以下の3点です。
- 基本的に文章以外の情報がないから
- 文章には想像が介入する余地があるから
- 考えながら読めるから
前述のとおり、最近は読書よりも動画を好む人が増えています。視覚と聴覚両方から情報が入ってくるし、ひとつの動画が短く、気軽に見られるのが人気の理由です。しかし、気軽に見られるというのは、途中で簡単にやめられるという意味でもあります。
その点読書には、ある程度集中力が必要です。文字しか情報源がないので、しっかりと意識して文章を読んでいかなければなりません。
さらに、文章には想像の介入する余地があります。たとえば、子どもは、小説を読むことが多いでしょう。好奇心旺盛な子どもは、普段の生活とはまったく異なる小説の世界観に引き込まれていきます。(ハリーポッターをみればわかりますよね)
しかも途中で立ち止まり、「どうしてこうなるのだろう?」「ほかに方法はないのか?」と考えながら読むことで、より理解力と集中力が高まります。
コミュニケーション力がアップする
「共感力や想像力が高まる」でもお話ししたように、読書で身につけた共感力や想像力は、コミュニケーション力を大きく改善してくれます。また語彙力が豊富な人は、適切な言葉を選択できるので、無用な誤解を生むケースがほとんどありません。
最近SNS上では、自分の意図する内容と異なる受け取り方をされてしまい、トラブルに発展するケースが非常に増えています。対面で話をしていれば表情や話し方でカバーできることも、文章(しかも短文)でのやり取りになると、誤解を解く機会すらないことが多いです。
こういったコミュニケーションの行き違いを防止するためにも、やはり読書の習慣化は必須だと思います。文部科学省の資料※を調べてみると、「読書をすることが多い子供ほど、コミュニケーションスキルや礼儀・マナースキルが高い傾向にある」という調査結果が報告されていました。
ただし読書習慣は、成長してから急に身につけようと思っても、正直なかなか大変です。図書館などを気軽に利用できる小学生のうちから、ぜひ積極的に読書をするように心がけてください。
※参考:文部科学省生涯学習政策局青少年教育課 子供の読書活動に関する現状と論点
◆SNS上でのコミュニケーションについては、コチラの記事でお読みいただけます
ストレスが解消される
自分の好きな本を読むと、ワクワクして気持ちが落ち着いてきますよね。自分の好きな作者の本を読み、その世界観にどっぷり浸かっていると、スーッとストレスが消えていくのがわかります。
また読書の癒し効果は、本の内容だけが関わっているわけではありません。本を読む場所や時間帯なども、大きく関係してきます。人のあまりいない静かなカフェで、ゆっくりとコーヒーを飲みながら好きな本を読む。本好きにとっては、まさに至福のひとときでしょう。
映画やドラマをみるのもよいですが、文字の奥に隠された自分だけが感じる想像の世界に浸ってみるのも、オススメですよ。
認知症予防効果が期待できる
認知症の予防効果が期待できるのも、読書の大きなメリットのひとつです。認知症に対する読書の効果については、すでに数多くの論文が存在しています。ここでは、2つの研究結果を紹介しておきましょう。
まず紹介するのは、アメリカラッシュ大学Robert Wilson教授による、医学誌「Neurology」の論文※1です。この論文のなかで、「読書のような認知活動をした高齢者は、アルツハイマー病の発症を約5年ほど遅らせる可能性がある」と述べられています。
またCambridge University Pressの「International Psychogeriatrics」に掲載された、台湾人に対する調査※2でも、読書の認知症予防効果が明言されています。この調査は、64歳以上の台湾人1,962名に対して、最長14年間も追跡したものです。
私たちは年を取ってから読書をしてもムダだと考えがちですが、そういった閉塞感を打ち消してくれる貴重なデータだと思います。
なお、読書が有効なのは、あくまでも認知症の予防です。認知症を治療してくれる効果はまた別の話ですから、そのへんは誤解のないようにしてください。
※参考1:Cognitive Activity and Onset Age of Incident Alzheimer Disease Dementia | Neurology
読書が脳によい影響を与える4つの理由

読書が脳に与える好影響を知っていただいたところで、この章では読書がどうして脳によい影響を与えてくれるのか、その理由を4点解説していきます。
文字からイメージする過程で想像力や共感力が鍛えられる
前述のとおり読書を大量におこなうと、文字からイメージする過程において、想像力や共感力が大いに鍛えられていきます。
表情や声のトーンなど、相手の感情を推し量る材料が極端に少ないため、自分の想像力で補おうとする習慣が自然と身につくわけです。
簡単に書いていますが、この「相手の気持ちを想像できる」というのは、非常に大きなポイントなんですよ。
というのも、近年では対面での会話よりも、TwitterやFacebookのようなSNSでの文字を使ったコミュニケーションが激増してきました。もちろん、写真や動画などが一緒に投稿されたりもしますが、やはり文字がコミュニケーションの中心であることに変わりはありません。
こういった文字中心のコミュニケーションでは、自分の意図しない方向に誤解されたり、相手の何気ない言葉に傷ついたりということが、頻繁に発生しがちです。
あとから、お互いに気持ちのすり合わせができればまだいいのですが、最悪の場合、誤解したままケンカ別れになってしまうこともあり得ます。これは、大きなストレスですよね。
読書によって鍛えられた想像力や共感力には、こういった文字によるコミュニケーションの弊害を軽減してくれる働きがあります。
脳細胞のつながりが強化されて記憶力などが向上
読書をすると、必ずなにかしらの新しい発見があるものです。じつはこのとき感じる「おっ!なるほど」という刺激が、脳細胞のつながりを強化して、記憶力が向上すると考えられています。
なかでも、気に入った本を何回も読み返す行為は強い刺激を脳に与え、より長期間の記憶を可能にしてくれます。今聞いた電話番号は忘れてしまっても、いつもかけている電話番号は忘れませんよね。まさに、これと同じ状態が起きているわけです。
この脳細胞の働きについては、別記事でも紹介していますので、よかったらそちらの記事も読んでみてください。
◆記憶のメカニズムについては、コチラの記事でお読みいただけます
知識と語彙が蓄積され、子どもの言語能力が飛躍的に促進
読書は、子どもの脳の成長に対して重要な鍵を握っています。当たり前ですが、生まれたばかりの赤ちゃんはなにも話せないし、相手の話す意味も理解できません。
そうした赤ちゃんが成長とともに言葉を不自由なく操れるようになるのは、生活のなかで大量のインプットを繰り返し、脳に知識と言葉をストックしていくからです。そのインプットの方法として、読書は非常に適しています。
本当に子どもが小さいときは、会話によるインプットが主流です。サイレンを鳴らしながら走っていく白黒の車をみたときに、母親が「あっ、パトカーだね。どこいくんだろうね〜」と根気よく語りかけてくれるから、赤ちゃんはパトカーを認識できるのです。
しかし、会話によるインプットは、どうしても量的に限界があります。そこで、文字が少し読めるようになった子どもは、本から知らない言葉や知識を覚えはじめます。
そうなれば、インプット量が激増するため、脳内に蓄積される知識と語彙は、加速度的に増えていくでしょう。このように読書は、子どもの言語能力の促進に、とても役立っているのです。
◆語彙力を伸ばす最高の方法「右脳速読」については、コチラの記事でお読みいただけます
さまざまな認知機能が総合的に刺激を受ける
ここまで、読書による効果を想像力や記憶力などを例に紹介してきました。しかし、読書は想像力だけ、あるいは記憶力だけによい影響をもたらすわけではありません。
読書は複数の認知機能に肯定的な影響を及ぼし、それぞれが複雑に絡み合って私たちの日常生活を支えてくれるのです。そこで、主要な認知機能が読書によってどのように強化されるか、簡単に解説していきます。
- 言語理解力:読書を通じて、新しい単語や表現に触れる機会が激増します。そのため語彙や表現力が磨き上げられて、文章の奥深い部分にまで意識が向くようになっていくのです。
- 集中力:おもしろい本に出会うと、時間を忘れて読みふけってしまうものです。このように読書は、周囲の気が散る要素から意識を切り離すよい訓練になります。
- 記憶力:名作と呼ばれる小説は、記憶力の強化にも役立ちます。奇想天外なストーリー、登場人物の複雑な関係性などを頭に入れながら読み進めていくため、短期記憶と長期記憶の両方が自然と鍛えられます。
- 想像力:イラストや図表などが内容を補足してくれる場合もありますが、本に書かれている情報の90%以上は文字です。そのため、読んだ内容を頭のなかで映像に変換してあげなければなりません。この文章のイメージ化を繰り返すうちに、想像力が豊かになってきます。
上記はあくまでも一例です。これら以外にも、共感力や判断力など、じつにさまざまな認知機能が向上します。
心の健康を支える読書の力

読書の効能のひとつに、メンタルケアがあります。効果的に読書をすれば、弱ったメンタルが大きく回復するかもしれません。今回は、心の健康を支える読書の力について、5つの観点から解説していきます。
リラクゼーション:読書がもたらす心の平穏
読書は心の平穏をもたらす、最適な手段になり得ます。本好きなら、読んでいる本に夢中になり、気づいたら朝になっていたという経験をしたことがあるでしょう。物語に没頭する間に、私たちは現実のストレスや忙しさから一時的に離れられるのです。
ミネソタ大学のサイト※には、読書は心拍数を下げ、筋肉の緊張を和らげてくれるので、体がリラックスすると書かれています。読書は、音楽を聴く・温かいお茶を飲むといった他のリラックス方法よりも、より効果的でより早く効果が出るそうです。
最初は、読書を継続するのはなかなか大変かもしれません。でも続けるうちに、「あー、面白かった!今度はあの本を読んでみよう」という気持ちになれたら、もうこっちのもの。まずは1日30分を目標に、読書に取り組んでみてください。
※参考:Reading for Stress Relief | Taking Charge of Your Health & Wellbeing
不安を和らげる:物語による気分の向上
読書は、心の不安を軽減し、気分を向上させる効果的な手段です。前述のリラクゼーションとも共通する話ですが、物語のなかに没頭すると、現実世界のトラブルや問題ごとから距離を置けます。
もちろん、読書による効果は一時的なものかもしれません。しかし、常に不安を感じていると心が参ってしまうでしょう。読書の時間だけでも、不安や悩みから解放されれば、心に余裕が生まれてきます。
疲弊しているときでも、お笑いを見たら元気になりますよね。同様に、好きな本を読めば、気分が上向いて、ストレスに立ち向かおうという気持ちになるものです。
2009年におこなわれたサセックス大学の研究※では、読書はストレスを最大68%軽減すると発表されています。心が疲れたとき、心が不安でいっぱいなとき、ぜひ好きな本を手にとってください。
※参考:Why It Pays to Read | National Endowment for the Arts
◆読書のリラクゼーション効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
エモーショナル・インテリジェンス:他者理解に対する影響
エモーショナル・インテリジェンスとは、自身の感情コントロールや他者の理解に必要な能力を指します。日本では、よく「EQ(心の知能指数)」と訳されているようです。
EQ 心の知能指数と聞けば、「あー、本のタイトルにもなっていたよね」という人も多いのではないでしょうか。
読書はエモーショナル・インテリジェンス、とくに他者理解の能力向上に役立ちます。オススメは、小説です。当たり前ですが、小説は文字情報がほぼ100%を占めます。そのため、キャラクターの考え方や感情を想像して、じっくり考える余地があります。
もちろん、共感するときもあれば、どうしても納得できないこともあるでしょう。でも、自分の考えとは異なる価値観があると認めない限り、読書はそこで止まってしまいます。
よくも悪くも、他者の価値観を受け入れる訓練ができる。それが読書の大きなメリットのひとつです。興味のあるかたは、EQに関する書籍を読んでみるのもいいかもしれませんね。
マインドフルネスと読書:現在に集中する力
深呼吸やストレッチといったごく簡単なものから、瞑想のように本格的なものまで、メンタルケアにはリラクゼーション技法が欠かせません。
なかでも、マインドフルネスは私たちのメンタルを深いレベルでケアしてくれます。じつは、マインドフルネスには、読書が非常に有効なのです。
過去や未来に囚われず、今このときに集中している状態を「マインドフルネス」と呼びます。マインドフルネスの境地に到達する具体的な手段としては、瞑想が一般的です。
読書は、この瞑想と非常によく似た状態を作り出してくれます。ここまで何度かお伝えしたように、読書中は本の内容に集中しているため、余計なことを考える余地がありません。
今に集中して、余計な外部要因をシャットアウトするというマインドフルネス瞑想のプロセスと読書は、非常に酷似していますよね。
過去と未来は後悔や不安を生み出します。私たちはもっと「今この瞬間」を重視すべきなのです。現在に集中する訓練として読書を捉えてみると、また違った感覚で読書に取り組めるのではないでしょうか。
◆マインドフルネスについては、コチラの記事でもお読みいただけます
睡眠の質の向上:就寝前の読書習慣
就寝前は、よくも悪くも、いろいろなことを考えてしまいます。なぜか夜に考える内容はネガティブなことが多いため、できれば余計なことを考えずに、気持ちよく眠りにつきたいものです。
睡眠の質の向上という意味では、就寝前の読書が非常にオススメです。好きな本を読めば、心がリラックスします。
よく、本を読もうとするとすぐに眠くなる人がいますよね。読書が苦手で眠くなる人もいるかもしれませんが、読書にリラックス効果があるのは間違いありません。
ただし、スマホやタブレットで読書をするのはやめてください。強力な画面の光を見て、脳が昼間だと勘違いしてしまうからです。そうなると、メラトニンという睡眠を誘うホルモンの分泌が減り、脳が活性化してしまいます。
就寝前に読書をする際は、あくまでもごく短時間だけ、紙の本を読むようにしてくださいね。
脳への影響を高める読書のコツとは

読書が脳へ好影響を与えることがわかったところで、さらにその影響を高める読書のコツを5点ほど紹介していきます。
重要なポイントは繰り返し読む
記憶に関する項目でもお話ししましたが、より記憶力を高めたいなら、重要なポイントを繰り返し読むのがオススメです。
理由は単純。人間の脳は、一度読んだだけでは長期間記憶しておけないようにできているからです。有名なエビングハウスの忘却曲線によると、わずか1日経過しただけで、人はインプットした情報を約74%も忘れてしまいます。
「えっ、それじゃ読書の意味がないじゃないか」と思われたかた、どうか安心してください。
カナダのウォータールー大学の実験データによれば、下記の頻度で復習をおこなうと、1カ月経っても最初に覚えた内容をほぼそのまま覚えておけるそうです。
- 第1回目:24時間以内に10分間
- 第2回目:7日後に5分間
- 第3回目:30日後に2〜4分間
本の内容や難易度によって、繰り返す回数はもう少し増えるかもしれません。いずれにせよ「復習は記憶力を大きく高めてくれる」という事実は、しっかりと頭に入れておきたいですね。
◆復習については、コチラの記事でお読みいただけます
覚えておきたい内容は紙の本で読むべし
より深く記憶に残しておきたい内容の本は、できるだけ紙の本で読むことをオススメします。利便性では圧倒的に電子書籍の勝ちですが、紙の本には紙にしかない大きなメリットがあるからです。
- 手触りや厚みといった要素が脳を刺激する
- マーカーや付箋を使ってカスタマイズできる
- 愛着が湧き読書の回数が自然と増える
- 特定のページを開きやすい
- スマホのようにSNSやゲームの誘惑がない
本のインクの匂いや、ページをめくるときのペラペラという音など、一見記憶とはまったく関係がないように思いますよね。でも、こういった触覚や聴覚が記憶のトリガーになって、ふとした拍子に内容を思い出すケースは本当によくあることなのです。
また「あれ、◯◯についてはなんて書いてあったっけ?」と、特定のページをパッと開きたいシチュエーションは、思っている以上にたくさんあります。
ところが電子書籍は、読みたいページを即座に開くのに、とても不向きです。しおり機能も用意されていますが、そもそも事前にしおりを設定しなければならず、地味に面倒くさいんですよね。その点紙の本なら、気になる箇所をすぐに確認できます。
変な誘惑がなく読書に集中できるのも、非常に大事なポイントです。この点については、別記事で詳しく解説しているので、よかったらそちらにも目を通しておいてください。
◆SNS上でのコミュニケーションについては、コチラの記事でお読みいただけます
オーディオブックを活用して耳からも情報をインプット
読書の有効性がわかっても、実際にはゆっくりと読書する時間が取れないというかたもいらっしゃると思います。そういう場合は、オーディオブックを取り入れてみたらどうでしょうか。
オーディオブックとは、書籍の読み上げサービスの総称です。厳密には、書籍に付属のCDなども含まれますが、実際には「Amazon Audible」のような月額制のサービスを利用するようになるでしょう。
オーディオブックのメリットは、大きく以下の5点があげられます。
- 車中や家事中でも読書ができる
- 早送り再生で時短が可能
- スキマ時間を有効活用できる
- 好きなナレーターの声は頭に入りやすい
- 保存場所が必要ない
できればオーディオブックと紙の本(電子書籍でもOK)を併用すると、視覚と聴覚のサンドイッチ効果で、記憶への定着度は大幅にアップする可能性が高いです。
また個人的には、1.5倍速でのリスニングを多用しています。なんども繰り返し聞いてガッチリと覚えたいときには、じっくりと聴くより1.5倍速のほうが効率的だからです。まずはいちどオーディオブックを試してみて、自分に合うかどうかを確認してください。
ハマれば、あなたの読書効率を一気に押し上げてくれるでしょう。
◆オーディオブックのメリットについては、コチラの記事でお読みいただけます
就寝前と午前中は読書のゴールデンタイム
同じ読書をするにしても、読書に適した時間帯に本を読むと、記憶効率は大幅にアップします。
まず記憶という面からみると、就寝前2〜3時間が読書のベストタイムです。というのも脳は、睡眠時にその日に起きたできごとを整理しようとします。したがって、できるだけ睡眠に入る直前にインプットするほうが、より鮮明な記憶として脳に保存されやすいのです。
ただし、あまりにも直前すぎると、ライトの光が睡眠へ悪い影響を及ぼす可能性があります。あくまでも就寝の2時間前くらいまでには、読書を終わらせましょう。
また、午前中も読書には非常に適した時間帯です。たっぷりと睡眠を取ってリフレッシュした脳は、午前中くらいならまだまだ余力があります。これが昼食を取ったあとや夕方になると、段々と脳が疲れてきて、じっくりと本を読む集中力が不足しがちです。
社会人の場合、午前中に読書をするのはなかなか大変だと思いますが、通勤時間などを利用して、積極的に読書へ挑戦してみてください。
インプットとアウトプットを両方おこなう
読書は、いうなればひたすらインプットをおこなう作業です。インプットはたしかに大事ですが、一方的にインプットばかりしていると、脳のバランス的にあまりよい状態とはいえません。
またインプットだけを繰り返すよりも、インプットとアウトプットをセットでおこなうほうが、より深い記憶が可能です。
もちろんアウトプットは、学校の読書感想文のように形式づいたものでなくても構いません。気になったポイントをちょっとメモしておくだけでも、大いに効果があります。
一番オススメなのは、読んだ内容を人に話すことです。内容を誰かに伝えようとすると、自分でもきちんと理解しなければなりませんから、自然と重要なポイントを読み取る力がつきます。
毎回でなくてもよいので、時々読んだ内容をアウトプットしてみてください。記憶への残り方が明らかに変わってくると思いますよ。
読書が子どもの脳の成長をサポート

読書は、子どもの脳の成長に大きな影響を与えます。この章では、読書が脳に与える影響について、わかりやすく説明していきます。
早期の読書が子どもの語彙力に与える影響
小さい頃から読書の習慣がある子どもは、語彙力の高さが顕著です。生まれたばかりの子どもは、もちろん言葉を知りません。親の話す言葉やテレビで流れる言葉を聞いて、少しずつ語彙数を増やしていくんですね。
少し成長して文字が読めるようになると、お母さんの読み聞かせを卒業して、今度は自分で本を読みだします。これまでは誰かから与えられた言葉ばかりに触れてきましたが、ここからは自分で読む内容を選べるわけです。
だから、なかには読書をほとんどせず、ゲームばかりしている子どもも出てきます。もちろん、ゲームが一概に悪いわけではありません。しかし、小学生の間に読書習慣をつくれない子どもの語彙力が著しく低いのは、さまざまな研究データを見ても明らかです。
たとえば、Centre for Longitudinal Studiesの研究チームは、14歳の子どもを対象におこなった研究結果として、「毎日読書をしている人は、まったく読書をしない人より26%多くの単語を理解している」と発表※しています。
そう考えると、やはり子どもには、できるだけ早くから読書習慣が身につくようにサポートしてあげたいところですね。
※参考:Reading improves teenagers’ vocab, whatever their background, say researchers
物語の理解と論理的思考力の関係
物語を読むという行為は、子どもが論理的思考を身につける絶好の機会をもたらしてくれます。
物語の中で繰り広げられる出来事に対して、あるいは登場人物の行動や思考を見て、子どもたちは「なぜ?」「それでいいの?」という疑問を何度も感じるはずです。
自分とは違う考えや行動を知り、自分の思考と比較することで、論理的な思考がどんどん鍛えられていきます。
また、高い論理的思考力には、すぐに思いつくだけでも以下のようなメリットが挙げられます。
- 相手の意向を正確に理解できる
- 自分の考えをわかりやすく相手に伝えられる
- 良好なコミュニケーションが取れる
- トラブルにも冷静に対処できる
- 生産性が大幅にアップする
これだけのメリットがありながら、多くの人は論理的思考力の凄さをあまり理解していません。まずは、大量の本を読み、いろいろな人の考え方を学ぶことからはじめてみてはいかがでしょうか。そうすれば、必ず理路整然とした思考でものごとを考えられるようになっていくでしょう。
読み聞かせは情緒促進に有効
子どもへの読み聞かせは、子どもたちの情緒発達にとって、非常に重要な役割を果たします。先ほどは、語彙力や論理的思考といった能力面に対するメリットをお伝えしました。
しかし、「読み聞かせは心の脳に届く」の著者である泰羅雅登教授は、「読み聞かせは知育だけでなく、人間の感情に大きく作用する」といった内容を、東京都教育委員会のサイト※に寄稿しています。
実際、親が子どもに読み聞かせをすると、感情や情動を司る大脳辺縁系の働きが強まったという研究結果が出ているそうです。
辺縁系を形成する海馬や扁桃体は、「楽しい、嬉しい」といったポジティブな感情だけでなく、恐怖や不安のようなネガティブな感情にも大きく関わっています。
人間はどうしても恐怖や不安を避けようとしますが、こういったネガティブな感情を知っておかないと、他人とのコミュニケーションがうまくいきません。嫌なことを知っているからこそ、相手に嫌なことをしてはいけないと、自分を律することができるのです。
もし、こういった心の動きを知らないまま、幼稚園や小学校に進級すれば、おそらく他人から受けるネガティブな感情に押しつぶされてしまうでしょう。
だからこそ、絶対的な味方である親が、読み聞かせを通して、心のよい面も悪い面も少しずつ教えてあげることが大切なのです。
※参考:東京都子供読書推進計画 » 読み聞かせは「心の脳」をはぐくむ
まとめ
「読書は脳によい」と、今までなんとなく感じていたことが、今回の記事で明確になったと思います。
そういった数あるメリットを意識しながら読書すれば、おそらく、今まであまり読書をしてこなかった人ほど、驚くほどたくさんの恩恵を受けるでしょう。
今回の記事が、読書をスタートするきっかけになればさいわいです。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読