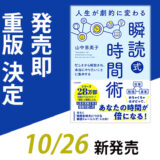記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
近年、SNSやチャットといったツールが一般的になり、文字によるコミュニケーションが激増しました。そこで俄然注目されるようになったのが、「読解力」です。
文字を主体にしたコミュニケーションの場合、読解力がないと変な誤解が生まれやすく、人間関係が壊れてしまう危険性もあります。そこで今回は、読解力に関する基本的な知識と、読解力が向上する方法について、解説していきます。
目次
読解力の基礎知識

読解力といっても、具体的にどういう能力を指すのか、いまいちハッキリしないという人も少なくないはずです。読解力向上の方法を紹介する前に、まずは読解力についてしっかりと学んでおきましょう。
読解力とは具体的にどういう能力なのか
読解力とは、文字通り、「読んだ内容を正確に理解する能力」です。とはいえ、この説明だけでは、イマイチ内容がわかりにくいと思います。
そこで、OECD加盟国を中心に定期的に実施される、国際的な学習テスト「PISA」を調べてみたところ、読解力は以下のように定義されていました。
自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力。
※引用:1 PISA調査における読解力の定義,特徴等:文部科学省
PISA読解力テストで測定する能力を見ると、さらに読解力に必要な要素が明確になります。
- 情報を探し出す
- 理解する
- 評価し、熟考する
つまり、ただ読んだ文章を理解するだけでは足らず、「その内容の真偽をきちんと評価して、しっかりと自分で考えられる」ところまでできて、はじめて読解力があるといえるわけです。
日本人の読解能力が低下しているのは本当か
日本人の読解力は低下していると、よく言われます。実際のところ、15歳児を対象におこなわれる「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)」では、回を重ねるごとに読解力の順位は低下し続けていました。
ところが最新の調査PISA2022※では、PISA2018の11位から、一気に2位まで上昇しています。つまり、日本人の子どもの読解力は、世界のレベルと比べて決して低くはないということです。
もちろん、この結果はあくまでも試験上のことだけであり、実際はさまざまな問題を抱えています。しかし少なくとも、日本人はある程度しっかりとした読解力の基礎を身につけていると判断しても構わないでしょう。
なお、成人については、2022〜2023年にかけておこなわれた国際成人力調査の結果が、おそらく2〜3年後に発表されるはずです。10年前の第1回調査で1位だった読解力が、どのような結果になっているのか、発表が待たれるところです。
※参考:文部科学省・国立教育政策研究所「PISA2022のポイント」
自分の読解力を評価する方法
自分の読解力を正しく把握するには、主観ではなく客観的な指標が必要です。そのひとつとして注目されているのが、「文章読解・作成能力検定(通称:文章検)」です。
公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する公的検定で、単なる語彙力や知識量ではなく、「文章を正しく理解し、論理的にまとめる力」を測定できます。
文章検では、与えられた文章をもとに要旨を読み取ったり、筆者の主張や根拠を整理したりと、実践的な設問が出題されます。そのため、自分の読解力を「仕事でどれだけ活かせるか」「相手に伝える力があるか」という観点から確認できるのが大きな特長です。
また、級ごとに難易度が設定されており、学習の目標にもなります。受験しなくても、文章検の公開サンプル問題を解いてみるだけでも、現在の読解力の課題を把握する良い目安になるでしょう。
読解力が重要な理由

読解力を身につけると、仕事や日常生活において、さまざまなメリットをもたらしてくれます。この章では、読解力が重要な理由を4つ紹介します。
情報収集のスピードが速くなる
読解力を高めると、情報収集のスピードが劇的に向上します。多くの人は、なにか知りたいことがあると、インターネットで検索するでしょう。(今はAIも台頭してきましたが)
検索上位の記事を中心に、いろいろなテキスト媒体を読み込むはずです。もちろん、ネット上の記事だけでなく、書籍を調べる人も多いでしょう。いずれにせよ、膨大な文章を読み、必要な情報をピックアップするには、かなりの時間がかかります。
しかし、読解力のある人は、文章をサッと読んで必要かどうかを判断できるので、情報収集にムダがありません。こうしたメリットは、とくにビジネスの場において威力を発揮します。情報を素早く集めて、顧客や上司に提案できれば、ライバルより一歩も二歩もリードできるはずです。
重要なポイントを的確に理解できる
先ほど、情報収集のスピードについてお話ししました。情報収集が素早くできるのは、優れた読解力により、重要なポイントを的確に理解できるからです。
現代社会は情報が簡単に手に入る時代であり、少し検索すればほぼなんでも答えが見つかります。しかし、目にする情報すべてが、等しく重要なわけではありません。
本にしても、本当に重要な箇所は数%という話をよく聞きます。たしかに、多くの本では、理解しやすくするための前フリや例・繰り返しが多用されていて、じつはなくても成立するパートが多いです。
読解力の乏しい人は、こういったオマケ的な部分も含めて、全部じっくりと読もうとします。すべて読めば取りこぼしは減るかもしれませんが、とにかく時間がかかり過ぎです。
一方で読解力があれば、文脈を素早く把握し、重要なキーワードや概念を効率よくピックアップできます。そういう意味で言うと、全文をザッと読みながら重要な箇所をイメージとして記憶していく右脳速読法は、非常にオススメです。
◆右脳速読法については、コチラの記事でお読みいただけます
情報の真偽を見抜く力がつく
読解力が高まると、目にした情報の真偽を見抜く能力も同時に養われます。この能力は、現代社会において、非常に重要です。なぜなら、インターネット上には正確な情報以上に、大量の誤情報や偏見に満ちた内容が氾濫しているからです。
いくら読解力があっても、間違った情報を信用してしまえば、かえって情報収集能力のスピードの速さが仇になってしまいかねません。でも、安心してください。高い読解力をもつ人々は、テキストを深く分析し、その情報源の信頼性や論理的な一貫性を客観的に評価できます。
なお、情報の真偽を見抜くという意味では、後述する「批判的視点で文章を読む」思考法(クリティカルシンキングという)は非常に有効です。
「本当に内容が正しいのか?」
「そもそも前提が違っているのではないか?」
「ほかにも選択肢はないのか?」
上記のように、批判的視点で文章を読めるようになれば、間違った情報に踊らされるリスクを大幅に軽減できます。
コミュニケーション力がアップする
読解力の向上は、コミュニケーション能力の向上に対して、ダイレクトに好影響を与えます。文章を読む過程で身につく洞察力や理解力は、言葉によるコミュニケーションの基礎をつくってくれるからです。
高い読解力をもつ人は、書かれている言葉の背後にある意図や感情を正確に捉えます。もちろん、会話によるコミュニケーションにおいても同様の能力を発揮できるので、相手の気持ちに寄り添った対応ができるのです。
ときには自分の主張をハッキリと伝えることも重要でしょう。しかし、多くの人は「自分を理解してもらいたい」と切望しているものです。だから、ほんの少し聞き役に回るだけで、相手から好意を抱いてもらえます。
もし、読解力を鍛えてコミュニケーションに活かしたいと思っているなら、小説がオススメです。文章で登場人物の心理描写や発言を表現する小説では、どうしても情報量に限界があります。しかし、小説を大量に読み込むうちに、不足する情報を自分で補って考えるクセがつきます。
そうなると、言葉の裏側に隠れた相手の気持ちや考え方を、少しずつ予測できるようになってくるはずです。こうした経験は、実際の会話の場においても、必ず役に立ちます。
読解力を伸ばす具体的な8ステップ

もし、自分の読解力に不安を感じているなら、今回紹介する8つの方法を試してみてください。どれか1〜2個習慣化するだけでも、読解力はぐんとアップするはずです。
◆読解力を向上させる方法については、コチラの記事でもお読みいただけます
1.語彙力を増やす:異なるジャンルの本に挑戦
読解力を高める第一歩として、まずは読書のジャンルを広げることから始めてみましょう。幅広い分野の本に触れると、語彙や表現力の引き出しが一気に増えるからです。いつも同じテーマの本ばかりだと、使われる言葉や文章構成が似通っていて、思考の幅も狭くなってしまいます。
たとえば、普段は小説中心の人がビジネス書や科学の解説書を読むと、これまで知らなかった言い回しや専門用語に出会えます。反対にいつも実用的な本ばかり読んでいる人がファンタジーものなどを読むと、想像力をかき立てる奥深い表現に驚くかもしれません。
いずれにせよ、こうして言葉のストックが増えていくと、文章を読む際の理解スピードや深さが格段に上がります。さらに、異なるジャンルで独特の表現方法や考え方に触れることで、自然と発想力や想像力も刺激されます。
読解力を鍛えたいなら、「なんだかむずかしそう」「自分には関係なさそう」と感じる本にも、あえて手を伸ばしてみてください。新しい言葉と表現方法が、あなたの読解力を大きく育ててくれるでしょう。
2.辞書を使って言葉の意味を掘り下げる
読解力の基盤は、やはり語彙力にあります。言葉の意味をあいまいなままにしておくと、筆者の意図を正確に読み取ることはできません。わからない単語に出会ったら、すぐ辞書を引く習慣をつけましょう。
辞書を使うときは、意味を確認するだけでなく、用例や語源、類語との違いにも注目してみてください。たとえば、「理解する」と「納得する」は似ていますが、前者は知的理解、後者は感情的理解という違いがあります。
こうした微妙なニュアンスの差をつかめるようになると、文章の解釈力がぐっと上がります。
また、こまかな使い分けを確認したい場合には、「記者ハンドブック」が便利です。新聞やビジネス文書などで使われる公的な文章のルールがチェックできるので、1冊持っておいて損はありません。
3.論理展開パターンと文章の構造を理解しておく
論理展開のパターンや文章構造を意識して読むと、理解力とスピードの両方が飛躍的に高まります。文章をただ順に追うのではなく、「どんな順番で、どのような論理展開の基に話が進んでいるのか」を意識してみましょう。
文章構成にはいくつかの基本パターンがあります。たとえば、三段構成「序論→本論→結論」は論文などでよく使われており、四段構成「起承転結」は物語やコラムに多い形式です。
事件の報道が目的である新聞やニュース記事は、結論をスパッと述べる頭括構成「結論→補足説明」で書かれているし、同じく結論ファーストのPREP法「結論→理由→具体例→結論」はビジネス文書やネット記事でよく使われています。
今読んでいる文章がどういった構成に基づいて書かれているのかがわかると、要点を素早く読み取れるようになります。
また、「しかし」「つまり」「たとえば」といった接続詞の働きを意識することも大切です。さらに、主語と述語の対応、修飾語の位置関係なども確認すれば、意味の取り違えを防げます。
このように論理展開パターンと文章構造を理解しておくと、複雑な文章でも流れを素早くつかみ、しっかりと内容を理解できるようになるでしょう。
◆基本的な文章構成ルールについては、コチラの記事でお読みいただけます
4.わからない部分は必ず「再読」で確認する
文章は前後の文脈がつながって意味を成しているため、途中の“わからない箇所”を放置すると、読み進めるほど内容がぼやけてしまいます。そのようなときは、迷わず「再読」しましょう。一度ではわからなかった箇所も、読み返すことでつながりが見えてくるものです。
再読では、つまずいた理由を明確にするのがポイントです。言葉の意味がわからないのか、文章の関係性が不明瞭なのか、つまづいた理由を切り分けると対処法が明確になります。
むずかしい言葉や抽象的な表現に引っかかったなら、辞書や信頼できる解説サイトできちんと調べましょう。文の流れがうまくつかめないなら、接続詞や修飾語を意識しながら前後の段落を通して読むと理解しやすくなります。
また、細部にこだわりすぎて進めなくなるときは、一度最後まで通読してから戻るのも効果的です。全体像をつかんだうえで再読すると、意外とすんなり理解できることも多いですから。
「わからないところをそのままにしない」このことを徹底すれば、あなたの読解力は確実に向上します。
5.アクティブリーディングを意識しながら読む
読解力を高めたいなら、「ただ読む」のではなく、能動的に理解しようとするアクティブリーディングを意識してみてください。目的意識を持って読むだけで、同じ本でも得られる情報量がまったく変わってくるものです。
読む前に「この本からなにを知りたいのか」「どのような結論が書かれていそうか」を考えるだけで、内容の吸収率は大きく上がります。
実践の第一歩として、まずは目次を確認しましょう。目次は本の全体構成を示す“地図”のようなもの。よく練られた目次なら、ざっと目次に目を通すだけでも、筆者の考え方や論旨の流れが大まかに見えてきます。
また、読書中に気づいたことや疑問点などは、余白や付箋にメモしておくのがオススメです。そういった点はあとからチェックすればいいので、頭のなかに雑念が残らず、本の内容に集中できます。
いずれにせよ、ただ読み流すのではなく、目次の確認や疑問点のチェックなど、アクティブ(能動的)に読む意識が重要です。そうすれば、文章を読むスピードだけでなく、分析力や情報処理能力も確実に向上します。
6.批判的視点で「著者の主張の根拠」を探す
読解力をさらに高めるには、文章を「批判的視点」で読む姿勢が欠かせません。ここでいう批判とは、相手を否定することではなく、書かれている内容の根拠や妥当性を冷静に確かめることを意味します。
書籍の内容はすべて正しいと思いがちですが、じつは著者の個人的思想がかなり介入しているケースも少なくありません。統計データや専門家の意見が示されている場合でも、それが本当に中立的に使われているか、いちど疑ってみてください。
同じ数字でも、表現の仕方ひとつで印象はまったく変わってくるものです。「50%もある」と「50%しかない」では、受け取る意味が逆になりますよね。このように、文章の裏にある意図やデータの扱い方まで意識して読むと、表面的な理解を超えた本質的な読解ができるようになってきます。
書き手のバイアスを排除して正しく読み解くためにも、ぜひクリティカルシンキングを意識してみてください。
◆批判的視点(クリティカルシンキング)とロジカルシンキングの違いについては、コチラの記事でお読みいただけます
7.重要部分にマーキングやメモを残す
マーキングやメモ書きも、読解力向上に大きく役立ってくれる方法のひとつです。読みながらマーキングやメモ書きをしておくと、文章の要点整理を効率よくおこなえるので、理解度が格段にアップします。
読みっぱなしだと読み進めるにつれ、どうしても情報が流れてしまいやすいです。ところが、自分の手を動かして重要なポイントや疑問点などをチェックしておけば、記憶にも残りやすくなります。
マーキングのやり方は自由です。たとえば、重要な主張には線を引き、疑問に思った部分には「?」、納得した箇所には「◎」など、自分なりの記号を決めて書き込んでおきましょう。
とはいえマーキングをやりっぱなしにしておくと、あとから読み返したときに、なぜそういう判断をしたのかをまたじっくりと思い返さなければなりません。マーキングをしたら、その理由や詳細を付箋などにメモしておくと、すぐに確認できて便利です。
ただし、あまりにも多くの箇所に印をつけると、重要な部分が埋もれてしまいます。ポイントは、本当に残したい部分だけに絞ってチェックするようにしましょう。
◆オススメのメモの取り方については、コチラの記事でお読みいただけます
8.1冊を読んだら「3行要約」をしてみる
きちんと読み取れたかどうか、自分の読解力を確認する方法として、ぜひ「3行要約」にトライしてみてください。読んだ内容を短くまとめようとすると、自然と文章の構成や筆者の主張を深く理解しようという意識が働きます。(3行にこだわる必要はありません。5行でも10行でもOKです)
要するに、要約は「理解を確認するテスト」のようなもの。要点を過不足なく自分の言葉で整理できるかどうかが、真の理解度を測る指標になります。最初は時間がかかっても構いません。繰り返すうちに、自然と重要な箇所がわかるようになってきますので。
3行要約でもっとも重要だと思われるポイントのまとめに慣れてきたら、次のステップとして章ごとの要約にも取り組んでみましょう。章の最後にまとめが載っているビジネス書などを題材にすれば、自分の読解力の答え合わせができます。
もちろん、まとめ以外にも重要な箇所があり、どこに響くかはひとそれぞれです。まとめと違っているから間違いというわけではないので、その点は誤解のないようにお願いします。
◆具体的な要約のポイントについては、コチラの記事でお読みいただけます
読解力と他のスキルの関係

読解力は決して単独で存在するスキルではなく、創造性やコミュニケーション力といった、ほかの能力と密接に関係しています。具体的に、読解力がどのようにほかのスキルと関係しているのか、今回は4つの能力を例に説明していきます。
創造性を高める読解力の役割
読解力は、創造性を高めるうえで大切な役割を果たします。創造性といっても、なにもないところからまったく新しいアイデアを生み出すのは不可能です。そもそも、情報社会の現代では、ひと通りの情報が誰でも簡単に手に入ります。
ゼロからつくり出すというよりも、既存のアイデアをいかにうまく組み合わせて、新しいものを創出するかが重要なのです。そういう意味で、情報の仕入れ方が非常に重要なポイントになってきます。
ネットですぐに確認できる動画がもてはやされる昨今ですが、情報収集に読書は欠かせません。主な理由は5つあります。
- 周辺情報も含めて網羅的に収集できる
- 新しい視点に出会える
- 復習がしやすい
- ビジュアルから受ける余計な先入観の影響が少ない
- ある程度の信頼性や権威性が担保されている
動画情報は、歴史が浅い分、情報の信頼性に疑問符がつく場合も多いです。その点、長年読み続けられている名著なら、情報の信頼性はまず問題ないと考えてよいでしょう。
また書籍は読み返しが容易なので、重要な部分だけを繰り返し読み、使える情報に落とし込みやすいです。優れた読解力で文章の奥深い部分まで理解できると、そこから得た知識やアイデアを発展させて、より豊かな発想を育てることができます。
コミュニケーション力との相互作用
読解力とコミュニケーション力は、互いに深く関係しています。読解力を高めることで、コミュニケーション力も向上し、高いコミュニケーション力によってさらに読解力が深まるのです。以下、その相互作用について簡単に説明します。
1.相手の意図を正確に理解できる
読解力があると、相手の言葉や文章の意図を深く理解できます。相手がなにを伝えたいのか、どのような気持ちで話しているのかを正確に把握できるため、誤解が生じにくくなり、スムーズなコミュニケーションが可能です。
2.自分の意見を的確に伝えられる
読解力が高いと、文章の構成や適切な表現方法を自然に学べます。その結果、自分の考えや意見を整理して伝える力も身につくのです。言いたいことを的確に伝えられれば、より効果的なコミュニケーションが取れるようになります。
3.意思の疎通を図る機会が増える
読解力が高い人は、相手の考えや感情に基づいた質の高いコミュニケーションが得意です。そのため、相手から好意をもってもらいやすく、意思の疎通を図る機会が増えるので、ますます関係がよくなります。
このように、読解力によって対人関係がよくなると、言葉の裏側にある気持ちや意図に敏感になります。そういう状態で読書をすると、さらに深いレベルで文章を読み解けるようになってくるのです。
問題解決能力への影響
読解力は、問題解決能力にも大きな影響を与えます。読解力とは、ようするに情報を正しく読み解く力です。問題解決をするには、まず問題点を正確に把握しなければなりません。読書で身につけた知識や論理的思考が、問題点の把握に非常に役立ってくれます。
読書の習慣がない人は、どうしても自分の先入観でものごとを判断する傾向が強いです。なぜなら、ほかの考え方を知らないからです。
その点、日頃から大量の本を読んでいる人は、さまざまな考え方や知識を身につけています。読書から得た高い読解力があれば、広い視点からより多くの解決策を見つけられるでしょう。
これから問題解決能力を高めたい人は、とくに論理的思考を意識した読書をオススメします。
◆問題解決に有効な論理的思考については、コチラの記事でお読みいただけます
記憶力と読解力の相乗効果
記憶力と読解力は、お互いに影響を与え合う関係にあります。まず、読解力が高いと、内容の理解が容易になり、その結果として記憶に残りやすくなります。一方で、むずかしい本を読んだとき、理解が曖昧なまま放置しておくと、すぐに忘れてしまうでしょう。
また、記憶力がよいと、過去に読んだ記憶を思い出しながら新しい文章を読めるので、より深い理解が可能です。
記憶力と読解力の相乗効果を活かすには、まず復習が重要になってきます。人間誰しも1回ですべてを記憶するのは不可能です。しっかりとした記憶として定着させるためにも、理解できるまで繰り返し読み返してください。
覚える際には、自分の言葉でまとめた内容を覚えた方が、より鮮明に記憶に残ります。鮮明な記憶は、記憶から引き出す際も、スムーズです。読解力を高める効率のよい記憶法については、別記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらの記事もご参照ください。
◆効率的な記憶法については、コチラの記事でお読みいただけます
読解力向上に役立つオススメの書籍
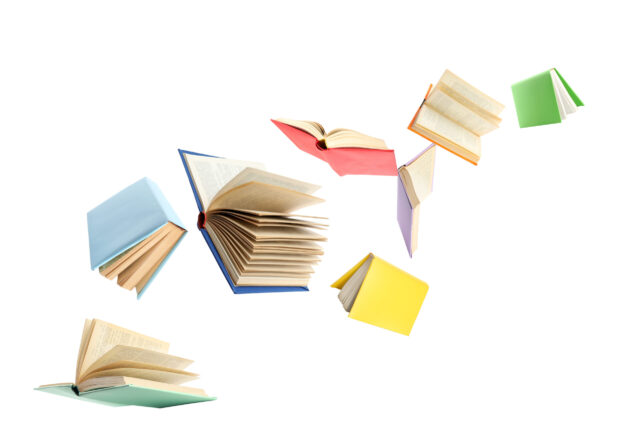
最後に、読解力向上に役立つオススメの書籍を3冊紹介します。
「読書する人だけがたどり着ける場所」齋藤孝
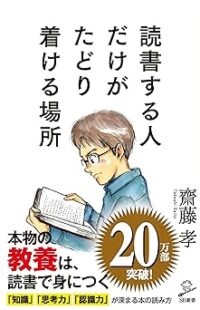
最初に紹介するのは、メディア露出も多い明治大学文学部教授「齋藤孝」さんによる、「読書する人だけがたどり着ける場所」です。
これまでにも、「読書力」や「読書の全技術」といった読書に関する書籍を出版していますが、当書も20万部を超えるベストセラーとなっています。
この本は、読書を通じて個人が教養を身につけ、より深みのある人間になる方法を提案しています。
「今の時代、ネットで情報が入るから読書は必要ない」という風潮も強いですが、ネットの情報は表面だけの情報が多く、非常に浅い知識になりがちです。
その点、読書は物事の本質を身につけられます。じっくりと文章に向き合うことで本の内容を疑似体験し、人生観や人間観を深め、人格の成長が期待できるからです。
読書において、このじっくりと本に向き合う姿勢(本書では構えと表現)は、非常に重要です。本からより深い情報を引き出す方法が知りたい人は、ぜひこの本を手にとってみてください。
「社会に出るあなたに伝えたい なぜ、読解力が必要なのか?」池上彰
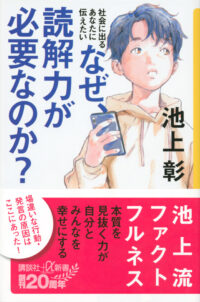
「場にそぐわない発言や行動をしてしまう」「相手とのコミュニケーションがうまくいかない」といった人は、読解力が不足しているケースが多いです。この本は、社会に出る新しい世代に向けて、読解力の重要性や読書力の伸ばし方を丁寧に解説してくれています。
本書では読解力について、「論理的読解力」と「情緒的読解力」は異なる能力であり、両方身につけることが重要であると述べています。
今の時代は、どうしても論理的に文章を読み解く力が重視されがちです。しかし、文章の裏にある相手の意図や感情を読み取る「情緒的読解力」ができて、はじめて本当の読解力といえます。
SNSやネットで頻繁に起こる炎上騒ぎも、こうした情緒的読解力不足が大きな原因です。こうした不要なトラブルを起こさないためにも、著者は「読書量を増やして、他人の経験を自分も追体験してみる」ように勧めてくれています。
「全教科対応! 読める・わかる・解ける 超読解力」善方 威
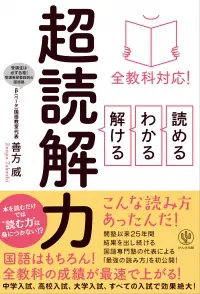
「全教科対応! 読める・わかる・解ける 超読解力」は、善方 威氏によって書かれた読解力に関する本です。
本書は、受験を控えた学生がターゲットの本ですが、論理的な文章を読み書きする必要のあるすべての人に役立つ内容になっています。
著者は法律の文章に携わってきた経験が長く、難解な法律文書を図式や道具に当てはめてわかりやすく読み解く方法を編み出しました。そのノウハウをまとめたのが、本書なのです。
- すべての文章:「〇×△」
- 論説文:「二元論スペシャル」「言語の構造」
- 物語文:「成長の物語」「ラブラブスペシャル」
など、図式を活用した著者オリジナルの読解法が満載の1冊となっています。非常にわかりやすい説明となっており、小学生や中学生でも十分理解できるオススメ本です。
まとめ
読解力が不足すると、いい加減な情報に騙されたり、コミュニケーションがうまくいかなかったりします。今回紹介した「読解力を伸ばす具体的な8ステップ」を参考に、しっかりと読解力をアップしていきましょう。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読