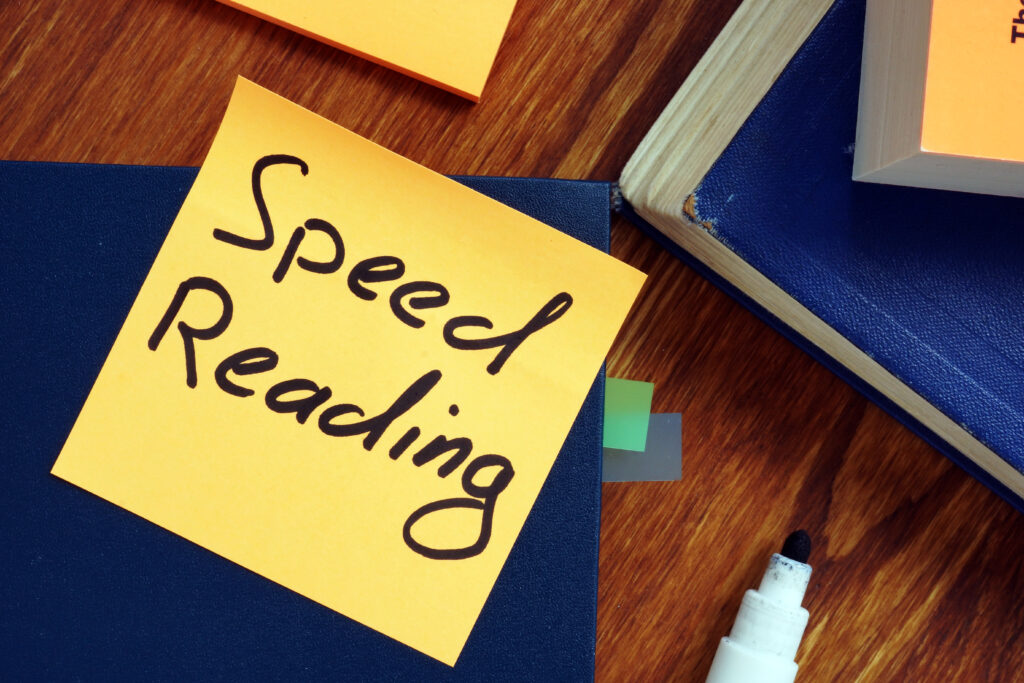記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
「速く読めるようになれば勉強も仕事ももっと効率がよくなるのに…」誰もが一度はこのように感じたことがあるのではないでしょうか。それなのに、自分には無理だと諦めてしまう人も多いのが現実です。
しかし、速読は持って生まれた才能ではなく、トレーニングによって習得できるスキルです。本記事では、速読の概要や得られる主なメリット、そして具体的な速読法についてわかりやすく解説していきます。
速読に興味のあるかたは、ぜひ最後まで読んでみてください。きっと「これなら自分にもできそう」と感じてもらえるはずです。
目次
速読とはなにか?基本から理解しよう
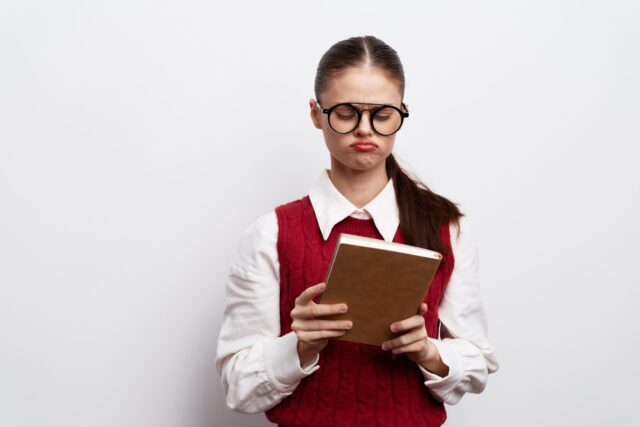
速読の本質を知ることは、効果的な活用への第一歩です。まずは、通常の読書との違いやよくある疑問、速読が注目される背景について整理していきましょう。
速読の定義と普通の読書との違い
速読とは、単に読むスピードを上げる技術ではなく、「理解しながら素早く情報を処理する」ことを目的とした読み方になります。私たちが普段おこなっている読書は、文字を一字ずつ目で追い、頭のなかで音声化しながら意味を理解していくのが一般的です。
一方、一般的な速読では、文字ではなく単語(あるいは複数の単語)ごとに読み、読書スピードを高めていきます。慣れてくると文節単位で読めるようになり、読むスピードは分速1,000〜2,000文字くらいまでアップします。(通常の読書スピードは分速500文字前後)
ただし、眼球の高速移動を基本としているため、長時間の速読になると目が疲れてしまい、速読の効率が低下することも少なくありません。
そういった背景もあり、近年では、目の負担が少ない“右脳型速読”が非常に注目を集めています。右脳型速読とは、イメージ化が得意な右脳を使い、文章を画像として記憶していく速読法です。各速読法の特徴と違いなどについては、最後の章で詳しく解説します。
速読に対する懐疑的な意見
速読でバリバリ速く読みたいという人が数多くいる一方で、「本当にそんなに速く読んで理解できるのか?」という疑問の声も少なくありません。たしかに、通常の読書しか知らない人からすれば、数分で一冊を読むような速読に怪しさを感じてしまうのは無理もないでしょう。
人間の脳が情報を処理する速度には限界がありますから、あまりにも速く読み進めると内容が頭に残りにくいという指摘はたびたび取り上げられてきました。実際、大学や研究機関の調査※でも、「読む速度を上げると理解度が下がる傾向にある」という結果が報告されています。
とはいえ正しい方法で訓練すれば、理解をある程度維持しつつ、通常よりも速く読むことは十分可能です。速読は誰でも一瞬で速く読めるようになる魔法ではなく、訓練によって伸ばせるスキルです。まずその点を、しっかりと区別しておく必要があります。
※So Much to Read, So Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help? – PubMed
理解力は落ちないのか?
速読についてよくある疑問のひとつが、先ほども触れた「速く読んだら内容の理解が浅くなるのでは?」という点です。結論から言えば、正しい方法で練習すれば、理解力はほとんど落ちません。
なぜなら、速読は単に文字を飛ばして読むのではなく、重要な情報を素早く見つけ出し、要点をつかむ力を高める読み方だからです。まず、大前提として、普通の読み方をしても100%内容を理解し記憶しておくのは無理だという論点があります。
当然速読でも、内容を100%理解するのは無理な話です。ですが、要点をしっかりと読み取っているので、通常の読書と同じくらいの理解度は問題なく維持できます。
先ほど紹介した研究でも、読む速度を上げると理解度が下がる傾向にあるという報告と同時に、「適切なトレーニングをおこなえば、速度と理解は両立可能である」と報告されています。
もちろん、いきなり速く読もうとすると理解度が落ちることはあるでしょう。しかし、段階的に練習を重ねれば、速さと理解を両立することは十分可能です。
速読が注目されるようになった背景
速読がここまで広く注目されるようになった背景には、現代社会ならではの“情報量の爆発”があります。インターネットやSNSの普及により、私たちが1日に触れる情報量は20世紀初頭と比べて数百倍に増えました。
情報量が多いのは一見よいことだらけのように思えますが、情報の取捨選択に余計な労力を割かれてしまうのは非常に大きなデメリットです。そのため、現代に生きる私たちには、生活のあらゆる場面で「限られた時間で効率よく情報を処理する力」が求められています。
こうした背景から、速読は単なる読書法ではなく、「情報社会を生き抜くためのリテラシー」として注目されているのです。
速読で得られる効果

本を速く読めることによるメリットがわからないと、なかなか速読に取り組もうという気持ちが起こらないものです。そこでこの章では、速読で得られる代表的な効果を4つ紹介します。
勉強の効率が大幅にアップ
速読を身につける最大のメリットのひとつが、勉強効率の大幅な向上です。読むスピードが速くなると、同じ時間で扱える教材や参考書の量が増えるため、インプットの総量が飛躍的に高まります。
また、文章の要点を素早くつかむ習慣がつくので、理解までの時間が短縮され、復習の回数も増やせます。受験、資格試験において、まずは1冊をやりこむ反復学習が基本です。
1冊に6時間かかっていた参考書が3〜4時間で読めるようになれば、残りの時間を復習または問題演習に使えます。このように、限られた時間のなかで成果を出したい学生や社会人にとって、速読は非常に大きな武器になってくれるでしょう。
ビジネスの実務処理が速くなる
速読は、ビジネスの現場でも大きな力を発揮します。仕事では日々、多くのメール・資料・レポートなどを読み解き、短時間で判断することが求められます。速読を習得すれば、こうした情報の処理スピードが飛躍的に向上し、意思決定までの時間を大幅に短縮可能です。
たとえば、1時間かかっていた報告書の精読が30分で終われば、その分ほかの業務に時間を回せますし、複数の資料を比較・検討する余裕も生まれます。
参考にする資料が少ないとどうしても、視点が偏ってしまうものです。その点、速読で複数の資料を比較できれば、より正確かつ客観的な情報を基に行動できます。
また、素早く全体像をつかんで要点を整理する力は、会議準備やプレゼン資料の作成などにも役立ちます。このように仕事のパフォーマンスが向上し、大きな信頼や評価につながる点が、速読の大きな魅力のひとつです。
試験での時間的アドバンテージ
速読は、試験対策において大きな武器になります。限られた時間のなかで問題文を読み解く力が求められる試験では、読むスピードが遅いと解答しきれず時間切れになってしまうことも珍しくありません。
速読を身につければ、文章を読む時間を大幅に短縮できるため、解答に使える時間を増やせます。たとえば、1分間に300字だった読書速度が、速読で600字にアップしたとしましょう。
60分の試験で問題文を読む時間が20分かかっていた人なら、単純に考えて10分で読み終えられます。そうすれば、その10分を選択肢のこまかい検討や解答の見直しに充てられるわけです。
また、試験前の過去問演習や教材の復習にも速読は役立ちます。短時間で繰り返し復習できるので、理解の精度が高まり、本番での得点力アップが期待できます。
◆速読の試験における時間的アドバンテージについては、コチラの記事でもお読みいただけます
スポーツやアートでも役立つ
速読は勉強や仕事だけでなく、意外なことにスポーツやアートの分野でも役立ちます。なぜなら、速読のトレーニングは「情報を瞬時に捉えて判断する力」を鍛えることにつながるからです。
たとえば野球やサッカーのような球技では、相手の動きやボールの軌道を素早く読み取って次の行動を決めなければなりません。視野を広く使って情報を処理する力が高まれば、判断スピードにもよい影響が出ます。
また、速読で培った視野の広さや情報処理能力は、作品全体を素早く把握して構図やバランスを考える力が求められる、絵画やデザインといった創作活動にも役立ちます。
さらに、多くの情報を短時間で取り入れられるようになると、アイデアの引き出しも増え、表現力の幅が大きく広がるでしょう。このように速読は、「読む力」を超えて、さまざまな分野で応用できる汎用的なスキルなのです。
◆速読がスポーツに与える好影響については、コチラの記事でもお読みいただけます
主な速読法の特徴

ひと言で速読といっても、さまざまな方法に分類され、それぞれ特徴が異なります。ここでは、代表的な4タイプの速読法の概要を紹介します。
視読
「視読(しどく)」は、ほとんどの速読法のベースとなる最も基本的なアプローチです。通常の読書では、文字をひとつずつ追って頭のなかで音読しながら理解していきます。視読ではそのプロセスを省略し、単語や文節単位を1回にまとめて捉えます。
たとえば通常の読書なら、「東京タワーが見えるレストラン」という文章を、「東京」「タワーが」「見える」「レストラン」とこまかく分けて読んでいるはずです。
ですが視読では、「東京タワーが見える」「レストラン」というように、もっと大きなかたまりとしてまとめて理解していきます。慣れてくると、そのかたまりが文章単位になり、さらに読書スピードはアップします。
もちろん、脳内音読もしません。脳内音読の速さは分速400文字ほどであり、脳内音読を続けている限り、1分間に1,000文字以上の速さで読むのは不可能です。
このように、視読は速読の基本テクニックであり、どの速読法も視読がベースになっています。
◆視読については、コチラの記事でもお読みいただけます
◆脳内音読については、コチラの記事でもお読みいただけます
高速視線移動タイプ
「高速視線移動タイプ」は、文字通り目の動きを速くして読むスピードを高める速読法です。「速読をしたいなら、速く目を動かせばいい」という非常にシンプルな理論であり、やるべきトレーニングも明確です。
おそらく、多くの人が速読としてイメージしているのは、この高速視線移動タイプでしょう。高速視線移動タイプも、ベースにあるのは前述の視読です。かたまりで読める範囲を広げていく手段として、目を速く動かしていきます。
ただ、目の動きにはどうしても限界があります。どれだけ速く目を動かせるようになっても、通常の2倍程度までが限界です。しかも、長時間目を高速で動かし続けると、疲労によりパフォーマンスが落ちてしまうというデメリットも存在します。
そのため長時間の速読は必要ないが、シンプルに速読を学びたいという人に、高速視線移動タイプはオススメです。
スキミング・スキャニング
「スキミング」と「スキャニング」は、別名「飛ばし読み」とも呼ばれ、日本でも広く使われているテクニックです。どちらも詳細な内容にはこだわらず、全体の大まかな理解を目的としています。
スキミングは、文章の全体像や重要な流れをざっくりとつかむのに向いています。一方スキャニングは、全体を把握する点は共通していますが、必要な情報を素早くピックアップするのが主な目的です。
同じ飛ばし読みでも目的が異なるため、たとえば試験の長文問題で概要だけをつかみたいときはスキミング、必要なデータをすぐ確認したいときはスキャニングを使うというように使い分けていきます。
いずれにせよ、全体を流して読んでいるので、こまかい内容は理解できていません。なので、深い理解度を必要としない作業、ビジネス書や資料の要点チェックなどに活用していくのがオススメの活用法です。
◆スキミングとスキャニングについては、コチラの記事でもお読みいただけます
右脳速読
「右脳速読」は、これまで紹介してきた視覚処理中心の速読とは大きくアプローチが異なります。視読がベースになっているのは共通していますが、右脳速読の場合、目の高速移動がほとんどありません。
通常の読書(眼球高速移動タイプの速読を含む)では、文字を順番に読み取り、論理的に理解する「左脳型」の処理が中心です。一方、右脳速読では、文字情報を映像のように一瞬でイメージ化し、全体の意味を直感的に把握します。
たとえば、「海辺を歩く少年」という一文なら、その情景を頭のなかで映像に変換していきます。文章を映像としてパッと理解するほうが、単語ごと理解していく通常の読書より圧倒的に速い速度での読書が可能です。
また、映像で理解するほうが、記憶への定着度も格段にアップします。こういった読み方ができるのも、イメージ化や直感、空間把握能力などをつかさどる右脳の働きを活用しているからです。
もちろん、習得までにある程度のトレーニングは必要ですが、きちんとメソッドに沿っておこなえば誰にでも習得できます。
◆右脳速読の詳細については、コチラの記事でお読みいただけます
◆主な速読法の違いについては、コチラの記事でもお読みいただけます
まとめ
速読とは、ただ文字を速く追う技術ではなく、「効率的に情報を処理し、理解する力」を高める読み方です。読む速度が上がれば、勉強や仕事の効率はもちろん、試験での得点力や日常生活での判断力まで大きく向上します。
もちろん、最初から驚くようなスピードで読める人はいません。ですが、正しい方法でトレーニングを重ねれば、誰でも少しずつ速さと理解を両立できるようになります。情報が溢れる時代だからこそ、速読を「知識を武器に変える力」としてどんどん活用していきましょう。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読