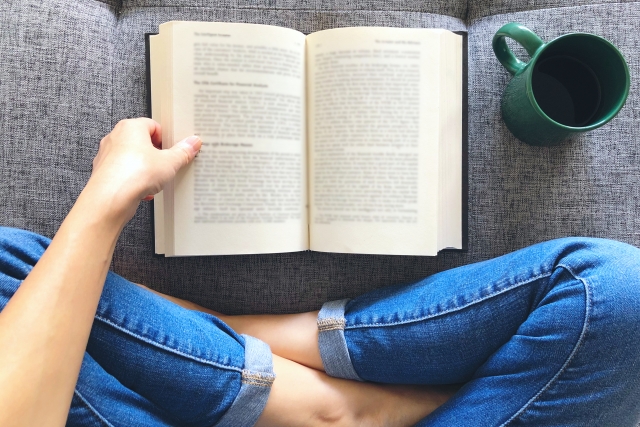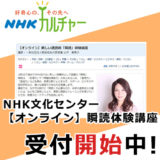記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
記事の監修
株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子
大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。
学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。
2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。
著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。
脳科学研究 第一人者の推薦
私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう
私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。
本を読む習慣のない人にすれば、「読書にはたくさんの効果がある」といわれても、ピンとこないかもしれません。
しかし結論からいえば、読書には本当にたくさんの効果があります。まず著者と面識がなくても、専門家のもつ知識や考え方が、自宅にいながら手に入ります。簡単に書いていますが、よく考えたらこれは凄いことですよね。
もちろん、読書の効果はそれだけではありません。今回は読書で得られる代表的な効果を9つご紹介します。
目次
語彙力が飛躍的に伸びる
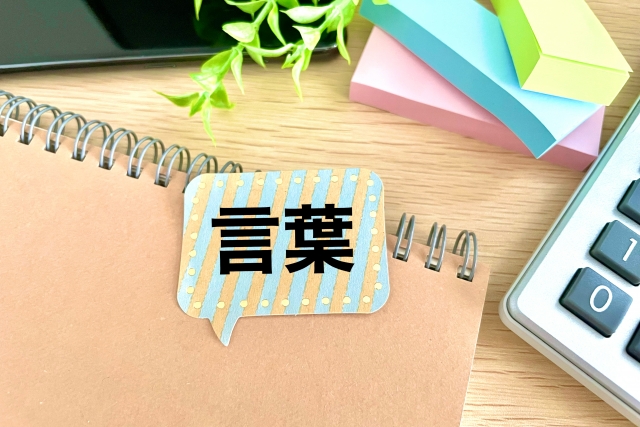
読書を習慣にすると、自然と語彙力が伸びていきます。なぜなら本のなかには、普段の会話ではあまり使わない言葉や言い回しが数多く登場してくるからです。
私たちが普段よく見るニュースやSNSでは、ごく一般的な言葉しか登場しません。しかし、文学作品やエッセイを読むと、じつに豊かな言葉の世界が広がっています。
たとえば「美しい」という意味を表す言葉ひとつとっても、「麗しい」「華やか」「端麗」など状況に応じて微妙にニュアンスの異なる言葉が登場します。しかも実際に文章を読み進めるなかで出会った語彙は、文脈とともに記憶に残るので忘れにくいのです。
いくら日本語のネイティブでも、知らない言葉や表現は必ずあります。読書はそういった語彙を身につける絶好のチャンスです。
◆語彙力がある人のメリットについては、コチラの記事でお読みいただけます
表現力・文章力が鍛えられる

読書は、語彙力だけでなく表現力や文章力を養うのにも大いに役立ちます。理由は、優れた文章に触れることで、「言葉の選び方」や「文の組み立て方」を自然に学べるからです。
たとえば小説を読めば情景描写の多様な表現に出会えるし、ビジネス書では論理的で簡潔な書き方が学べます。そうやって身につけた表現力や文章力は、メールの文面や企画書の作成、プレゼンの原稿づくりなど、仕事や勉強などあらゆる場面に活用できます。
自分のなかに軸となる文章力が不足していれば、いくら文章を考えてもなかなか上達しません。しかし、読書により自分のなかに表現の引き出しが蓄積されてくれば、自然と文章力は上達します。
その結果、自分の発言がより的確に相手へ伝わるようになり、仕事のみならずプライベートでも成果が出やすくなってくるはずです。
共感力が育まれコミュニケーション能力が向上する

読書には、人の気持ちを理解する力、つまり共感力を高める効果があります。小説やエッセイを読むと、登場人物の立場や感情を追体験することになり、自分とは異なる価値観や背景を自然に想像する習慣が身につくわけです。
これは心理学の研究でも裏付けられており、質の高いフィクションを読む人ほど他者への理解度が高い傾向があると報告※されています。たとえば、物語の主人公が困難に直面している場面を読むと、自分も同じ状況に置かれたように感じ、相手の苦しみや喜びを想像できるようになってきます。
もちろん、自分の感じていることと相手の意図がズレていることも当然あるでしょう。ですが、相手の気持ちを推し量ろうとする気持ちは必ず相手に伝わります。そういったことの積み重ねが、円滑なコミュニケーションや信頼関係の構築につながっていくのです。
※Novel Finding: Reading Literary Fiction Improves Empathy | Scientific American
◆読書によるコミュニケーション能力の向上については、コチラの記事でもお読みいただけます
創造力が磨かれる
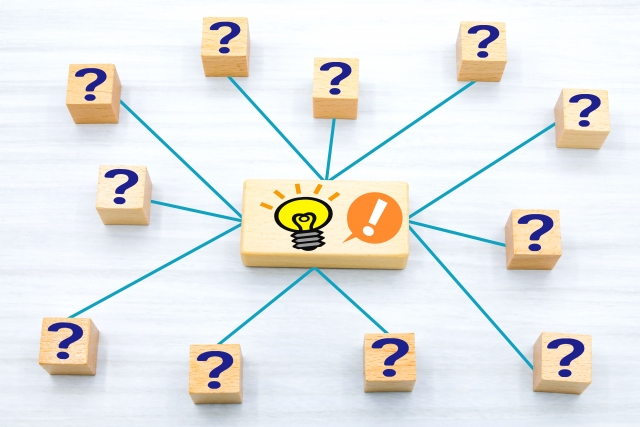
読書は創造力を育てるうえでも、非常に効果的です。読書を通じて普段接点のない世界観や思考に出会うと、新しい視点が自分のなかに少しずつ育ってきます。
たとえば異文化を舞台にした作品を読むと、日常の枠を超えたさまざまな描写が自然と頭に蓄積され、発想の幅が広がります。受容できる範囲が広がっているので、一見突拍子がなさそうに見えることでも、無下に否定しません。
また、エッセイや哲学書を読めば、自分では思いつきもしないような新しい発想のきっかけを得られます。そうやって育まれた「新しいことを受け入れる姿勢」が、これまでに考えつかなかった斬新な発想を生み出す原動力になってくれるのです。
もちろん、創造力には先天的な才能も多少は関係しているでしょう。しかしそれと同時に、日々の刺激によって磨くことのできる能力でもあります。読書を通じて、創造のタネをどんどん仕込んでいきましょう。
新しい価値観に出会える
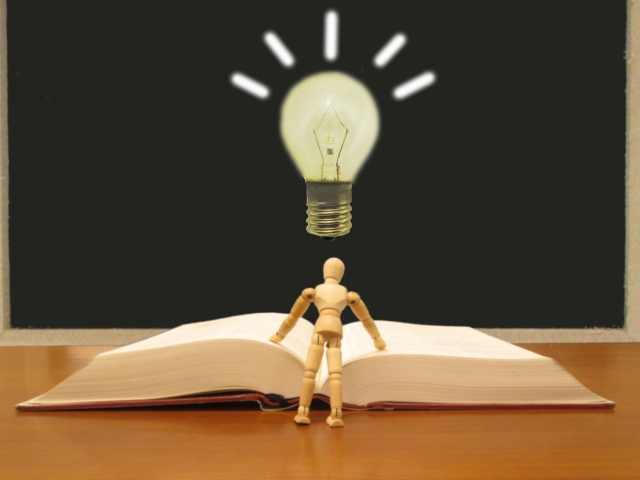
読書は、今までの自分では考えもつかないような新しい価値観に出会うきっかけを与えてくれます。私たちは普段、家族や職場など限られた環境のなかで生活しているため、どうしても考え方や視点が偏りがちです。
しかし、本を開けば、自分とは違う文化や背景を持つ人の生き方や思想がふんだんに詰め込まれています。たとえば異国の小説を通じて、日本では当たり前と思っていた習慣が、実は特異なものであると気づくこともあるでしょう。
心理学や哲学の本を読み、考え方が180度変化したという人もいるかもしれません。もちろん、違う考え方に触れ、改めて自分の考え方に自信を深める人もいるはずです。
いずれにせよ、自分以外の価値観・視点に触れる経験は、自分の固定観念を和らげ、より柔軟な思考へと導いてくれます。
知識が増えて問題対応力が向上する

本をたくさん読めば、その分だけ知識が手に入ります。たとえば、歴史書には先人の知恵や思考が詰まっていますし、ビジネス書はまさに専門的な知識の宝庫です。
こういった知識が引き出しに蓄積されていくほど、なにか問題に直面した際に、前に読んだ知識や考え方を瞬時に応用できるようになっていきます。
ところが、知識を得るだけならネットやAIで十分と、読書を敬遠する人も少なくありません。たしかに、そういった媒体は便利です。ですが、ネットやAIの情報は断片的なものが多く、さらに信頼性に欠ける情報も数多く存在します。
書籍なら、最低限出版社のファクトチェックが入るし、情報をある程度網羅的に効率よく取得できます。判断材料を増やすなら、本当に読書はオススメです。
記憶力や情報処理能力がよくなる

読書は記憶力や情報処理能力の向上にも役立ちます。本を読むとき、小説ならば登場人物の心情やストーリーの流れ、あるいは専門書なら出てくる理論や用語を頭のなかで整理しながら理解しています。
こういった情報処理の過程を繰り返すことによって、私たちの記憶力や情報処理能力は磨かれていくのです。
たとえば長編小説を読むとき、前に登場した人物や出来事を思い出しながら読み進めないと、ストーリーの流れがなかなか理解できません。「あれっ、これはさっき出てきた人のせいじゃないのか……」などと記憶をたどる作業が、自然と記憶を強化してくれるわけです。
またビジネス書や実用書では、複数の概念を比較・統合して理解するため、情報処理のスピードと正確さが鍛えられます。最初はなかなか理解できないむずかしい専門書であっても、何冊も読み進めるうちに理解度もスピードも向上してきます。
これは知識の蓄積だけでなく、複雑な構成やむずかしい言い回しに対応できるレベルまで、情報処理能力がレベルアップしたおかげです。
◆読書と記憶力・情報処理能力との関係性については、コチラの記事でもお読みいただけます
ストレス解消やリラックス効果が得られる

読書には心を落ち着け、ストレスを和らげる効果があります。本の内容に没頭すると不安や悩みから意識が切り離されて、自然とリラックスできるのです。
とくに紙の本を読む場合にリラックス効果が出やすく、就寝前に電子書籍を読んだ場合と比べて、睡眠ホルモンの分泌が妨げられずに起床時の覚醒度が高いという報告※1があります。
イギリスでは、こういった読書のリラックス効果を活かして心のケアを行う「ビブリオセラピー」という手法が、政府のバックアップにより広く導入されています。
専門家が推薦する本を図書館で借りられる「Reading Well」や「Books on Prescription」などの公的プログラムがあり、軽度のストレスや不安の軽減に役立てられているのです。
もちろん、読書が心の不調を完璧に治療してくれるわけではありません。ですが、読書による心のケアを公的機関が支援している点は注目に値します。私たちもこういった活動を見習って、読書の癒し効果をもっともっと取り入れていくべきではないでしょうか。
※2:Books on Prescription | The National Association of Primary Care
◆読書のリラックス効果については、コチラの記事でもお読みいただけます
キャリアや収入にプラスの影響がある可能性

読書習慣は、キャリアや収入面に長期的なプラスをもたらす可能性があります。というのも、本に書かれているさまざまな知識や考え方を取り入れていくうちに、自分のマインドや行動が成功に直結したものへと変貌していくからです。
実際、世界のビジネスを担う著名なリーダーたちも、読書を自己成長の源としてきました。たとえば、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ※1は「本から常に新しい視点を得ている」と語っており、定期的にオススメ本リストを公開するほど読書を重視しています。
また、テスラやスペースXを率いるイーロン・マスクも「どうやってロケットの作り方を学んだのか」と聞かれた際に 「I read books.(本を読んで学んだ)」 と答えており、専門外の知識を読書から吸収し事業に応用してきたことがわかります。
こうした事例は、読書が単なる趣味ではなく、実際の成果やキャリア形成に直結する力を持つことを示しているといえるでしょう。もちろん読書だけで収入が必ず増えるわけではありませんが、仕事の基礎力を高め、キャリアを前進させる大きな武器になることは間違いありません。
※1:Bill Gates Discusses His Love for Books and Reading | TIME
※2:In Just 3 Words, Elon Musk Explained How You Can Become Expert at Anything (Even Rocket Science)
◆収入アップと読書の関係については、コチラの記事でもお読みいただけます
まとめ
今回は読書で得られる9つの効果について解説しました。今まで読書にあまり興味のなかった人も、きっと「よし!読書してみよう」と思っていただけたと確信しています。
読書は直接人に会うことなく、いつでも新しい知識や価値観に出会える最高の方法です。今回紹介したメリットを意識しながら、読書でさらに広い視野を身につけていきましょう。
 株式会社 瞬読
株式会社 瞬読